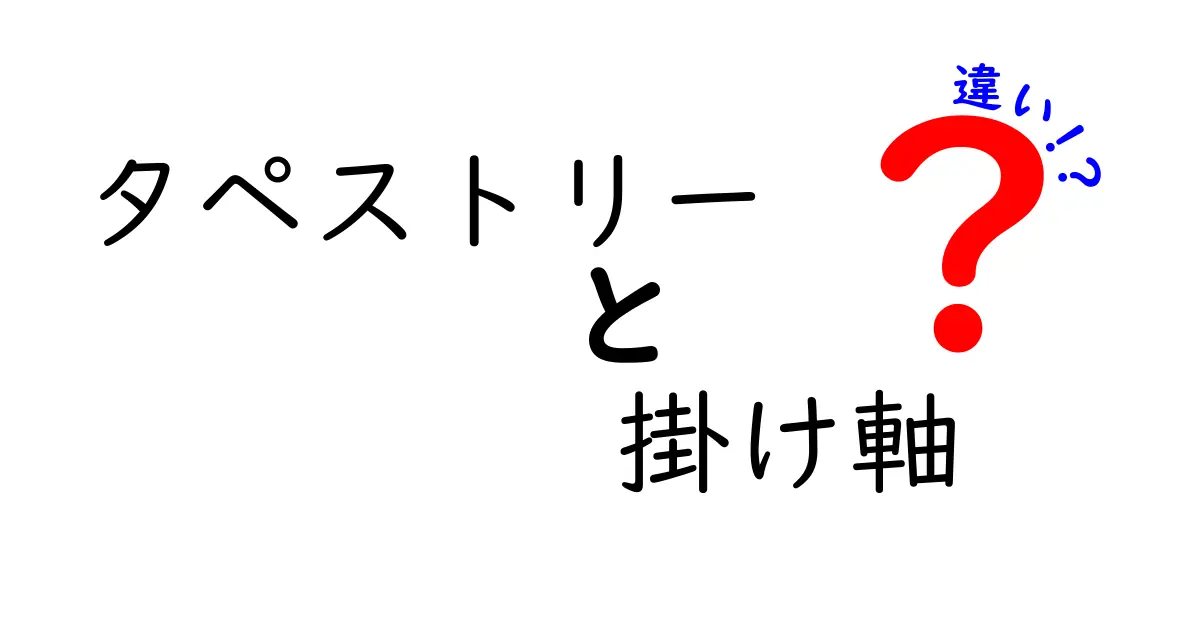

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
タペストリーと掛け軸って何が違うの?基本的な特徴を知ろう
学校の美術室やお店の壁に飾られていることが多いタペストリーと、和室などでよく見かける掛け軸。どちらも壁に掛けて楽しむことができる装飾品ですが、実はその用途や作り方、歴史には大きな違いがあります。
まず、タペストリーは主に布でできていて、織物やプリントで絵柄が表現されています。横に広がる布の形が多くそのまま壁に掛けてポスターのように飾れます。
一方で、掛け軸は和紙や絹に絵や書が描かれており、細長く巻き取って保管できるのが特徴です。掛け軸は棒が上下についており、使わない時は巻き巻きしてしまいます。和の伝統美を感じさせる装飾品として長い歴史があります。
使う場所やお手入れの違いとは?それぞれのメリット・デメリット
タペストリーはカジュアルで多様なデザインが魅力です。子ども部屋やリビング、カフェの壁など、カラフルで現代的な空間にぴったり。素材も綿やポリエステルで軽く、取り付けも簡単です。お手入れは洗濯表示に従って丸洗いが可能なものが多いので、汚れても安心です。
掛け軸は和室や書斎、茶室などで使われることが多く、季節感や気持ちに合わせて掛け替える文化があります。掛け軸は巻いて収納できるので、場所を取らず保管できるのが便利。
ただし強い光や湿気に弱く、直射日光や高温多湿は避ける必要があります。専門の軸装技術で作られており、保存も難しいためお手入れや保管には注意が必要です。
タペストリーと掛け軸の違いをわかりやすく比較表でまとめてみた
まとめ:自分にピッタリの飾りはどっち?選び方のポイント
タペストリーは気軽に自分の好きな絵やデザインを楽しみたい方、色々な場所で使いやすい装飾品を求める方におすすめです。
掛け軸は日本の伝統美や季節感、静かな趣を大切にする方に向いています。お手入れや飾る場所を工夫すれば、長く楽しめる逸品です。
ぜひ今回の違いを参考にして、家や部屋の雰囲気に合った壁飾りを選んでみてくださいね!
掛け軸といえば、和の美術品の代表格ですが、実は掛け軸には季節ごとに掛け替える文化が根付いているんです。夏は涼しげな絵、冬は暖かみのある絵に変えることで、季節の移り変わりを身近に感じられます。また、掛け軸の巻き取り棒は扱いやすさだけでなく、作品を傷めないための大切な役割を果たしています。この細かな気配りが、伝統的な美術品としての価値を高めているんですね。
次の記事: 茶器と茶道具の違いとは?初心者でもわかる基本ポイントを徹底解説! »





















