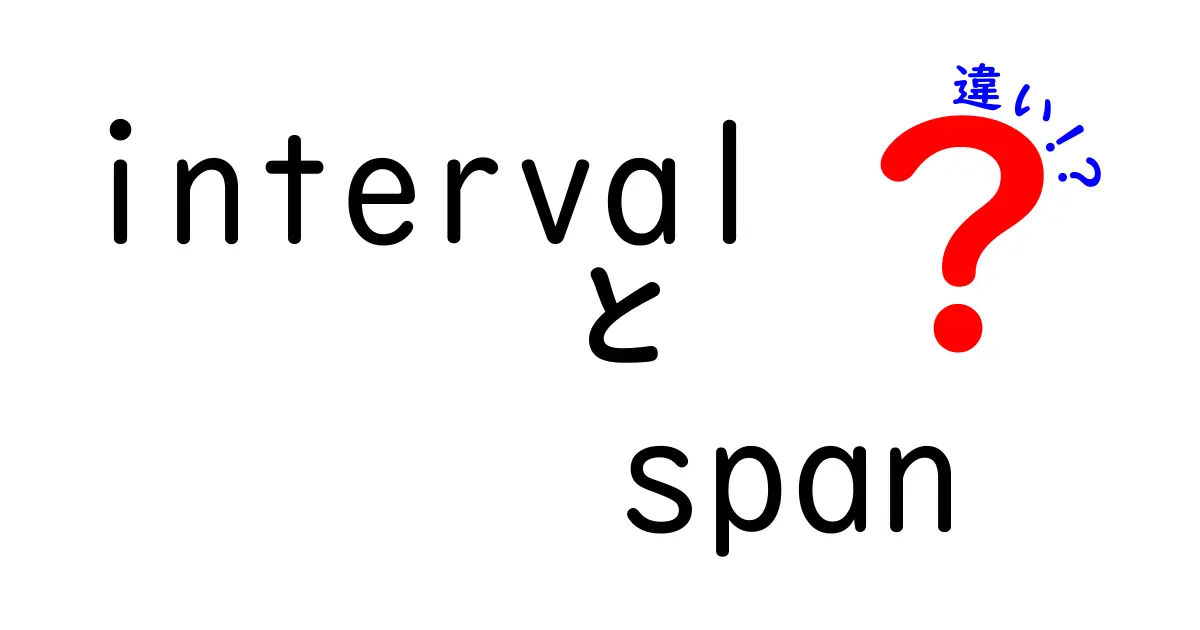

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
intervalとspanの基本的な意味と違い
intervalの基本的な意味は「間隔・区間」です。英語圏では日常から技術文書まで幅広く使われ、時間の長さの間隔や繰り返しの間の空きなどを指すときに用いられます。日本語に訳すときには「間隔」や「インターバル」という言葉が近いニュアンスです。授業と授業の間には15分の間隔があります、という場面では interval が自然です。なおアスリートの練習の区切りにも使われます。
一方、spanは「幅・長さ・期間を広く覆う範囲」を指す語で、長さの概念と期間の概念の両方で使われます。長さの範囲を強調したいときにはspanを選ぶと伝わりやすいです。例として「a span of ten years」は十年間の期間を意味します。「橋の全長」という意味で使われることもあり、広がりそのものを示すニュアンスがあります。
数学の文脈では区間を意味することが多く、[a,b] のような表現を指します。
このように intervalとspanは似ているようで、使いどころが異なります。中学生が覚えておくと役立つポイントは、intervalは“2点の間の空白や空間の距離を強調”、spanは“ある範囲全体の長さや時間の連続性を強調”という点です。
この二つの語を使い分けると、英語の意味が正確に伝わりやすくなります。以降の節では、日常生活や学習の場面での使い分けのコツや具体例を紹介します。
日常や学習での使い分けの具体例とポイント
次のポイントを押さえると混乱を防げます。
1) intervalは時間の「間隔」を強調。授業の合間、運動の休憩、リズムの間隔などでよく使います。
2) spanは期間や広がりの「全体」を強調。十年間の期間、橋の全長、連続した範囲を表すときに使います。
3) 数学・科学の文脈ではinterval notationの方が登場頻度が高く、spanは日常語や文学的表現で使われることが多いです。
- 時間の間隔の例: There is a two-hour interval between classes. 訳: 授業と授業の間に2時間の間隔があります。
- 期間の幅の例: The span of the project lasted six months. 訳: プロジェクトの期間は6か月続きました。
- 長さの範囲の例: The span of the bridge is two hundred meters. 訳: その橋の全長は200メートルです。
覚えておくと良いポイントは、会話では自然な日本語に置き換えると伝わりやすいことです。たとえば interval をそのまま使うよりも間隔と訳す方が伝わりやすい場面が多いです。span は長い期間や広い範囲を説明するときに適しています。
今日は放課後、友達と英語の話題で盛り上がりました。intervalとspanの違いを実際の会話にどう活かすかを試すとき、相手にはまず時間の間隔を意識してもらうのがコツです。私の友達は、部活の練習スケジュールを例にして interval を使い分けようとしていましたが、私は代わりに span を使って全体の期間や活動の幅を表現して伝えようとしました。会話の中で互いに意味を確認し合い、少しずつ感覚が分かれていくのを体感しました。やさしい日本語に置き換える練習を重ねると、英語のニュアンスが自然と身についていくと実感しました。





















