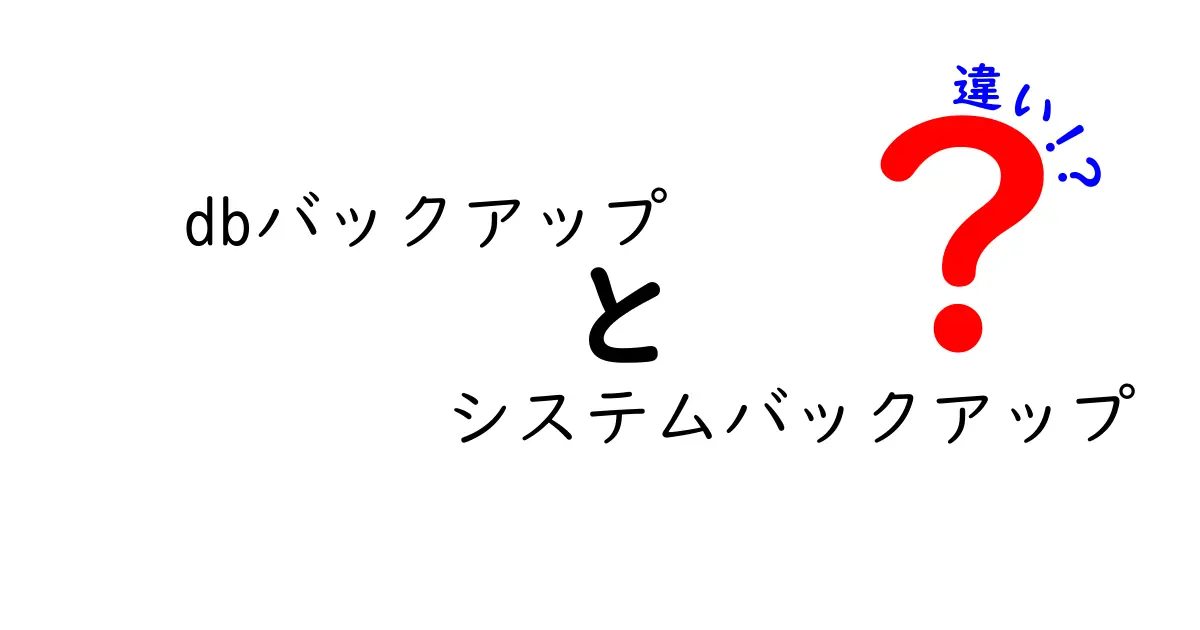

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:DBバックアップとシステムバックアップの基礎
この話では、データの安全を守る方法として「DBバックアップ」と「システムバックアップ」の違いを、難しくなく分かりやすく解説します。学校の課題や自宅のパソコン運用、会社のIT運用など、さまざまな場面で役立つ内容です。まずは用語の定義を確認しましょう。
DBバックアップは「データベースの中のデータを別の場所にコピーすること」です。
システムバックアップは「パソコンやサーバーの全体を丸ごとコピーすること」です。
この2つは似ているようで、守るべき対象・目的・使い方が異なります。ここを正しく理解しておくと、いざという時に速く復旧できます。
以下では、実際の運用でどう使い分けるか、どんな場面でどちらを選ぶべきかを、具体的な例とともに紹介します。
DBバックアップの基本を知ろう
DBバックアップとは、データベースに蓄えられた「データそのもの」を別の場所にコピーして保存する作業です。
対象は主に顧客データ・売上データ・在庫データなど、データベースの中身となる情報です。
このバックアップのメリットは、データの整合性を保ちやすい点と、復旧時にデータベースだけを元に戻せる点にあります。
一方デメリットとしては、データベース以外のファイルやOSの設定は含まれず、最新の取引データを失うリスクがあることです。
頻度は運用方針次第ですが、取引が多い環境では毎時間・毎分ごとにバックアップを取ることも検討します。
また、復旧時にはデータベースエンジンの仕組みや、適切なインポート・リストアの手順が必要になるため、事前の検証が欠かせません。
システムバックアップの基本を知ろう
システムバックアップは「OS・アプリ・設定・データなど、システム全体を丸ごとコピーする作業」です。
対象にはOSの設定・アプリの状態・ドライバ・ユーザーの設定など、PCやサーバーの全体が含まれます。
このバックアップの強みは、復旧時にハードウェアが変わっても、ほぼ同じ状態へ戻せる点です。
欠点は、バックアップの容量が大きくなることと、復旧に時間がかかる場合があることです。
またバックアップの頻度によっては、バックアップ作成時のシステム負荷が業務に影響を与えることもあります。
近年は仮想化環境やクラウドを活用したイメージバックアップも普及しており、RPO・RTOを考えた計画が重要です。
違いを整理して使い分けるポイント
ここまでを踏まえて、現場での使い分けのコツを整理します。
まず前提として、保護したい対象が「データだけ」なのか「システム全体」なのかを明確にします。
次に、復旧の速さが最優先かどうか、データの整合性をどれだけ重視するか、容量とコストをどう抑えるかを検討します。
以下の表は、代表的な違いを短くまとめたものです。観点 DBバックアップ システムバックアップ 対象 データベース内のデータ OS・アプリ・設定・データ全体 復旧対象 データベースを戻す OSとアプリ環境を戻す 復旧時間 比較的早い/インポート手順次第 時間がかかることが多い リスク・コスト データの整合性重視 容量・負荷・コスト大 使い分けの例 顧客データの保護・取引データの履歴管理 OS障害時の完全復旧・開発環境の再現
このように、現場では「データ重視か全体復旧重視か」を軸に、適切なバックアップを組み合わせて設計します。
さらに、定期的な検証とテストを必ず行い、非常時に備えましょう。
テストは、実際の復旧手順を模擬して行うと効果が高く、手順書の不備を早期に発見できます。
安全に使い分ける実務のコツ
実務でのコツは以下の通りです。
1. 目的を最初に決める(何を守りたいのか)
2. 优先度を決定(RPO/RTOの要件を設定)
3. バックアップの種類を組み合わせる(DBバックアップ+イメージバックアップなど)
4. 保管先を分散する(オンプレとクラウドの混在など)
5. 自動化と監視を導入する(失敗を早期検知)
6. 復旧手順を定期的に演習する。これらを実践すれば、障害が起きても迅速かつ正確に対応できます。
DBバックアップについて深掘りする小ネタです。私たちはデータを宝物みたいに扱いますが、宝物はただ保管するだけではダメ。宝物庫の棚は増え続けるので、どのデータがいつバックアップされたかを分かりやすく管理することが大切です。DBバックアップでは、データベースごとにバックアップの世代管理を行い、最新データだけでなく過去の状態も取り戻せるようにします。さらに、バックアップの検証は復旧の最終段階だけでなく、バックアップ作成時にも行うべきです。つまり、バックアップそのものが“正しく機能しているか”を常に確認することが、安心につながるのです。もしバックアップファイルが壊れていると、最新データが戻せなくなる恐れがあります。だからこそ、私たちは定期的にファイルの整合性チェックと復旧テストを欠かさず行うべきです。
次の記事: ccsとccusの違いを徹底解説!初心者にも分かるポイントと実例 »





















