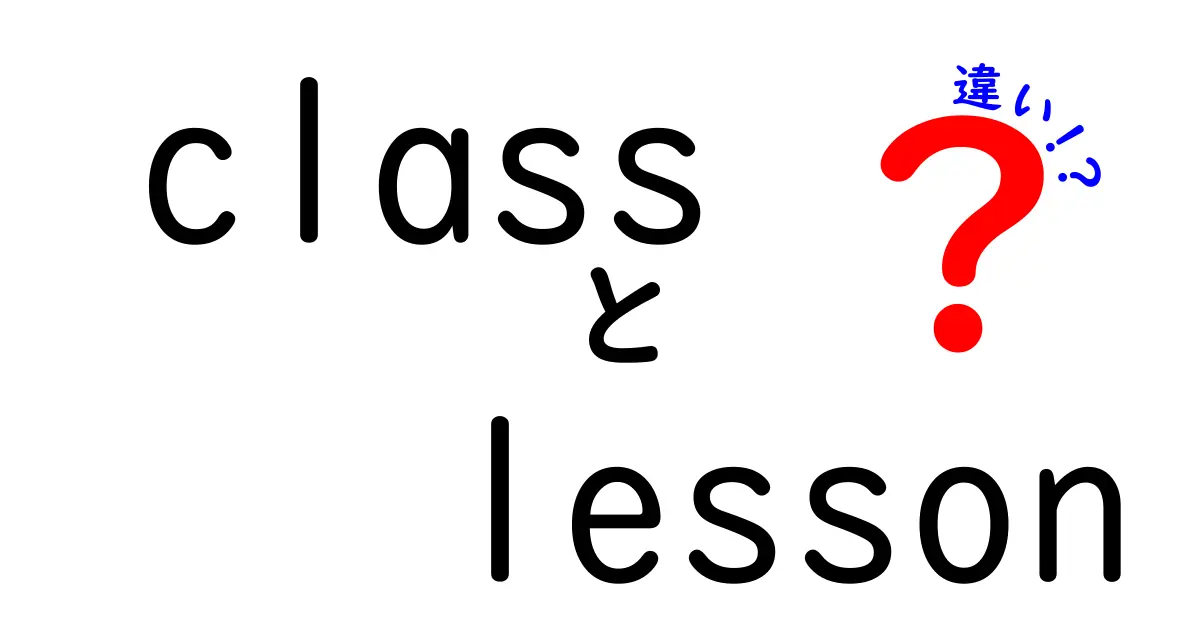

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
class lesson 違いを徹底解説:中学生にもわかる使い分けのコツと実例
「class」は日常英語で非常に頻繁に登場する語ですが、使い方には幅があります。学校の授業を指す場合だけでなく、時間割の枠組みや集団の意味としても使われるため、文脈をよく読み取ることが大切です。ここではまず基本の意味とニュアンスを整理します。
例えば「I have a math class at nine」という文は、9時に数学の授業があることを伝えています。一方で「that class」や「a class of students」といった表現は、授業そのものではなく、その授業を受ける人の集まりを指すことが多いです。
この違いを掴むと、英語の会話や文章で「何を指しているのか」を直感的に判断できるようになります。要点は“集団・時間・場所を表す総称”か“中身の単位を表す区切り”かという切り分けにあります。
次に「lesson」について考えます。「lesson」は授業の中の一つの単位・内容を指す語として使われることが多いです。学校の科目全体を指すときは「class」を使うことが自然ですが、授業の中身や演習のひとまとまりを強調したいときには「lesson」が適切です。日本語に直すと「授業の一コマ」「講義の一節」「練習のセッション」といったニュアンスになります。
つまりclassは大きな枠組み・時間・集団を指す総称、lessonはその枠組みの中の具体的な内容・単位を指すのが基本です。
この違いを押さえておくと、英語のテキストや会話で“何を学ぶのか”“誰が関わっているのか”を正しく理解でき、自然な言い換えができるようになります。
さらに補足しておくと、語源的には両者が異なる場面で派生しており、日本語の訳語としてはしばしば「授業」という同じ単語で訳されることが多いですが、使い分けのコツは文脈と目的を読み取る力にあります。中学生のみなさんは、英語の文章を読むときに「この文は授業の一部を指しているのか、授業全体を指しているのか」を想像してみると、スムーズに理解できるようになります。
練習として、自分の学校の時間割を英語で説明してみると、classとlessonの使い分けが自然に身についていきます。
基本の意味と使い分け
このセクションでは、'class'と'lesson'の基本的な意味を、実際の例と対比で整理します。まず前提として、'class'は学校の授業だけでなく、集団・階級・カテゴリーを表すこともあります。また、'class'を使うときは必ずしも内容の長さを限定しません。一方、'lesson'は内容の単位を指すことが多く、長さは授業や教材によって変わります。例えば、"a science class"と"the science lesson"は意味が異なる場面を指します。classはグループや時間のまとまりを含む総称、lessonは内容の単位・区切られたセッションを指すという理解が基本です。
対して、日常の会話や教材での使い分けは、話者の立場に左右されます。教師が話すときは“lesson plan”や“this lesson”と述べ、学習者が話すときは“in this class”のように、対象が異なることを理解しておくと混乱を避けられます。英語圏の教材では、'lesson'は授業の中身・教材・演習の集合体を指すことが一般的です。最後に、日本語訳としては“授業”で統一されがちですが、使い分けの基本原理は「内容の単位 vs 集団・機会」という観点です。
日常会話での実例と注意点
日常の会話での代表的なケースをいくつか挙げます。例1:友達と話すときに“I have a class at 10”と言えば、単に授業がある時間だと伝えています。ここではクラスの時間割の“時間帯”を指すニュアンスが強いです。例2:“Today's math lesson was tricky”は、その日の授業の中身・演習の内容を伝えています。つまり同じ“授業”という日本語を使っていても、英語では文脈によってclassとlessonを使い分けるのが自然です。
このセクションの注意点は、複数形の扱いです。"class"は複数形で"classes"とすると複数の授業やクラス全体を指しますが、単数形の"a class"は一つの授業・一つの時間帯の意味になります。対して"lesson"は通常、特定の内容のセクションを指すため、複数のセッションをまとめて言うときは"lessons"と複数形を用います。実際の会話で慣れるには、例えば自分のスケジュールを声に出して英語で説明してみる訓練が効果的です。使い分けの感覚は練習によって身につくので、日常のちょっとした会話から始めていきましょう。
表で見える違いとポイント
最後に、実務的な理解を深めるために、表を使って違いを一目で把握します。以下の表は、語ごとの意味・ニュアンス・使いどころの例を簡潔に並べたものです。
この表を見ながら自分の状況を英語で言い換える練習をすると、自然な語感が身につきます。
この表を使って練習する際には、まず自分が伝えたい“対象”をはっきりさせることが大切です。読解時は文脈、口語では場面を想像して判断すると、誤用を減らせます。表の例を口に出して読み上げるだけでも、語感が体に染みつきます。
友達とカフェで雑談しているとき、classとlessonの違いを話題にすることがあります。友人は“class”を時間割の区切りとして捉え、私は“lesson”をその時間に実際に学ぶ“内容のまとまり”として捉える、という微妙なズレを体感しました。結局、私たちは会話を通じて、英語では同じ日本語の授業でも場面によって使い分けることが自然だと理解しました。もし英語で自分の学校生活を説明する機会があれば、最初に“this class covers…”か“this lesson focused on…”と始めると伝わりやすく、聴き手にも理解してもらいやすくなるでしょう。
次の記事: 初心者でもわかる!imgとisoの違いを徹底解説 »





















