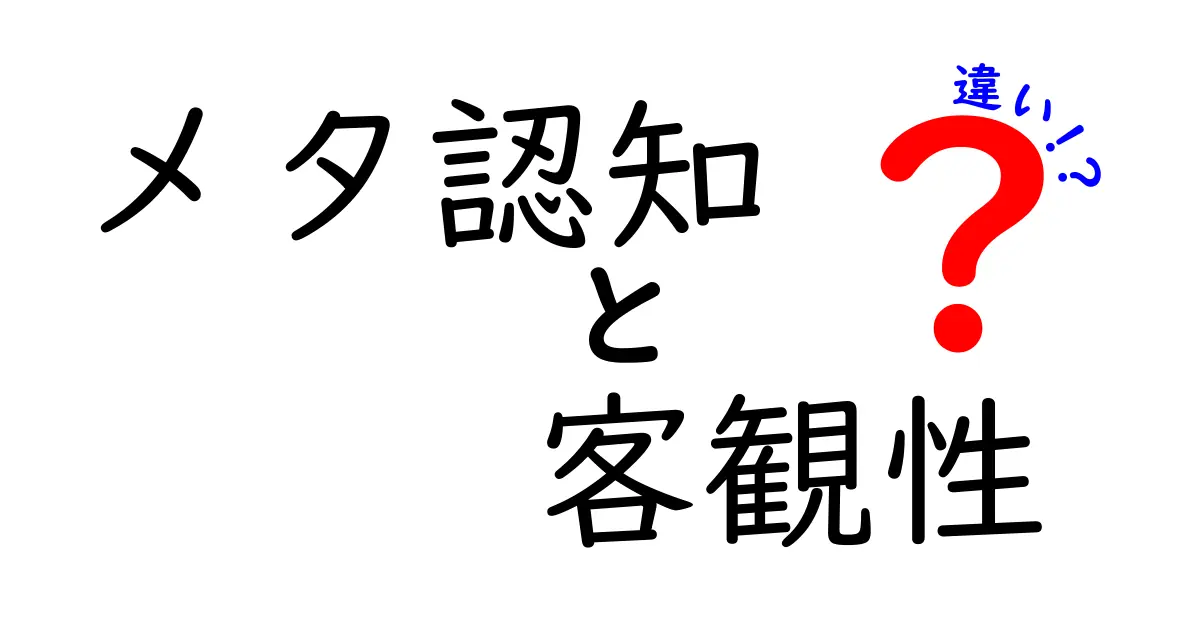

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
メタ認知と客観性の違いを理解する基礎と誤解を解くポイント
私は日常や学校の勉強で「どう考えるべきか」と「どう判断するべきか」を混同してしまうことがあります。そこで鍵になるのがメタ認知と客観性という2つの考え方です。メタ認知は自分の思考の仕組みを観察し、計画・監視・修正を行う能力のこと。これを身につけると、学習のやり方を自分で分析でき、何がわかっていないかを早く見つけ出せます。
一方、客観性は外部の事実や他人の意見を尊重し、個人の感情や偏見をできるだけ排除して判断する姿勢のことです。客観性が高いと、情報を主観的に解釈するのを避け、データや根拠に基づく結論を導きやすくなります。これらは別の能力ですが、実際の場面では互いに補完し合います。
たとえば数学の解答を考えるとき、まず自分の解法の過程を自分の頭の中で言語化することがメタ認知の第一歩です。次に、その過程が正しいかを公式・証拠で検証し、必要なら別解や最適解と比較します。これがメタ認知と客観性の連携です。
この連携を意識すると、誤解や感情に振り回されることが減り、根拠のある判断を迅速に下せるようになります。結局のところ、重要なのは両者を適切に使い分けることです。
日常生活で体感する2つの感覚の差と練習法
現場での例を使って2つの感覚を体感すると理解が深まります。前述のメタ認知は「自分の考えの道筋を意識する力」で、客観性は「外の世界の情報を均等に受け止められる力」です。日常の小さな出来事を考えるとき、例えば友達との意見の食い違いを解く場面を思い浮かべてください。まず自分がどう考え、なぜそう思うのかを自分の頭の中で言語化します。これがメタ認知の第一歩です。次に、その考えが本当に正しいかを証拠と反対意見で検証します。これが客観性の力の発揮です。双方を順番に使うと、感情的な対立を回避し、根拠のある結論へと近づくことができます。練習としては、ニュース記事を読むときに著者の主張とデータの対応を整理する、または自分の意見を友人に説明してもらい、相手の指摘を受け止める、というサイクルを日常的に回すと良いでしょう。さらに失敗から学ぶ姿勢を忘れず、誤りを認め、修正するところまでをセットで反復します。最後に、下記の表を使って「何を重視するのか」を整理しておくと、メタ認知と客観性の差が頭の中で整理され、混乱を避けやすくなります。
友達とカフェで雑談しているとき、メタ認知の話が出たんだけど、僕はつい自分の言い分を正しいと信じてしまう癖がある。そこで最近、話す前に一旦自分の考えを整理する練習を始めたんだ。紙に『こう考えた→根拠→反論を想定』と書き出すだけで、意外と自分の思い込みに気づくことが多い。メタ認知は難しく感じるかもしれないけれど、実は小さな習慣で大きく変わる。例えばニュースを読んだとき、著者の意図と自分の感情を分けて考えるだけで、同じ情報でも受け取り方が変わる。今日はその話を友だちにして、みんなで“自分の考えのクセ”を共有することにした。





















