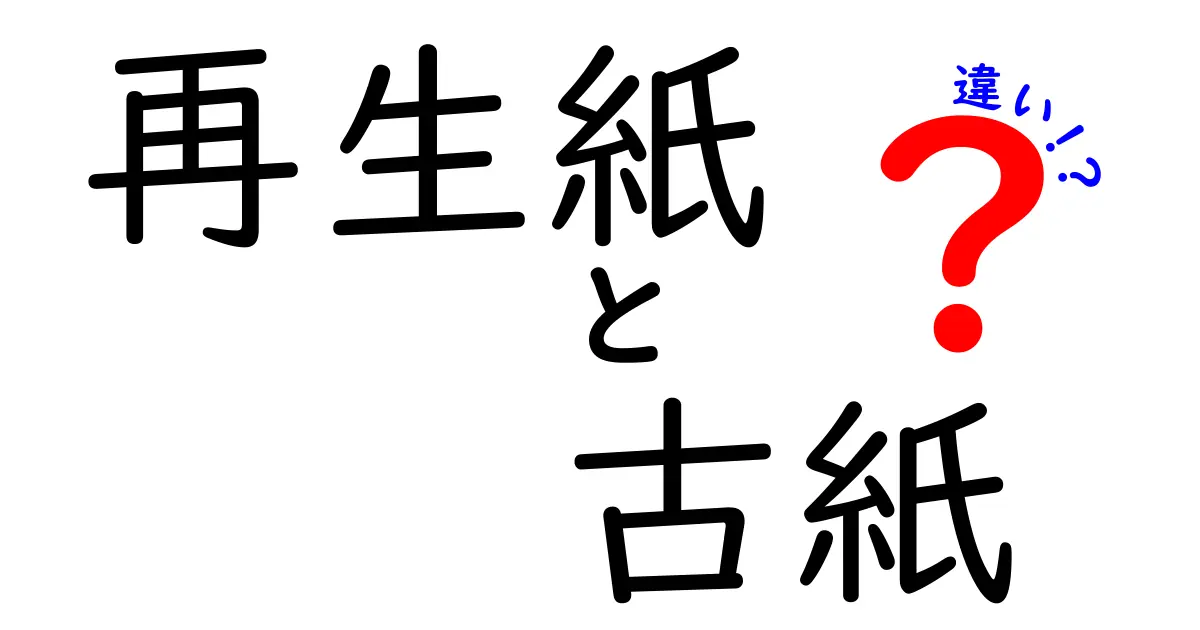

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
再生紙と古紙の基本的な違いを整理する
再生紙と古紙の違いを正しく知ると、私たちが日常で何を買い、どの紙を選ぶべきかが見えてきます。まず重要なのは用語の意味です。再生紙とは、使用済みの紙を回収して洗浄・解繊・漂白・抄造といった工程を経て新しい紙へと生まれ変わった製品のことです。古紙は、その回収された紙の総称で、未だ新しい紙には形をとっていない原料のことを指します。つまり古紙は再生紙の素となる素材であり、再生紙は古紙を材料として仕上がる最終製品です。道具や教科書、雑誌、ダンボールなど、古紙には種類が混ざっています。混ざり方次第で、紙の細さ、厚さ、白さ、耐久性が変化します。学校のプリントやノート用紙を作るときは、短繊維の混入を避けつつ、落ち着いた色味と適切な硬さを保つことが求められます。
ここで覚えておいてほしいのは、同じ“再生紙”でも、原料の混ざり方や製造工程の違いによって性能に差が出るという点です。あなたが家庭で使うラップの包み紙や包装紙が再生紙で作られている場合、その色や風合いはエコ設計の一部といえます。環境意識が高まる今、多くのメーカーが漂白の方法やインキ除去の程度を改善し、白さと安全性のバランスを追求しています。
作られ方と用途で見る違い
古紙と再生紙の製造過程は、材料の整理・処理・抄造の順序で進みます。古紙はまず回収され、新聞、雑誌、段ボール、コピー用紙などの素材ごとに分別されます。この段階で不可燃物や混入物を取り除く作業が重要で、ここが品質の分かれ道になります。選別が適切であれば、古紙は高品質のパルプへと変わり、再生紙の基礎となります。次に、この古紙を水と混ぜて細かく液状化し、繊維を取り出します。この段階をパルプ化と呼び、ここで繊維の長さが紙の強さや風合いを左右します。続いて漂白・脱インキ・洗浄などの工程を経て、印刷用紙や書籍用紙などの用途に合わせた抄造へつなげます。漂白の程度が高いほど白さは増しますが、環境負荷も高くなる傾向があるため、メーカーは有機物の除去と水の再利用を優先します。
用途の面では、再生紙はノートやコピー用紙、プリンタ用紙、包装材など幅広く活用されます。一方、古紙を原料として使う場合は、色味や強度の要求に応じてブレンド比を調整します。たとえば、耐水性が必要なパッケージ用紙には、他の植物繊維を混ぜることもあります。こうした設計の工夫は、紙の用途ごとに最適な性能を引き出すために欠かせません。
選ぶときのポイントと誤解を解く
紙を選ぶときには、グレードの表示だけで判断せず、用途と環境への影響のバランスを考えることが大切です。再生紙と表示されていても、漂白の程度やインキ除去の方法が異なるため、風合いや白さ、書き心地が変わります。学生用ノート・プリンタ用紙・印刷用紙など、用途別の適正グレードを選ぶと失敗が減ります。さらに、リサイクル可能性や包装の過剰を避ける配慮も重要です。実生活のポイントとしては、使用済み紙を分別し、できるだけ長く使える紙製品を選ぶこと、包装資材を最小限にすること、そして可能な限り紙のリサイクルを促進する選択を心がけることです。表面の白さだけでなく、環境への負荷をどう抑えるかを判断基準にすると良いでしょう。
以下の表は、再生紙と古紙の特徴を簡単に比較したものです。特徴 再生紙 古紙 原料の性質 古紙を再生して作る 回収された紙の総称 白さ・強度の調整 用途に応じて調整 素材混在により幅がある 用途の例 ノート、印刷用紙、包装紙 原料としての供給
結論として、日常で使う紙の選択は、用途と環境の両方を考慮することが大切です。可能な限り長く使える紙を選び、リサイクルに協力するesignの紙を選ぶことが、私たちにできる最も現実的なエコ行動の一つです。
環境への影響と実生活での実践
紙のリサイクルは、資源の有効活用と廃棄物削減に直結しますが、現実には限界も存在します。再生紙の利用を増やすと、木材の伐採を抑制でき、エネルギー消費や水資源の節約にもつながるとされています。しかし、リサイクル過程での清浄化や脱インキにはエネルギーが必要で、過剰な漂白は環境に負荷を与えることがあります。だからこそ、私たちは「長く使える紙を選ぶ」「再利用できる包装を選ぶ」など、日常の選択で環境負荷を減らす努力を続ける必要があります。学校のプリントを減らし、デジタル機器を補助的に使う、買い物の際にはリサイクルマークのある紙を選ぶ、包装の過剰を避ける、家庭の紙ごみを分別するなど、できることは多いです。企業側も循環型の設計を進めており、再生紙の品質向上と廃水の再利用、二酸化炭素排出の抑制などの取り組みを公表しています。私たち一人ひとりの選択と、企業の透明性ある情報公開が組み合わさることで、より良い循環社会へとつながります。
友達と紙の話をしていて、再生紙ってどうしてふつうの紙と同じように使えるのか、ふしぎだよね、なんて話になりました。私なりの結論はこうです。古紙は回収された紙の集合体で、まだ加工されていない状態の素材。再生紙はその古紙を材料として、解繊・洗浄・漂白などの工程を経て新しい紙としてよみがえる。つまり、紙の循環が回り始める瞬間が古紙の回収で、完成品になる瞬間が再生紙の抄造です。家庭でできることは、使い終わった紙を分別して捨て、リサイクルを意識した包装を選ぶこと。最初は小さな行動でも、長い目で見ると資源を守る大切な一歩になるのだと、私は友人に伝えたいです。





















