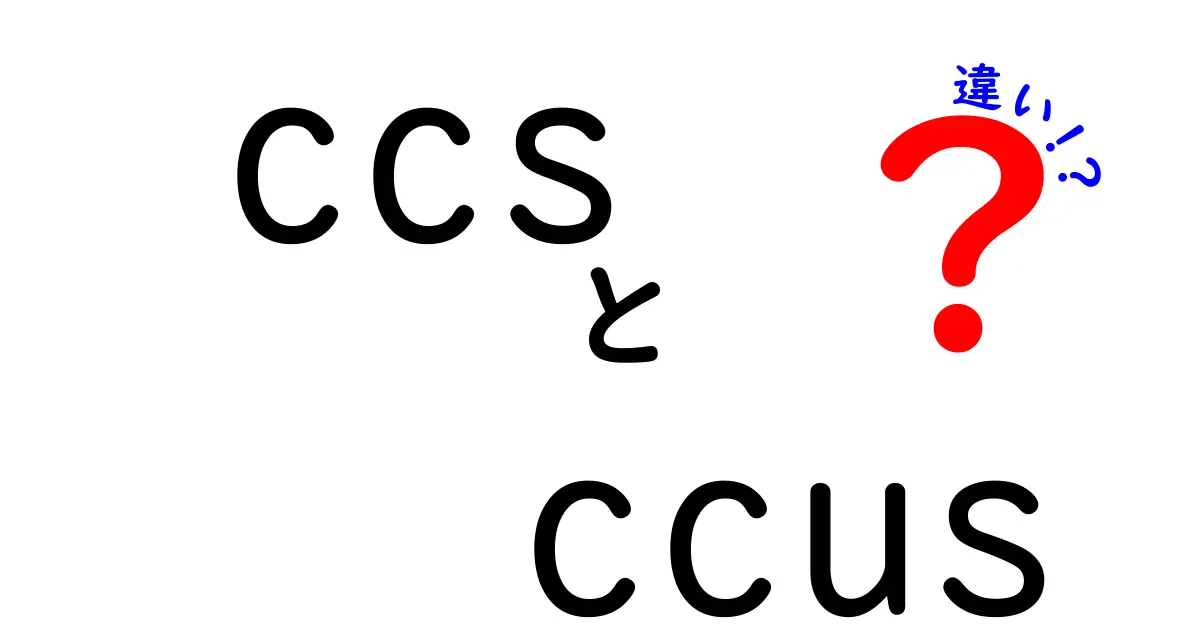

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ccsとccusの違いを理解するための基礎知識
地球温暖化を抑える技術としてさまざまな取り組みが話題になりますが、その中でも CCS と CCUS はよく耳にします。CCS は Carbon Capture and Storage の略で、名前のとおり“炭素を捕まえて、どこかに蓄える”という考え方です。具体的には発生源である発電所や工場の排出ガスからCO2を取り出し、地下の岩層や海底の地層などに圧入して長期的に貯蔵します。CCS の目的は“大気中のCO2濃度を直接減らす”ことですが、捕捉したCO2を別の用途に使わず、保存するのが基本です。
一方 CCUS は Carbon Capture, Utilization, and Storage の略で、 CCS の発想に加えて CO2 を有用な資源として活用する考え方です。つまりCO2を素材として化学品や建材、再生可能エネルギーと組み合わせた燃料などに活用し、排出削減効果を高めようとします。CCS が“捨てない・蓄える”発想なら、CCUS は“活用する・再利用する”発想です。実際の現場では地球温暖化対策の枠組みの中で、 CCS/CCUS を組み合わせる形で両者の利点を生かそうとする動きがあります。
CCSとは何か
CCS とは何かを整理すると、まず捕捉の段階があり、ここで排出源の CO2 を分離する技術(脱着、化学吸収、吸着剤、膜分離など)を用います。次に輸送の段階。 CO2 をパイプラインや船舶で搬送し、適切な経路を確保します。最後に貯蔵の段階。 地層や海底の地層に長期間封じ込める技術が中心です。この過程で最も重要なのは長期安定性と漏れの防止で、地質学的データの解析と継続的な監視技術が必要になります。CCS は主に大気中へ放出される二酸化炭素の総量を直接減らすことを狙います。企業や国が排出削減目標を達成するうえで、発電所の排出を“外部に出さず処理する”選択肢として検討されます。
ただし CCS 自体にも課題があり、コストや技術難易度、長期の法的枠組み、周囲の生態系への影響評価など、さまざまなハードルがあります。実際の導入には政府の支援、適切な規制、社会的合意が不可欠です。さらに地下の地層が持つ個性(貯蔵容量、漏出リスク、地震リスクなど)を事前に正確に評価する必要があり、地質学・地球物理学・化学・エンジニアリングの協調が求められます。CCS は“今ある排出を後から安全に減らす”現実的な選択肢として期待されましたが、費用対効果と長期安定性の検証が続く課題です。
CCUSとは何か
CCUS とは何か。まず CCUS という用語自体は、CO2 をしっかりと捕捉したうえで、それを有用な資源として活用することを意味します。具体的には捕捉した CO2 を化学品の原料として利用したり、建材や油田の作業で回収作業を効率化したりします。活用先は多岐にわたりますが、最終的には CO2 を大気へ排出する量を減らすことが目的です。これにより企業の収益性を高めつつ、排出削減にも寄与することを狙います。
CCUS の実現には資金調達と技術の両方が重要です。活用の需要が小さい地域では捕捉コストが高く、十分な回収効果を得るには適切な産業連携や市場の整備が必要です。さらに CCUS を推進するには規制の整備、技術標準の共有、信頼性の高いモニタリング体制が求められます。表面的には「利用してしまえば良いのでは」と思われがちですが、長期的なCO2の安定供給と安全性を確保するためには、技術の継続的な研究・開発と人材育成が不可欠です。
実世界での活用事例と今後の展望
世界各地で CCS/CCUS の実証プロジェクトが進み、ノルウェーの Sleipner プロジェクトは1990年代後半から進行しており、北海の地層にCO2を貯蔵する代表的な例として挙げられます。こうしたプロジェクトは長期安定性の検証データを蓄積するうえで重要です。その他にも石油・ガス業界の油田回収と組み合わせた実証や、発電所の排出削減と材料化学への応用など、さまざまな実証が行われています。 友達のミキと道で話していたとき、CCSとCCUSの違いについてぼそぼそと議論になった。ミキは『捕捉して地下にしまうだけで地球は救えるの?』と疑問を投げかけ、僕は『そうとも限らない。コストや安全性、規制がクリアされないと現場には入れないんだよ』と答えた。話は進み、CCSは「CO2を貯蔵すること」中心、CCUSは「それを有用資源として活用する可能性もある」という点を抑えると整理できる。結局、技術はまだ成熟過程で、地域ごとに適した解決策を組み合わせるのが現実的だと実感した。
今後は規模の拡大とコスト削減を目指す動きが活発です。再エネと組み合わせた発電所の排出削減、産業部門の脱炭素化を加速するための市場整備、国際的な規制の整合性づくりなど、社会全体の協力が鍵になります。しかし地域差が大きく、資金確保や法制度の整備、長期のモニタリングの課題が残るのが現状です。
表も併せて、CCSとCCUSの違いを整理すると理解が深まります。以下の表は定義・用途・課題・現状の事例を簡潔に比較したものです。項目 CCS CCUS 定義 排出源からCO2を捕捉し、地下等へ貯蔵 捕捉したCO2を有用資源として活用しつつ貯蔵・安定化させる 主な用途 長期貯蔵・大気CO2削減 化学品・建材・油田回収等の活用 課題 コスト・規制・地質リスク 活用市場・技術標準・長期安定性の確保 現状の事例 北海 Sleipner などの貯蔵プロジェクト 一部産業でのCO2利用実証、油田回収のケース
科学の人気記事
新着記事
科学の関連記事





















