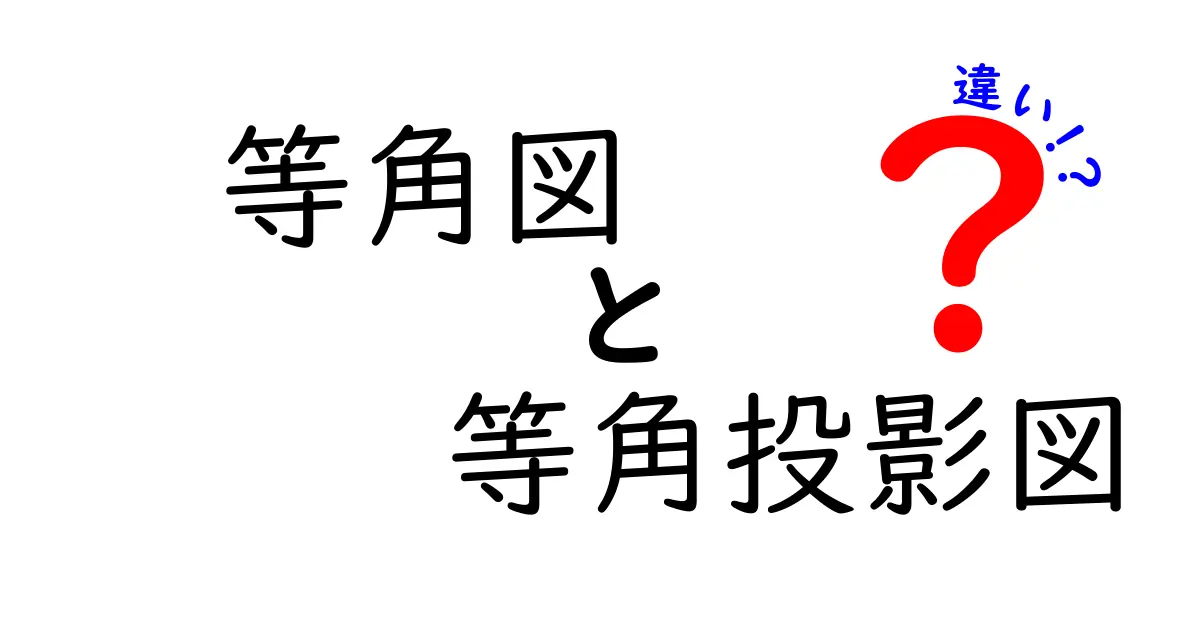

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
等角図と等角投影図の基本を徹底解説
等角図とは、図形の中の角度関係をわかりやすく示すための歴史ある表現方法です。物体の縦横高さを直感的に並べる代わりに、複数の軸を等間隔で配置して、角度が同じになるように描くことが多いです。実際には、主に平面図として現れることが多く、三つの方向が120度の間隔で並ぶことが特徴です。この配置によって、立体を見てもらうときの混乱を減らし、角度の関係性が頭の中で崩れにくくなります。ここで重要なのは、縮尺が三つの方向で同じになる点と、描く手を離すと自然にバランスの良い図形になる点です。
一方、等角投影図は技術図面の世界でよく使われる“投影”の一種です。物体を見たときの形を、実際に空間でどう見えるかに近い形で平面に写し取る方法で、三つの主軸を同じ縮尺で描くことが基本となります。地図作成や機械部品の設計、建築の初期案などで活躍します。等角投影図では、描かれた長さや角度が現実のものと同じ感覚を保つよう工夫されており、三軸が等しく縮小されることが重要なポイントです。
この二つは似ているようで目的や使われ方が違います。等角図は関係性の説明や概念理解の補助に適しており、読み手の頭の中に図の意味を作る役割を果たします。一方の等角投影図は、現実の物体を“平面上に正確に写す”目的に強く向いています。教科書や資料作成の場面で混同されがちですが、まず自分が何を伝えたいのかを意識して図法を選ぶことが大切です。
まとめとして、等角図と等角投影図は名前が似ていますが、目的と描き方が異なるため、初学者が混同しやすい点です。授業の課題ではまずどちらを選ぶべきかを決め、必要な情報を図に反映させる訓練をするとよいでしょう。
この章のポイントは次の通りです。
1) 等角図は概念の整理に適する、
2) 等角投影図は現実世界の写し方を重視する、
3) 描く前に目的をはっきりさせる、
4) 図には凡例や注釈を添えて読み手を助ける、この四つを押さえておけば、初学者でも図の意味を誤解せず伝えられます。
ねえ、等角投影図の話を思いついたんだ。三つの軸を120度で並べて描くと、見た目は立体の形が平面上で“正しく見える”って魔法みたいだよね。でも実は、全ての長さが同じ割合で縮まるわけではなく、角度の見え方を整えるための工夫の連続なんだ。教科書の図を眺めていると、時々線の太さや角の鋭さが違うことに気づくはず。そんな微妙な変化を感覚でつかめると、図形の世界がぐっと身近になる。





















