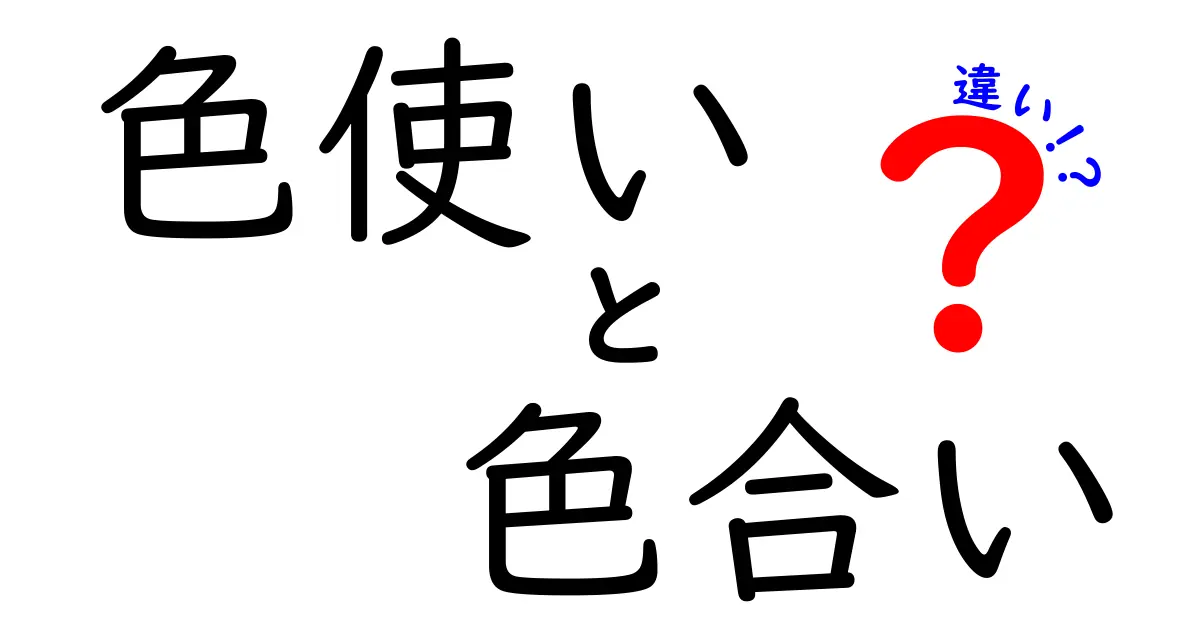

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
色使いと色合いの違いを理解するための基本
最初に結論を一言で言うと、色使いは「どう色を組み合わせるか」という方法全般、色合いは「色そのもののニュアンスや見え方」のことです。これを日常のデザインに置き換えると、色使いは配色設計の設計図、色合いは実際に画面や印刷で見える色の雰囲気と捉えると分かりやすいです。
この違いを理解しておくと、ポスターを作るときにどの色を主役にして、どの色を添えるか迷う時間を減らせます。
特に学校の美術・デザインの授業やプレゼン資料作成のとき、どの色同士を組み合わせると伝えたい情報が強く伝わるかを、色使いの観点から整理できます。
色の名前だけでなく、明度・彩度・色相といった要素も絡めて考えると、より実践的になります。
以下のポイントを覚えておくと、色使いと色合いを別物として扱いやすくなります。
色使いの定義と実践例
色使いはデザインの「設計図」です。色相、明度、彩度といった色の特性を組み合わせ、目的に合わせた配色を作り上げます。例えば、学習ポスターでは読みやすさが最優先なので、背景と文字のコントラストを高める配色を選びます。
ここでポイントなのは「〇〇を主役にする」「〇〇を引き立て役に回す」という役割分担を決めることです。
次に挙げる表は、日常で使える基本パターンの一部です。用途 組み合わせの例 狙い 見出しの強調 紺×白 視認性と厳かな印象 背景の和らげ 薄いグレー×淡い色 優しさと読みやすさ アクセント オレンジ×濃いネイビー 活気と深みの同居
このような組み合わせをケースごとにメモしておくと、実際の制作で迷いにくくなります。
色合いの定義と実践例
一方の色合いは「その色そのものがもつ雰囲気」です。色相だけでなく、明度と<彩度の仕上がりで、同じ色でも見え方が大きく変わります。明るい色は元気さや軽さを、暗い色は落ち着きや重厚感を与えます。
たとえば同じ「青」という色でも、明度が高いと爽やかな印象、暗いと格式高い印象になります。
この違いを活かすには、色使いで作った設計図を、最終的な色の実体で微調整する作業が欠かせません。
以下は色合いを設計する時に意識したいポイントです。
1) 目的の感覚を決める(例:安心感、興奮、信頼感)
2) 実際の素材や画像で色を再現する際の現実味を確認する
3) 周囲の色と比較して浮きすぎないようバランスを取る
色使いと色合いの実践ポイントまとめ
ここまでの解説を実践に落とし込むと、デザインではまず「何を主役にするか」を決め、その次に「どの色を引き立て役にするか」を決定します。
主役となる色は強い印象を与えがちなので、背景や文字、補助色で抑えめにする戦略が基本です。
色合いの調整では、選んだ色の明度と彩度を微調整して、全体の雰囲気を整えます。
結局のところ、色使いは計画的な積み重ね、色合いはその積み重ねの結果として現れる印象です。
この二つを分けて考え、実際のデザインで組み合わせる練習を繰り返すことが、上達への近道です。
この前、友だちと雑談していて、色使いと色合いの話題になって、僕は『色使いは組み合わせの技術、色合いは色そのものの雰囲気を決める感性だ』と説明した。彼は最初、同じ色が違うだけでこんなに印象が変わるのかと驚いていた。私は実例を挙げた。ポスターでは赤と緑の組み合わせが目を引くが、同じ赤でも彩度を下げ、背景をくすませれば落ち着いた印象になる。色使いの設計図を描くとき、色合いの雰囲気を先に決め、そこから適切な色を選ぶとミスが減る。こうしたささやかなコツが、学校の課題や部活のチラシづくりを楽しくするのだ。
次の記事: 色使い 色遣い 違いを徹底解説!中学生にも伝わる具体例つき »





















