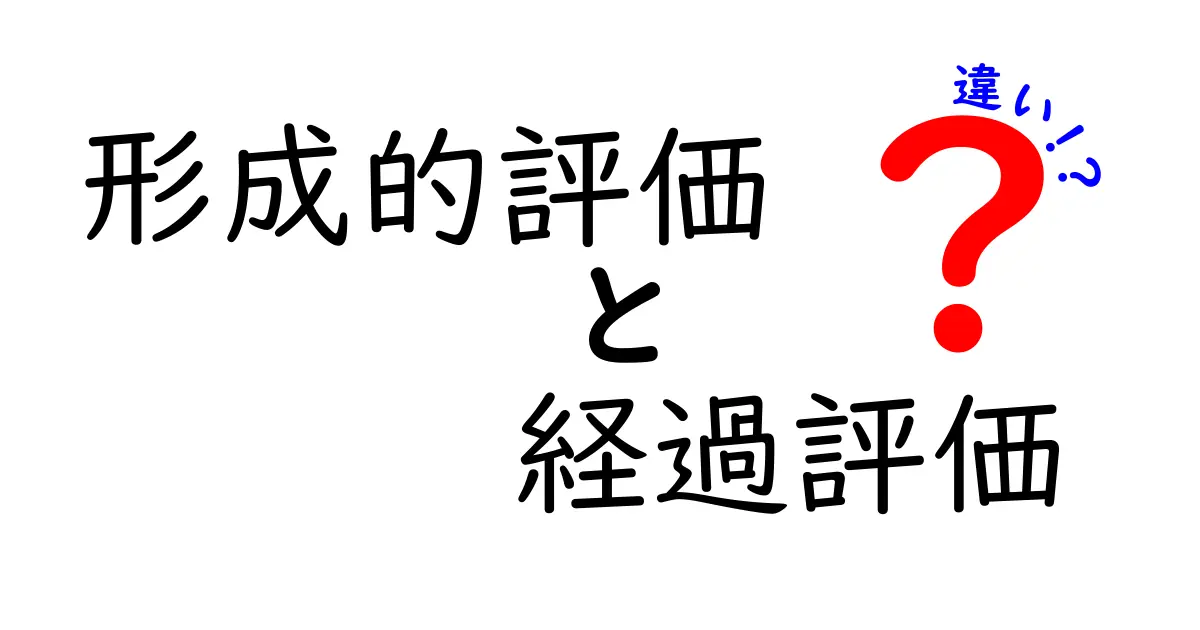

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
形成的評価と経過評価の違いを理解する
学校の授業や部活の活動では、評価のやり方にはいくつかの種類があります。その中でも「形成的評価」と「経過評価」は、似ているようで役割が違います。まず、形成的評価とは、学習の途中で生徒の理解度やつまずきを把握し、次の学習につなげるための評価です。試験の結果だけを見て終わるのではなく、授業の進み方を調整する手がかりとして使います。例えば、授業中に出された短い質問に対する答えをすぐにチェックして、なぜ分からないのかを一緒に探したり、わかったところをどんどん深掘りしたりします。こうした評価は生徒の「今の理解」を中心に考えるため、返却までの時間も短く、教師と生徒の間にフィードバックの循環を作ります。
一方、経過評価は、学習の過程でどれだけ進んでいるかを長期的に追う評価です。定期的な小テスト、進捗アンケート、ポートフォリオの総括などがこれにあたり、学習の成長曲線を描く材料になります。経過評価の目的は「現在地の把握と将来の指針づくり」であり、最終的な成績を決めるだけではなく、学習計画の見直しや個別の支援につなげます。形成的評価と経過評価を組み合わせると、授業は単なる暗記の連続ではなく、生徒が自分の成長を自覚でき、何をどう学ぶべきかを具体的に知ることができます。
大切な違いは「目的」と「時点」です。形成的評価は“今この瞬間の理解を高める”ことを目的に、授業中や家庭での学習の過程で頻繁に行われます。
一方で、経過評価は“学習の経過を記録し、将来の改善につなげる”ために、一定の期間をまたいで行われます。
つまり形成的評価は学習の調整用の“道具”、経過評価は学習の“記録と計画の材料”と考えるとわかりやすいです。
学校や教育システムによって呼称が微妙に異なる場合もありますが、実際の授業運営では両者をうまく組み合わせることが基本となります。これからの章で、実際の使い方と事例を詳しく見ていきましょう。
この2つの評価を正しく使い分けることで、成績だけでなく「学ぶ力」を育てることができます。形成的評価と経過評価を組み合わせると、学習は「今の自分を知り、次にどう動くべきかを知る」ための道具立てになります。学習者にとっても、教師にとっても、評価は終わりではなく新しいスタートです。ここからは、実務での使い方と具体的な事例を紹介します。
実務での使い分けと事例
実際の授業や学習支援で、どのようにこの2つを使い分けると効果的になるのでしょうか。まずは形成的評価を日常的に取り入れるコツです。授業中に5問ほどの短い質問を投げ、学生の答えを全員分すぐに確認します。答えが分からない部分があれば、その場で同じテーマを別の角度から再説明し、次の活動につなげます。これを毎回の授業の冒頭に行うと、学習のつまずきを早期に捕まえられ、復習の時間を効率的に使えます。次に経過評価の活用です。月末や学期の区切りで「ここまでの成長はどうだったか」を国語・数学・理科など科目横断で振り返る時間を設けます。生徒自身にも自分の進捗を記録させ、ポートフォリオの形で提出させると、自己評価の力も育ちます。最後に、両者を統合した実践例です。授業後のフィードバックカードには、今日学んだことと次回の課題、つまずきポイントを三つずつ書くように指示します。これにより、すぐに修正が入り、経過評価はその後の学習計画にも反映され、形成的評価は次回の授業の土台となります。
事例として、数学の「分数の足し算」を考えましょう。形成的評価としては、授業中に生徒が分数を足し合わせるたびに答えを出させ、間違いをノートに書き出してもらいます。先生はその場で誤りの原因を説明し、同時に「このタイプの問題はどの手順が重要か」を強調します。経過評価としては、月末に小テストを実施して、各自の理解の進捗を点数化します。成績表には「今月の進捗:向上」「次月の課題:通分の練習を増やす」などのコメントを添え、保護者にも共有します。こうした連携で、生徒は自分の成長を実感しやすくなります。
今日は形成的評価についてひとこと深掘りします。私が学校で感じるのは、形成的評価は教室の“コーチング機能”に近いということです。生徒が躓けばすぐ近くの先生が手を差し伸べ、つまずきを一緒に解決していく。試験結果が良くなくても、毎日の短いフィードバックで「今日のつまずきを次の日には解消できるか」を考える。これが学習の持続力を生み、最終的には自分で計画を立てて動ける力へとつながります。私の経験では、形成的評価を日常に取り入れると、子どもたちは失敗を恐れず、質問する回数が自然と増え、学習のリズムが安定します。経過評価と組み合わせると、長期の見通しも立てやすく、保護者にも納得の説明がしやすくなります。つまり、評価は点数を決めるだけではなく、学ぶ力を育てる“道具”なのです。





















