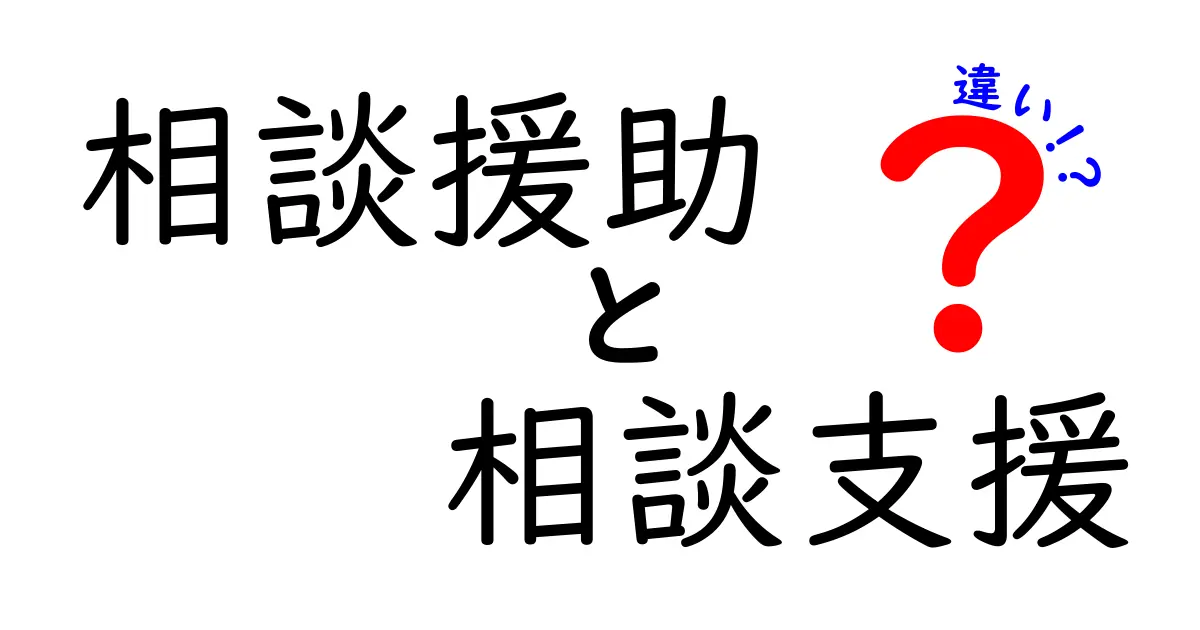

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
相談援助と相談支援、それぞれの意味とは?
相談援助と相談支援は、言葉が似ているので混同しやすいですが、実は意味や使われ方に違いがあります。
相談援助は、主に福祉や医療の分野で使われる言葉で、専門家が相談に乗り、問題解決や支援を行う活動全般を指します。具体的には、生活上の悩みや社会的な問題に対して助言や支援をすることが多いです。
一方、相談支援は、障害者総合支援法に基づく制度で、障害がある人に対して必要なサービスの調整や情報提供を行うことを指します。この相談支援には、計画作りやサービス利用の支援など具体的な支援内容が決まっているのが特徴です。
簡単に言うと、相談援助は広い意味での相談と援助の活動、相談支援は制度に基づく支援サービスのことを指します。
相談援助と相談支援の役割の違い
相談援助の役割は、相談者が抱える問題に対して共感し、話を聞き、必要な情報や支援に結びつけることです。福祉や心理の専門家が行うことが多く、利用者の気持ちに寄り添うことを大切にしています。
相談支援は、社会福祉士や相談支援専門員が担当し、障害のある人が自立した生活を送れるよう、福祉サービス計画を作成し調整する役割があります。具体的には、サービスの利用計画を作成したり、関係機関と連絡調整を行ったりするのが特徴です。
このように、相談援助は相談者の気持ちや問題に寄り添う広い支援活動で、相談支援は制度に基づき障害者の具体的な生活支援や計画作成を行う役割です。
相談援助と相談支援、具体的なケースでの違い
たとえば、ある高齢者が生活に困り相談するとき、相談援助ではその人の話を聞いて、不安や困りごとを整理し、適切なサービスや支援を紹介します。心理的な支えや日常生活のアドバイスも含まれます。
一方、障害がある人が新たなサービスを利用したい場合は、相談支援専門員が計画を作成し、どのサービスをいつ利用するかを調整します。計画に沿って進めるので、具体的で制度的な支援が中心です。
以下の表で両者の違いをまとめました。
| 項目 | 相談援助 | 相談支援 |
|---|---|---|
| 対象 | 広く生活困難な人全般 | 障害のある人 |
| 目的 | 相談者の話を聞き問題解決の助言や支援 | 福祉サービス計画の作成・調整 |
| 実施者 | 福祉職や医療職など | 相談支援専門員 |
| 特徴 | 心理的支えや相談者に寄り添う | 制度に基づく支援計画の作成 |
まとめ:相談援助と相談支援の違いを理解しよう
相談援助と相談支援は似ているようで大きく違います。
相談援助は幅広く人の悩みを受け止める支援活動
対して、相談支援は障害者の福祉サービスを計画・調整する制度的な支援です。
もし社会福祉の仕事に関心がある場合は、これらの違いをしっかり理解しておくことが重要です。
どちらも困っている人の生活を支える大切な役割を持っているので、違いや特徴を知って使い分けられるようにしましょう。
「相談援助」と聞くと、なんとなく“誰かに話を聞いてもらい、助けてもらうこと”とイメージしがちですが、実際はもっと専門的です。相談援助では、ただ話を聞くだけでなく、相談者の心理や生活背景を理解し、適切な支援へつなげる役割を持っています。たとえて言えば、相談援助は“人生の案内人”的な存在で、ただのアドバイスとは違う深い関わりを持つんですね。
前の記事: « 【完全比較】役員持株会と従業員持株会の違いをわかりやすく解説!
次の記事: 介護保険と総合事業の違いとは?わかりやすく解説! »





















