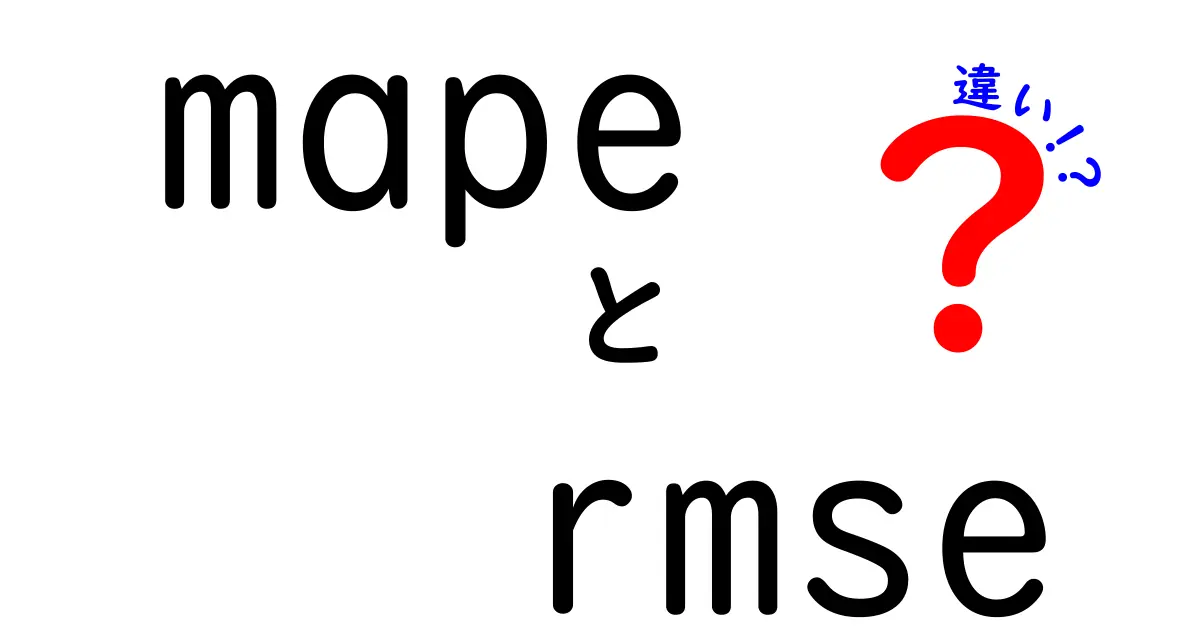

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
mapeとrmseの違いを徹底解説:データ分析初心者がつまずくポイントを丸わかりに解説
データを予測する場面では、誤差をどう測るかが分析の成否を左右します。特に mape と rmse はよく使われる指標ですが、意味や適切な使い方を理解していないと、間違った結論を導くこともあります。この記事では中学生にも分かるやさしい日本語で、mape の基本的な考え方と rmse の基本的な考え方、そしてそれぞれの長所と短所、実務での使い分けのコツを丁寧に解説します。難しい数式が苦手な人でも、少しずつ読み進められるよう工夫しています。
まずは、誤差をどう捉えるかという「考え方の違い」から見ていきましょう。MAPE は予測と実測の差を絶対値で取り、それを実測値で割ってから平均します。つまり「予測がどれだけ実測に対して割合でずれているか」を知る指標です。実測値が大きいほど誤差の絶対値が大きくても、割合として穏やかに見えることがあり、比較的理解しやすい点が魅力です。相対的な誤差を重視する場面に向くと言えます。
一方の RMSE は「二乗平均平方根誤差」という名前の通り、誤差を二乗して平均し、最後に平方根を取ります。これにより、大きな誤差が強く影響する特徴が生まれます。単位は元のデータと同じになりますので、数値が直感的に理解しやすい反面、外れ値の影響を受けやすいという点にも注意が必要です。大きなミスを重視したい場面に向く指標です。
この二つは一見似ているようで、情報の焦点が異なります。MAPE は「割合で見るとどうか」を教えてくれ、RMSE は「大きな誤差がどれくらい影響するか」を教えてくれます。だからこそ、同時に使って比較することが多いのです。以下の表は二つの違いをざっくりと整理したものです。
この表を見ながら、あなたのデータの性質に合わせてどちらを重視すべきかを考えてください。
ここまでで、MAPE と RMSE の基本的な考え方と特徴をつかめたはずです。重要なのは「目的に合わせて二つを組み合わせて使う」ことです。たとえば、比較を行うときには MAP E を用いて相対的な誤差の傾向を確認し、モデルの改善が進んでいるかを見守る際には RMSE で大きな誤差が減っているかを確認します。具体的には、データの分布、外れ値の有無、予測の目的(たとえば売上の割合を重視するかどうか)を前提として判断します。
次に、実際の計算手順や注意点、そして初心者でも実践できるポータル的なチェックリストを紹介します。ここまで読んだあなたなら、MAPE と RMSE を「どう使うべきか」を自分の状況に合わせて選べるはずです。少しずつ手を動かして、データの誤差の傾向を自分なりに読み解く練習をしていきましょう。
MAPEとは何かを実務的に理解するコツ
MAPEは予測値と実測値の差を割合として表すため、データのスケールの違いをまたいで比較するのに適しています。しかし、分母が実測値でありゼロに近い値が含まれると値が極端に大きくなりやすい点には注意が必要です。実測値がゼロに近い場合の扱いを事前に決めておくと、評価が安定します。
また、MAPE は非対称性を持つことがあり、過小予測と過大予測で誤差の感じ方が変わることがあります。これを理解しておくと、予測モデルの改善点を見つけやすくなります。
MAPE を使うときには、データの分布と分母の値の安定性を確認することが基本です。分母が非常に小さい値を多く含む場合には、補正を検討します。中学生にも分かる言葉で言えば「割合のうまさ」を測る指標ですが、分母の性質次第で数字の意味が変わることを意識することが大切です。
RMSEとは何かを深掘りして使い分けを練習するコツ
RMSE は大きな誤差を強く反映するので、データの中の外れ値がモデル評価を大きく動かす可能性があります。外れ値の影響をどこまで許容するかを前提に、外れ値の扱い方を決めておくとRMSE の解釈が楽になります。外れ値をそのままにしておくと、RMSE が大きくなりすぎて「モデルは悪い」と誤解することもあります。対策としては外れ値の検出と除外、あるいは別の指標と組み合わせて見る方法があります。
RMSE を活用する場面は、予測の「大きなミス」に特に関心がある場合です。商品価格の予測や需要予測など、大きなズレが実際のビジネスに直接影響する場面では RMSE の方が現実のダメージを反映しやすいと感じることが多いです。最終的には、MAPE と RMSE の両方を見比べ、どちらが自分の目的に適しているかを判断します。
友人同士がカフェでデータの話題をしているところから始まる雑談を想像してみてください。Aさんは「MAPEって何がいいの?」と尋ね、Bさんがコーヒーをすすりながら丁寧に解説します。Bさんはまず、MAPEは「予測と実測の差を割合で見せる指標」だと説明します。割合という言葉は身近で、たとえば友達が買う本の値段が一冊千円としたら、予測がどれくらいずれているかを“何パーセントずれているのか”で表せる点がありがたいと言います。ただし分母がゼロに近いと値が不安定になる点には注意が必要だと付け加えます。Aさんは「じゃあ、ゼロに近いデータがあるときはどうするの?」とさらに掘り下げます。Bさんは「その場合はデータ清掃や補正、あるいは別の指標と組み合わせて判断するのが賢い」と答え、MAPEだけに頼らない姿勢を教えてくれます。次にRMSEの話題に移ります。BさんはRMSEを、「誤差を二乗してから平均して、平方根を取る指標」と説明します。ここがポイントで、大きな誤差が数字に強く影響するので、外れ値があると結果がぐっと変わってしまうことを教えてくれます。Aさんは「だから外れ値をどう扱うかが大切なんだね」と納得します。二人は最後に結論として、MAPEとRMSEを両方見るべきだと agreement します。つまり、割合で見たいときはMAPE、重大なミスに敏感になりたいときはRMSEという役割分担を、状況に応じて使い分けるのが良いという教訓を、カフェの穏やかな雰囲気の中で語り合うのです。





















