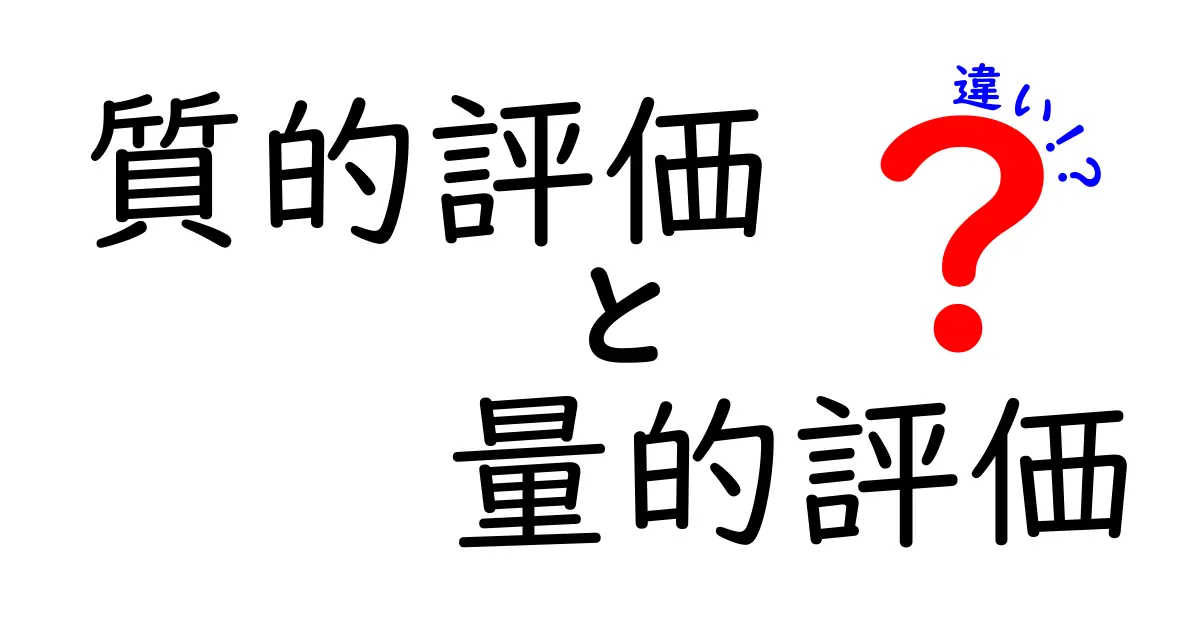

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
質的評価と量的評価の違いを理解するための基本ポイント
評価とは物事をよく知るための方法です。学校の成績表を想像してみてください。成績には数値がつくことが多く、その数値の大きさで「できる・できない」がわかります。これが量的評価です。対して、友達の話をよく聞くとき、感想や感じたことを文字にします。
「この絵は明るい色が印象的だ」「話し方が丁寧で伝わりやすい」といった言葉が立ち上がります。これが質的評価です。量的評価は数値化され、比較がしやすくデータを集めやすいのが強みです。たとえばテストの点数やアンケートの星の数など、誰が見ても同じ基準で測れるデータです。質的評価は人の感じ方や背景を深く知るのに向いています。授業の雰囲気、美術作品の解釈、店のサービスの好みなど、言葉にしなければ伝わらない情報を拾います。
どちらにも長所と短所があり、単独では十分でないことが多いです。文章での説明と数字の両方を組み合わせると、より豊かな結論に近づきます。
この違いを日常の例で考えてみましょう。例えば学校で新しい計画を立てるとき、数値目標と言葉の意味づけの両方を使うと、何を改善すべきかが分かりやすくなります。質的データだけでは「どうしてそう感じるのか」が深くわかりますが、偏りが出やすい点には気をつける必要があります。反対に量的データだけでは「どれくらい良いのか」は分かっても「なぜ良いのか・どの場面で違いが生まれるのか」が見えにくいことがあります。結局のところ、正しい判断には両方の情報を使うことが大切です。
質的評価の特徴と実例
質的評価は言葉・文脈・意味を重視します。観察やインタビュー、自由記述などを通じて深い洞察を得ます。
具体例としては授業の雰囲気を知るための生徒の声、商品開発の初期段階でのフォーカスグループ、街の安全性を調べるための地域の人との会話などが挙げられます。
質的データは柔軟性が高い一方、偏りが入りやすい点があります。信頼性を高めるには複数のデータ源を使う triangulation の手法が有効です。
またコード化をして類型化すると、情報を整理しやすくなります。
量的評価の特徴と実例
量的評価は数値・データを使い、標準化された測定基準で比較します。テストの点数、アンケートの星の数、販売数、ウェブ閲覧数などが代表例です。
目的は総量を測ることであり、統計処理によって傾向を見つけ出します。大量のデータを集めると、個々の背景の影響は薄くなるため、一般化された結論を作りやすい利点があります。
一方で数字だけだと現場の細かな事情が見えにくいという欠点もあります。だから現場の話を質的データと組み合わせるのがよく使われる方法です。
ねえ、さっきの話題、質的評価って言ってたよね。ここは雑談風に深掘りしてみよう。例えば教室の雰囲気を知るとき、数字だけ見てもよくわからないことがある。『先生の授業はわかりやすかったか?』と聞くと、意見は十人十色だ。
そこで僕らは他の人の感じ方を聞き、言葉の意味を整理する。こうして深さと背景を一緒に捉えるのが質的評価のキモだ。もちろん偏りには気をつける必要がある。
そして次に見えるのは、同じ授業でも人によって受け取り方が違うという事実。結局、数字だけでは見えない“なぜ”を探るのが質的評価の役割だ。その“なぜ”を探す旅は、日常の中にたくさんあって、話をする人の数だけ新しい発見が生まれる。
前の記事: « bsc KPI 違いを徹底解説!初心者にも分かる3つのポイント





















