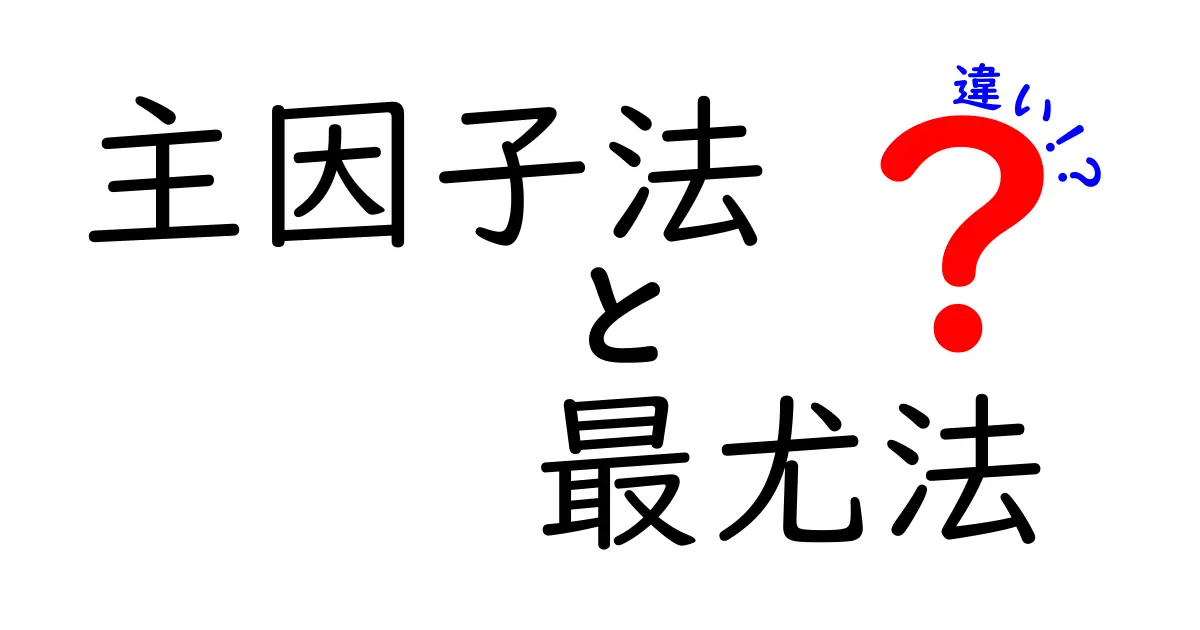

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
主因子法と最尤法の違いを徹底解説—データ分析の現場で役立つ考え方
データ分析の世界には、さまざまな手法が登場します。特に「主因子法」と「最尤法」は、似ているようで全く違う役割を持つ代表的な方法です。本記事では、中学生にも理解できる言葉で、この2つの違いと使い分けのポイントをやさしく解説します。まず押さえるべきは、それぞれの「目的」と「前提条件」の違い。主因子法はデータの背後にある共通因子を見つけ出し、データを説明する力を高めることが目的です。これに対して最尤法は与えられたデータが“どんな確率分布のもとで生まれてきたのか”を、最も可能性の高いパラメータで表すことを目指します。
具体的には、主因子法は観測データの相関を使って、共通因子と呼ばれる要因を抽出します。抽出された因子は、複数の変数をまとめて説明する力を持ちます。最尤法は、モデルを仮定してデータがどのように生成されたかを数式的に最適化します。ここでの“最適”は、データが観測される確率をできる限り高くするパラメータのことです。これらの違いは、分析結果の解釈の仕方にも影響します。
実務では、データの性質と研究の目的を見極めてから分析手法を選ぶことが大切です。例えば「データの背後にある見えない原因」を知りたいときは主因子法が有効です。反対に、モデルの適合度や予測力を高めることが目的なら最尤法が向いています。
この判断を助けるコツは、“何を推定したいのか”を最初に決めることと、仮定として何を置いているのかを確認することです。
以下の表と例を見れば、違いがさらにイメージしやすくなります。
読み方のヒントとして、左が“何を扱うか”、右が“推定の仕組みと前提”です。表を眺めながら自分のクラスのデータを思い浮かべてみましょう。
| 項目 | 主因子法 | 最尤法 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 目的 | 共通因子を特定しデータを単純化 | データのパラメータを最もらしく推定 | 使い分けの核は「何を知りたいか」の一言 |
| 前提 | 因子構造の仮定と公正な共通性の仮定 | データが特定の分布(例: 正規分布)に従うこと | 前提が崩れると結果が大きく揺れる |
| 推定量 | 因子負荷量や共通性を推定 | モデルパラメータを最大化して推定 | パラメータの意味づけが異なる |
| 用途 | データの要因構造の理解・説明変数の削減 | 適合度や予測の最適化 | 分析の目的に合わせて選択 |





















