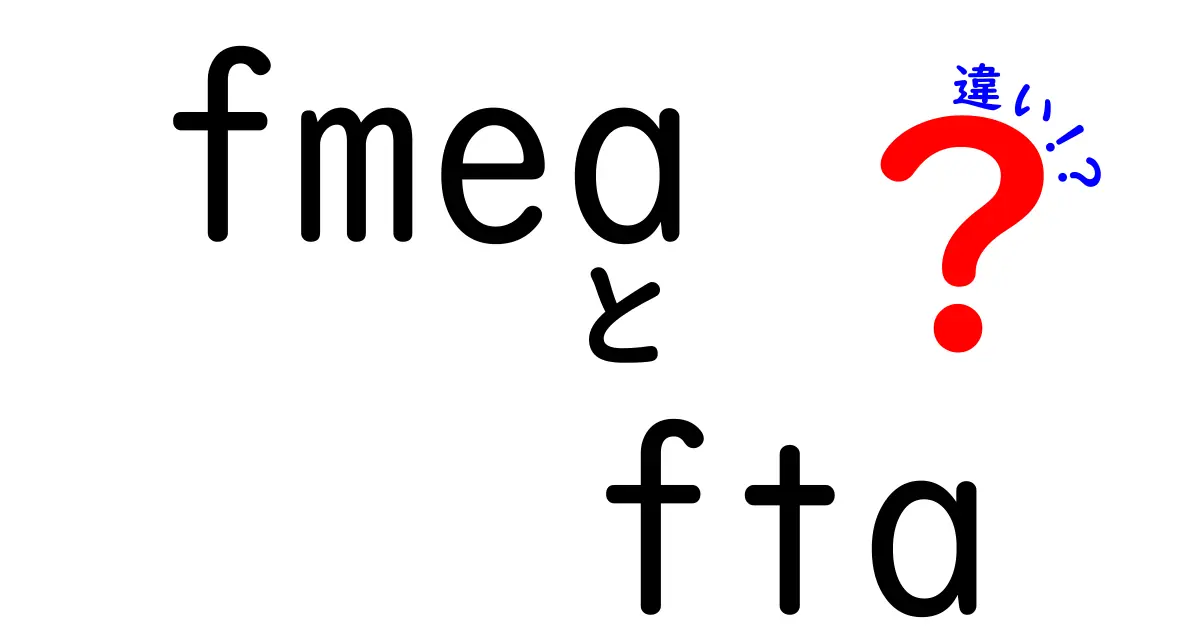

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
fmeaとftaの違いを理解するための基礎知識
この節では、fmeaとftaという2つのリスク分析手法が何を目的としているのか、どのように使い分けるべきかを、中学生にもわかる言葉で解説します。FMEAは故障モードとその影響を系統的に洗い出す方法で、製品開発や製造プロセスの品質改善に強力です。一方、FTAは事象が発生する原因の連鎖を木構造でたどる分析で、重大なイベントの“根”を探るのに適しています。これらは別々の道具ではなく、組み合わせて使うことで全体像を把握しやすくなります。
このガイドを読むと、どちらを選ぶべきか、どんな場面で役立つのかが見えてきます。
キーワードを押さえるポイントは、分析対象と目的、成果物の形式です。FMEAは
FMEAとは何か?
FMEAは故障モードと影響の分析を意味します。製品や工程で起こり得る故障の種類を洗い出し、それぞれの故障が発生した場合にどんな影響が出るかを評価します。次に、その影響の大きさと発生頻度を組み合わせて優先順位をつけ、対策を立てます。一般的には、故障モードごとに発生の確率、影響の重大さ、検出の困難さを数値化して、RPN(リスク優先度番号)という指標を算出します。このプロセスは、製品の信頼性を高めるための予防的アプローチであり、設計段階から実装へと流れる設計思考の一部として機能します。
中学生にも理解しやすく言うなら、FMEAは何が起こりうるかを全体的にリスト化して、どれを先に直すべきか順番を決める作業です。
FTAとは何か?
FTAはFailure Tree Analysis(故障の樹木分析)の略で、ある重大なイベントが起こる原因を根本まで枝分かれさせて追う方法です。大きな事件をTop Eventとして起点に置き、それに至る原因を木の枝のように順に掘り下げ、どの根本原因が最も影響しているのかを把握します。FTAは複雑なシステムや組織内のプロセスで、複数の要因が絡み合うときに特に有効です。
例えばソフトウェアの大規模障害や自動車の安全関連のリスク評価など、イベントのつながりを分解して理解する場面で活躍します。
要点は、原因の連鎖を視覚化できることと、重大なイベントの直接的な根本原因を特定できることです。
主な違いと使い分けのコツ
FMEAとFTAは似た目的を持つことがありますが、アプローチが異なります。FMEAは個々の故障モードとその影響を列挙して優先順位を決める作業で、発生確率と影響度の組み合わせでリスクを数値化します。FTAはトップイベントから原因を辿ることで、根本原因の特定に重点を置きます。実務では、FMEAで問題領域を広く見つけ出し、FTAで特定の重大イベントの根本原因を深掘りする組み合わせ戦略が有効です。
使い分けのコツは、目的と対象をはっきりさせること。品質改善の初期段階ではFMEAで網羅性を確保し、重大事故が発生した場合にはFTAで原因の深掘りを行うと良いでしょう。
注意点として、過度な数値分析に走りすぎず、現場の知見を取り入れること、そしてチームでの共同作業を重視することが大切です。
実務での導入ステップ
実務でFMEAとFTAを導入する際の基本的なステップを整理します。まず目的と適用範囲を明確にします。次に関係者を集め、情報を集約するチームを編成します。FMEAの場合は、機能・部品・部位ごとに潜在的な故障モードを洗い出し、発生確率・影響の重大さ・検出の困難さを評価してRPNを算出します。FTAの場合は、トップイベントを設定し、原因を木のようなツリー状に描き、各分岐の確率を評価して重要な根本原因を特定します。
評価結果は改善計画として具体的な対策に落とし込み、責任者と期限を設定します。文書化は全員が参照できる形式にして、作業の透明性を確保します。
表で見るポイントと実例
| 観点 | FMEA | FTA |
|---|---|---|
| 対象 | 故障モードと影響 | 根本原因の連鎖 |
| 主な出力 | リスク優先度番号、対策リスト | 根本原因分析、木構造図 |
| 使い方の場面 | 設計・製造の予防 | 重大イベントの原因追及 |
| 強み | 網羅性と優先度の整理 | 原因の根本解決の可視化 |
まとめ
この2つの手法は、リスクを見える化する点でとても役立ちます。FMEAは広く全体を見渡す網羅性を強みとし、FTAは特定の出来事の根本原因を深く掘り下げる技術です。実務では、まずFMEAで全体の課題を洗い出し、それから特定の重大イベントをFTAで追跡する組み合わせが効果的です。
学習のコツは、現場の声を大切にすることと、結果を関係者と共有して改善計画を具体的に落とし込むことです。
友達とカフェでFMEAとFTAの話を深掘りしてみた。FMEAは何が起きうるかを全体で洗い出す作業で、FTAはある出来事が起きる原因を木の枝のように辿る作業という理解がぴったりだと感じた。部活の大会準備でFMEAを使い、まず道具の問題点をリスト化して影響の大きさを点数化して優先度を決めた。次にFTAでは、その問題がどのように連鎖して重大イベントへと至るのかを根本原因まで掘り下げ、対策を具体化した。これを繰り返すとリスク全体像が見え、対策の順番も自然と決まってくる。身近な場面での練習や学習計画にも活かせる考え方で、将来の設計にも役立つと感じた。





















