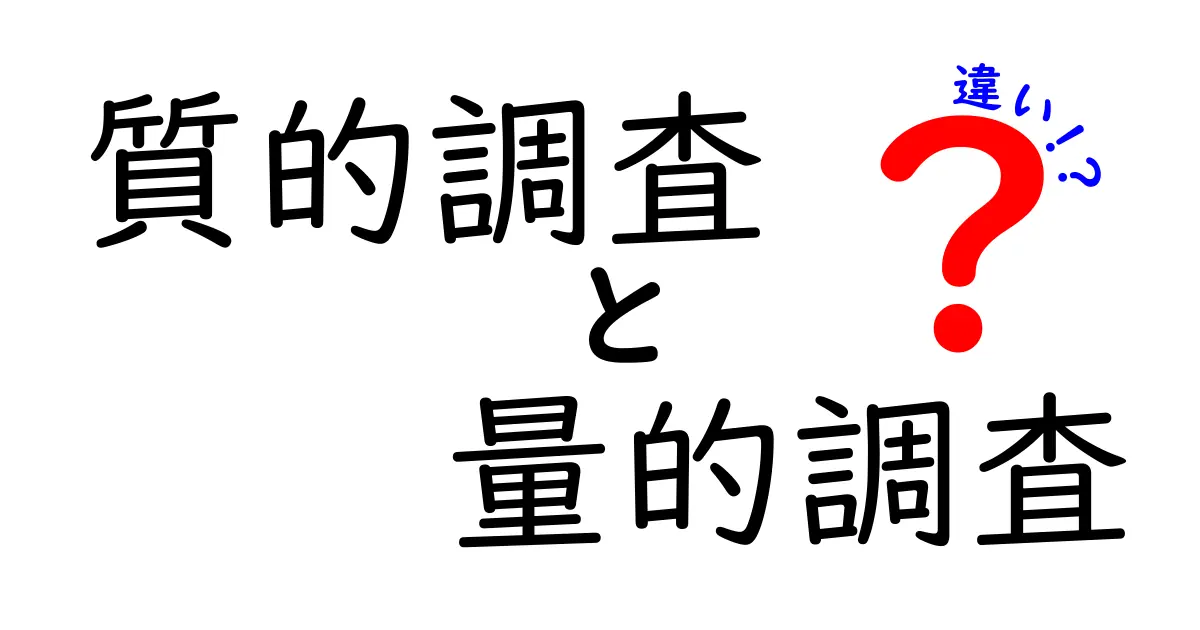

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
質的調査と量的調査の違いを徹底解説|中学生にもわかる見分け方と実務のコツ
現代の研究ではデータの取り方が結果を左右します。質的調査と量的調査はこのデータの取り方の代表的な二つの方法です。質的調査は言葉や意味を丁寧に読み解く作業であり、個人の感じ方や文脈を深く理解することを目指します。一方、量的調査は数字を集めて大勢の傾向を測る方法であり、再現性の高い結論を作ることを狙います。二つの方法は目的によって使い分けるべきで、同じテーマでも得られる答えの性質が大きく異なります。
例えば学校のアンケートをとって全体の満足度を知るとき、量的調査の方が適しています。なぜなら全員の答えを数値化して平均や分布を出せば統計的に判断できるからです。一方で授業の進め方や生徒の感じ方といった「なぜそう感じるのか」を知りたい場合には質的調査が有効です。インタビューや小さなグループ討議を通じて、答えの背後にある理由や経験の意味を詳しく掘り下げることができます。
現場では研究の目的に合わせてデータの性質を決めます。質問の設計とデータの性質を同時に考えることが多く、データの収集と分析の計画を連携させることが重要です。さらに混合手法と呼ばれる方法もあり、同じ研究で質的データと量的データの両方を集めて総合的に解釈します。混合手法は時間とコストが増えることもありますが、より豊かな理解を生む可能性があります。
質的調査の特徴と例
質的調査の特徴はデータの性質が言葉や意味、体験の背景にあることです。個人の感じ方や文脈を深く読み解く作業であり、対象は通常数名から数十名程度です。データの収集方法にはインタビューやフォーカスグループ、日記記録などがあり、答えの背景にある意図や価値観を読み解く技術が求められます。分析は語られた内容をテーマごとに分類し、物語のような説明として整理します。
長所としては新しい視点を発見し、前提や背景を明らかにする力が強い点が挙げられます。一方の短所は時間がかかり、対象者の発言に依存しやすい点です。研究者の解釈が影響しやすいため、透明性を保つ工夫が必要です。
例としては学校の授業についての意見を深掘りする場合などが挙げられ、質問の導入や話の流れを工夫して進めると、現場の本音が見えてきます。
量的調査の特徴と例
量的調査の特徴はデータが数値として表現され、全体像を統計的に把握できる点です。データは大勢の人から集められ、平均値や割合、分布などの指標を使って特徴を説明します。対象は時として千人規模以上にもなり、質問紙や実験設計で再現性を高めます。分析は集計と統計手法を使い、傾向や因果関係を検証します。
強みは再現性と信頼性が高く、結果を他の研究や現場の意思決定に使いやすい点です。反面は言葉のニュアンスや背景の意味まで読み取るのが難しく、質問の設計次第で偏りが生まれやすい点です。代表的な例として全国規模の意識調査や商品の満足度調査があります。
使い分けの実務と表のまとめを見てみましょう。現場では目的と制約を見比べ、混合手法を検討します。
使い分けの実務と表
研究の目的を明確にしたうえで、どのデータが必要かを決めます。次に収集手段を設計し、分析方法を選ぶのが基本です。混合手法を選ぶ場合は同時にデータの整形と統合の計画を立て、時間と費用を見積もることが大切です。
質的調査の現場を想像すると友だちとカフェで長い話をしている場面が思い浮かびます。インタビューで語られる一言一言には、話者の価値観や生活の背景が隠れていて、聞く側はその意味を丁寧に開いていく作業をします。私は小さな質問から始め、話が進むにつれて新しい疑問が生まれるのが好きです。そんな過程で見える“本当の理由”に気づくと、調査の答えは数字よりも深く豊かな意味を持つことがわかります。
次の記事: エティックとエミックの違いを徹底解説!中学生にも分かる実例つき »





















