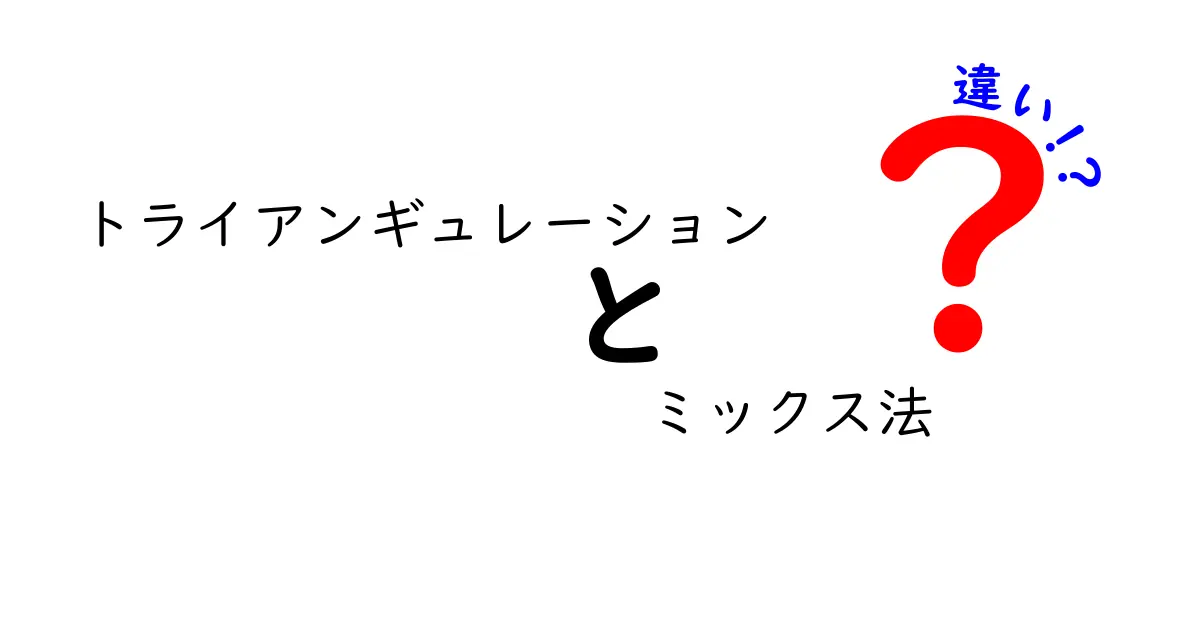

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
トライアンギュレーションとミックス法の違いをわかりやすく学ぶ
この投稿では、研究の世界でよく出てくる二つの考え方「トライアンギュレーション( Triangulation )」と「ミックス法(混合研究法)」の違いを、中学生にも理解できるようにやさしく説明します。まず覚えるべきは、トライアンギュレーションは結果を検証するための戦略であり、ミックス法はデータの種類を組み合わせて研究全体を設計する方法だという点です。これらは別々の概念ですが、うまく組み合わせると信頼性と深さの両方を高める力を持っています。本文では、それぞれの定義、使い方が向いている場面、実際の進め方のコツを、日常の身近な例を交えつつ丁寧に比べていきます。
特に重要なのは、どのデータを使い、どの手法を選ぶかを事前にきちんと決めることです。そうすることで、後からデータを足したり分析を変えたりする時にも混乱を避けられます。以下のセクションでは、三つの視点から違いを詳しく見ていきます。
また、表や例を使って視覚的にも理解しやすく作っていますので、読み進めるうちに「自分の研究計画にどう活かすか」が自然と見えてくるはずです。
放課後の部活で、僕と友達は混合研究法について雑談していました。僕は数字が好きだから最初は定量データの力だけで解を追いかけたかったんだけど、友達がちょっと待てと提案。『人の言葉や感じたことを無視していいの?』と尋ねられて、二人で近所の公園で観察ノートとインタビューのメモを引っ張り出しました。そこで気づいたのは、定量と定性を両方使うと、数字の背後にある理由まで見えるということ。僕らは、統計の結果だけを信じるのではなく、現場の声を取り入れることで「なぜそういう結果になったのか」を説明できるようになりました。結局、研究は答えを出すだけでなく、なぜそうなるのかを伝える力も大事だと感じました。ミックス法は難しそうに見えるけれど、設計を丁寧にすれば、数字と物語を同時に育てられるんだと実感しています。





















