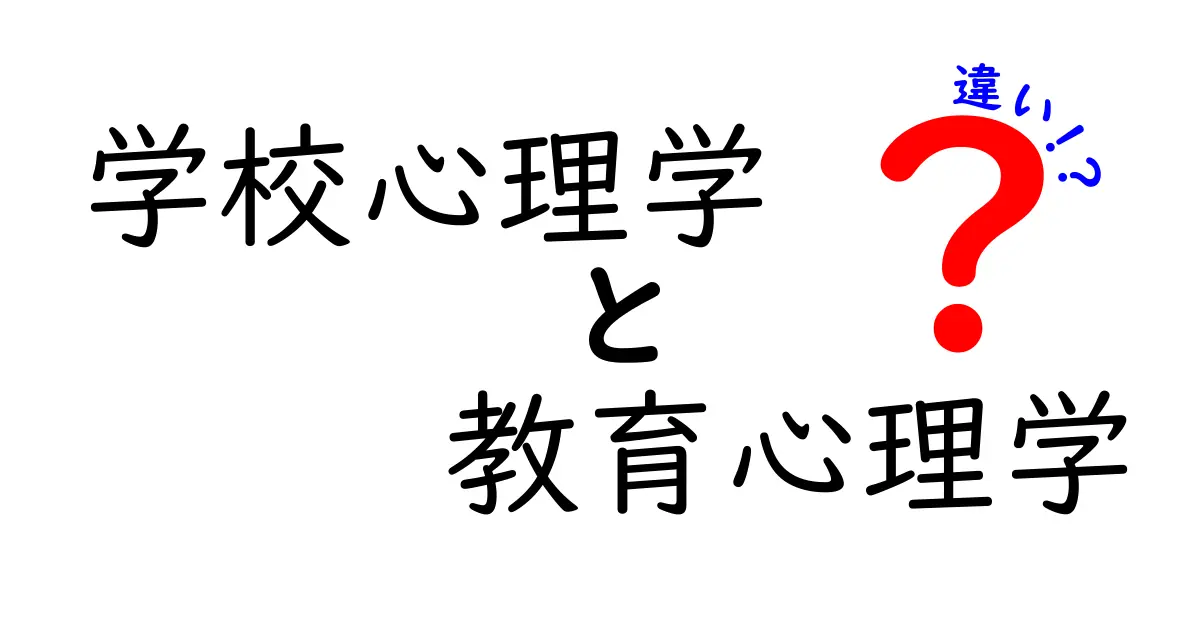

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:学校心理学と教育心理学の違いを正しく理解する
学校心理学と教育心理学は、学校の現場で子どもの心や学びを支える専門分野です。見かけは似ているようですが、目的や実践の場、使う方法には違いがあります。本記事では、中学生にも理解できるよう、専門用語をできるだけ避け、身近な例を用いて説明します。まず前提として大切なのは、学校心理学が「学校という場の力を最大化するための科学的支援」、教育心理学が「学習そのものを改善するための心理学的理論と技法」という二つの視点を持っていることです。
つまり、学校全体の安心できる雰囲気と、個々の子どもの学習の良さを同時に育てるのが両分野の役割です。ここから先は、実際の違いを具体的な場面で見ていきます。
読み手の立場を想像すると、友達との関わりや授業の受け方、先生との相談の仕方など、日常の中で感じる「心と学びのつながり」が理解の手掛かりになります。
具体的な違いを分かりやすく整理する
まず考え方の違いを整理します。学校心理学は子どもの心の動きと学校環境のつながりを総合的に見る視点です。例えば、登校拒否の背景には家庭の事情だけでなく、クラスの人間関係、授業の進み具合、環境の変化などが絡んでいます。学校心理士は観察や面接、アンケート、心理テストなどを通して全体像をつかみ、教師や保護者と協力して解決策を組み立てます。教育心理学は、授業設計、学習意欲、理解の仕方、記憶の仕組みなど「学習の仕方」を科学的に理解して、教師が授業をどう作るべきか、子どもがどう学ぶのが最も良いのかを探ります。
実際の場面での違いを考えると、学校心理学は「学校全体の環境と子どもの心の状態」をマクロに見るのに対して、教育心理学は「個々の学習過程や教材の作り方」というミクロな視点が中心になります。これらは別々の分野のようですが、現場では互いに補完し合います。例えば、いじめの対応を考えると、学校心理学は全体の雰囲気作りや相談体制の整備を担当し、教育心理学は授業の中身や学習活動の工夫を提案します。
学習の理論には共通点も多く、記憶、注意、モチベーション、自己効力感などの心理的要因がかかわります。ただし評価の目的が異なります。学校心理学の評価は子どもの適応と健全な学校生活の確保、教育心理学の評価は学習成果の理解や授業改善のためのデータ収集です。中学生としては、授業の受け方と生活の困りごとが、学習の結果にどう影響するかを知ることが大切です。
中学生として身近に感じやすいポイントは、授業での理解の仕方と生活の困りごと、どちらがどう影響するかという視点です。授業の工夫は教育心理学のテーマであり、友だち関係や心の健康の支援は学校心理学のテーマになります。これらを混同せず、役割分担を理解することが、学校をもっと居心地の良い場所にする第一歩です。
違いの要点を表でまとめる
この先は表形式で、観点別に要点を整理します。表を読むだけで、学校心理学と教育心理学の役割の違いが頭に入りやすくなります。読み手が自分の学校で何を相談すべきか、どの先生がどんな支援をしてくれるのかを想像しやすくなるよう、要点をコンパクトに整理します。
友だちとの会話でよく出てくる自己効力感という言葉、実は身近な大事な心の力を表しています。自己効力感とは“自分には困難を乗り越える力がある”と感じる気持ちのこと。学校現場では、小さな成功体験を積ませたり、先生と信頼関係を築く話し方を工夫したりすることで、高めることができます。自己効力感が高い子は新しい課題にも挑戦しやすく、失敗を学びの機会と捉えやすくなります。だからこそ、学習の場だけでなく生活の場でも大きな役割を果たしているのです。





















