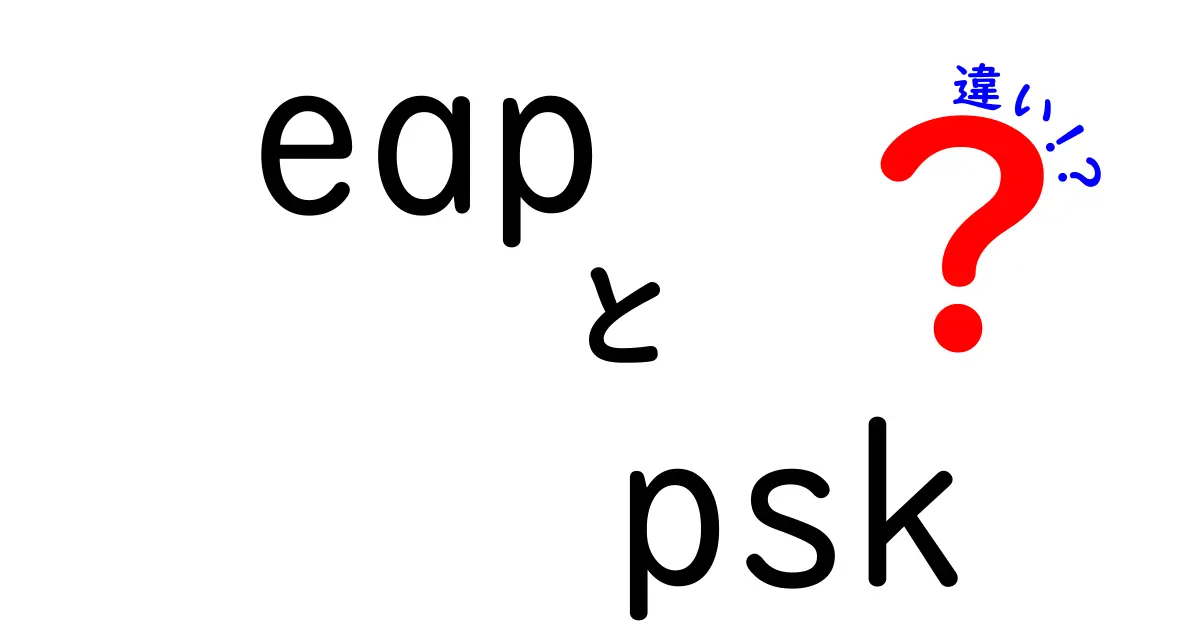

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
eapとpskの違いを徹底解説:中学生にもわかる安全なネットワーク認証の基本
ネットワークに接続する時には、いくつかの認証の仕組みが使われます。中でも「eap」と「psk」はよく聞く名前ですが、意味や使い方が違います。ここでは、難しい専門用語をできるだけ避けつつ、「eapは認証の枠組みであり、pskは事前共有鍵という具体的な鍵の仕組み」という基本を丁寧に解説します。まず最初に覚えておきたいのは、eapは認証の窓口のような役割を果たし、pskはその窓口を開けるための鍵そのものだということです。具体的には、家庭のWi-Fiなどでよく使われるのが
本記事を読み進めると、次のようなポイントが見えてきます。1つ目は「EAPは認証の枠組みであり、複数の具体的な認証方法を含む」こと、2つ目は「PSKは鍵そのものを指し、覚えやすさと同時に弱点にもなり得る」こと、3つ目は「実務では用途に応じて選ぶべき」という現実的な判断基準です。これらを押さえると、家庭のネットワークの安心感を高めつつ、学校や職場でのセキュリティを理解しやすくなります。
この章を読んで、難しく聞こえる言葉が日常の実務につながる具体的な知識へと変わる手助けになれば嬉しいです。最後に、用語の整理として“eapはプロトコルの柔軟性を持つ認証の枠組み”、“pskは鍵の形で配布される認証情報”というイメージを頭に置いておくと迷いにくくなります。
さあ、次のセクションでは、もう少し具体的な意味を掘り下げていきましょう。
eapとは何か?基礎の基礎
EAPとは Extensible Authentication Protocol の略で、日本語では「拡張認証プロトコル」と呼ばれる認証の枠組みです。ここが紐づくのは802.1Xといわれるネットワークの入口の部分です。EAPは個々の認証方法を差し替えられる“枠組み”であり、固有の鍵の種類を決めるものではありません。この特徴が、企業の無線LANで使われる場面の多さにつながっています。たとえばEAP-TLS、EAP-PEAP、EAP-FASTといったさまざまな方式があり、どれを選ぶかは環境に応じて異なります。論点は大きく分けて3つです。第一に「誰が認証されるべきか」という点、第二に「どのように認証情報を安全にやり取りするか」という点、第三に「認証サーバーをどの程度設置・運用するのか」です。
EAPの大事な考え方は、「認証情報を外部のサーバーと安全にやり取りする仕組みを整えること」であり、鍵そのものを配布するpskとは別の層で動きます。結果として、組織の規模が大きくなるほどEAPの恩恵を受けやすく、設定の柔軟性とセキュリティの強化を両立できる場面が増えます。この柔軟性は、現代の企業ネットワークで重要な要素のひとつです。
なお、EAPの中には証明書(デジタル証明書)を使うものもあり、これを適切に管理するためにはIT部門の体制と教育が欠かせません。これが導入難易度やコストの目安になることも覚えておくと良いでしょう。
つまり、eapは「鍵をどう配るか」ではなく「認証をどう成り立たせるか」という考え方を決める枠組みなのです。これを理解しておくと、後のpskとの違いが頭に入ってきます。
pskとは何か?どう使われるか
PSKは Pre-Shared Key の略で、日本語では「事前共有鍵」と呼ばれる、ネットワークに入るための合い言葉のことです。家庭のWi-Fiでよく使われるWPA-PSKは、1つの鍵(パスワード)を事前に全員で共有して使用します。この仕組みの良い点は、導入がとても簡単で、専門的なサーバーを用意する必要がない点です。導入の難易度が低く、すぐに使える反面、パスワードが漏れるとネットワーク全体が危険にさらされます。特に“誰が接続していいか”を個別に判定する仕組みがないため、同じ鍵を複数の人が使い回すことになります。これがセキュリティ上の大きな弱点になる場合があります。
違いのまとめと実務での判断
結論として、EAPは認証の枠組みであり、多様な認証方法を組み合わせて安全性を高める設計、PSKは鍵そのものを使う最もシンプルな形、という点が基本的な違いです。日常的な家庭のネットワークではPSKで十分な場面が多いですが、企業や学校などの大規模環境では、厳格なアクセス管理が必要なためEAPを前提にした802.1Xの導入が推奨されることが多いです。実務での選択には、次のようなポイントが関係します。まず第一に、誰がネットワークを使うのか(従業員・学生・来訪者など)を把握すること。第二に、鍵をどのように配布・更新するか(自動化できるか、手作業にならないか)。第三に、運用コストとセキュリティのバランスをどう取るかです。
PSKは手軽さが魅力ですが、パスワードの強度と管理方法をしっかり決めておく必要があります。EAPは設定が複雑になる一方で、鍵の配布方法や認証の実行方法を個別に制御できるため、規模が大きい環境でのリスクを抑えやすいというメリットがあります。ここを理解しておくと、具体的な導入時の議論で「どちらを使うべきか」の判断がずっと楽になります。
表で見る違い
以下の表は、eapとpskの主な違いを要点だけ整理したものです。実務での選択時に、ざっくりとした比較を頭に入れておくと判断が早くなります。
まとめと今後のポイント
今後ネットワークを設計・運用する際には、まず要件として「誰がアクセスするのか」「アクセスをどう認証・管理するのか」「運用コストとセキュリティのバランス」を整理しましょう。小規模であればPSKで十分な場合が多いですが、従業員や学生など複数の人が使う環境ではEAPを前提とした802.1Xの設計を検討すると安心です。さらに、教育現場や企業では、証明書の管理方法やユーザーの権限設定など、運用面の準備が鍵となります。これらを踏まえて適切な選択をすれば、セキュリティと利便性の両方を高いレベルで両立することが可能です。
今日はeapとpskの違いについて、まるで友だちと雑談するような雰囲気で話してみました。PSKは家庭用Wi-Fiの合言葉みたいなもの。みんなで同じ鍵を使うから手軽だけど、鍵が漏れるとみんなが危険な点がデメリット。対してEAPは“窓口”のような認証の仕組みで、複数の方法を組み合わせて使えるのが魅力。企業や学校の大規模ネットワークでは、鍵を配る人を限定したり、鍵を自動で更新したりすることが可能になるので、セキュリティがぐーんと高くなります。要は、覚えやすさと安全性のバランスをどう取るか、場面ごとに選び分けるのが大切という話でした。





















