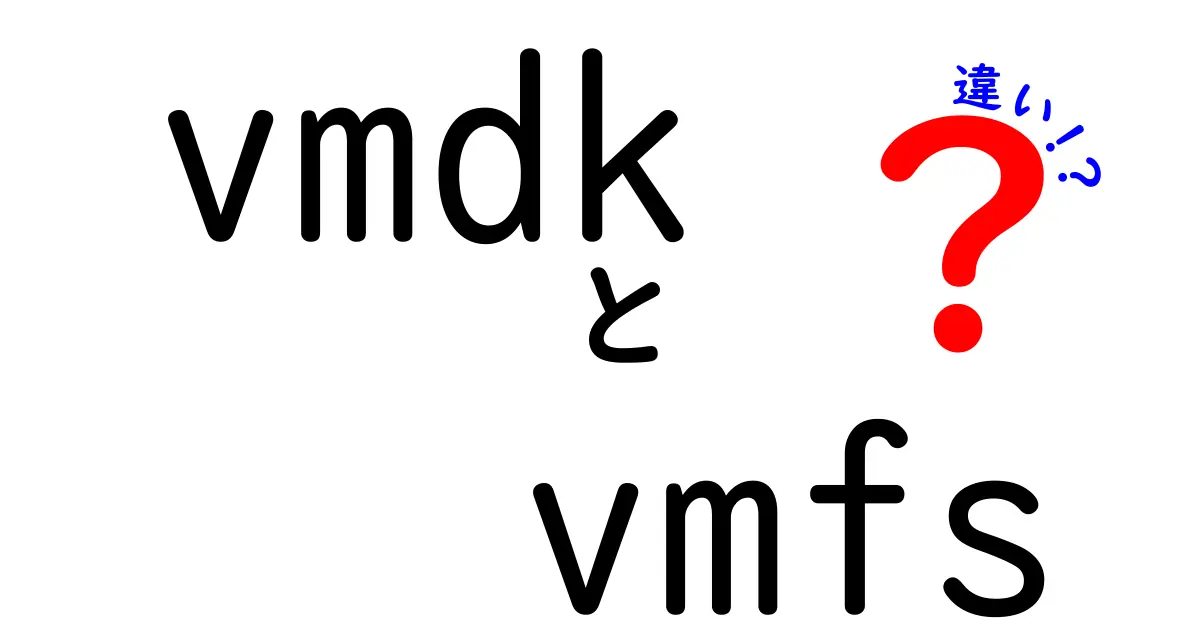

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに vmdkとvmfsの違いを知ろう
仮想化環境では日々多くの用語が登場しますが vmdk と vmfs は特に混乱しがちな組み合わせです。まず前提として覚えておきたいのは vmdkは仮想マシンのディスクを表すファイル形式であり、vmfsはデータストアと呼ばれる領域を作るためのファイルシステムだという点です。つまり vmdk は個々の仮想ディスクの実体を格納する箱のようなもの、 vmfs はその箱を置いて整然と管理するための地面や床材のような役割を果たします。これを理解すると仮想マシンの作成やバックアップ、リストアのときに何が実際に動いているのかが見えやすくなります。
仮想化の現場ではこの二つを混同してしまうと設定やトラブルシューティングが難しくなることがあるので、まずはそれぞれの役割を分けて考えることが重要です。
本記事では初心者でもわかる言葉で vmdkとvmfsの違い を順番に解説します。まずは基本の違いを整理し、次に 具体的な使い分け やトラブルになりやすいポイント、そして実務での確認手順を紹介します。最後には表にまとめた要点と、日常の運用で役立つヒントを載せます。読み進めるほど、仮想ストレージの“しくみ”が自然に見えてくるはずです。
この章では専門用語を極力避き、会話調で進めていますので、初めて学ぶ人でも安心して読み進めてください。
vmdkとvmfsの基本的な違いを理解する
vmdkは仮想ディスクの実体を格納するファイルです。仮想マシンが必要とするディスク容量を仮想的に作り出し、それを1つのファイルとしてホスト上のストレージに保存します。複数のディスクが必要な仮想マシンであっても、それぞれが 独立した vmdk ファイル として扱われます。逆に言うと vmdk 自体は「何かを動かすための箱」であり、データの書き込み順序や整合性の管理は VMware のソフトウェアが担います。
一方で vmfsはファイルシステムの役割です。vmfs はデータストアと呼ばれる領域を作り、その領域に vmdk を含む複数のファイルを格納します。vmfs は複数の ESXi ホストが同時にデータへアクセスして整合性を保つための規則を持ち、並行アクセス時の競合回避、データの整合性、メタデータの管理などを担当します。つまり vmdk が仮想ディスクの中身を直接担い、vmfs はそのディスクを収容する「大きな倉庫の床」として働くのです。
この違いをはっきりさせておくと、仮想マシンの移動やバックアップの際に何を移動すべきか、どのデータをバックアップ対象にするべきかが見えやすくなります。
ここで覚えておくとよいポイントを三つ挙げます。第一に vmdkは個別の仮想ディスクを表すファイルであり、仮想マシンの個々の要素として独立して扱われるという点です。第二に vmfsはデータストア全体を管理するファイルシステムであり、複数のディスクや仮想マシンが同じ vmfs 上で共有されることを意味します。第三に バックアップ戦略はこの二つの役割を分けて考えることが大切で、ディスクリストアとデータストアの運用を混同すると復旧時の拡張性が失われやすくなります。
以下の表でもこの違いを視覚的に整理しておきましょう。
構造と用途の違いを詳しく見る
仮想化環境での実運用を考えると vmdkは個々のディスクの“箱”として機能しますが、vmfsはその箱を置く“倉庫”としての役割を果たします。データの保存先としての vmfs は、複数の ESXi ホストが同時にアクセスすることが可能で、アクセスの競合を避けるためのロック機構や、ディスクの断片化を最小限に抑えるためのデータ配置戦略を持ちます。結果として、同じデータセンター内の別のホストが同じストアへアクセスしても、データの整合性とパフォーマンスが保たれるのです。
ここで注意したいのは vmfs のバージョンや設定次第でディスクの冗長性や性能特性が変わる点です。たとえばストレージの種類が違えば同じ VM の vmdk が存在する場所も変わることがあります。つまり vmfs の管理設定を適切に行うことが、安定した動作とスケーラビリティの確保には不可欠となります。
実務的には以下のようなケースを想定します。新規仮想マシンを作成して vmfs 上にデータストアを作る場合、vmdk はそのデータストア内の1つのファイルとして格納されます。別のホストに移動する場合も、同じ vmfs データストア内であればディスクのデータは失われにくく、移動の手間を最小限に抑えることができます。
日常的な使い分けと注意点
実務での使い分けの基本はシンプルです。vmdkは個別ディスクの運用管理、vmfsはディスクをまとめて格納するデータストアの運用管理と覚えましょう。仮想マシンを複数作成して同じ vmfs データストアを共有する場合、バックアップはデータストア全体を対象とするのが効率的です。個々の vmdk を個別にバックアップすることも可能ですが、整合性の観点からはデータストアの整合性チェックと併用する方が安全です。
また、トラブル時にはまずどちらが原因かを切り分けることが重要です。ストレージの接続障害で vmfs が読み書き不能になると、vmdk 自体には問題がなくても仮想マシンが起動しなくなる場合があります。逆に vmdk ファイルが破損していると、同じデータストア上の他の仮想マシンにも影響が及ぶことがあります。日常のチェックリストとしては、データストアの容量不足の有無、vmfs のロック状態、vmdk のファイル整合性、バックアップの成功履歴を定期的に確認することです。
最後に実務のヒントを一つ。新規ストレージを追加するときは、vmfs のフォーマットとマウント設定を事前に計画し、vmdk のディスク構成を仮想マシンの負荷と用途に合わせて適切に設計してください。これにより仮想マシンのパフォーマンスを最大化し、運用保守の手間を減らすことができます。
まとめと運用のヒント
ここまでをまとめると vmdkは仮想ディスクの実体を格納するファイル、vmfsはそのディスクを格納・管理するデータストア用のファイルシステムという2つの基本的な役割が明確になります。実務ではこの2つの関係を意識するだけで、仮想化環境の設計や障害対応が格段にしやすくなります。
表形式の要点を再掲しますので、運用手順の際に参照してください。さらに、大きなストレージを導入する前には vmfs の設定項目と vmdk の作成方針を事前にチームで共有しておくとトラブルを防ぐことができます。
この知識を日常の IT 作業に落とし込むことが、安定した仮想化基盤を維持する第一歩です。
ある日学校のIT室で友達が vmdk と vmfs の区別を混同していた。私は先生に教わった体験を思い出しつつ、二つの役割をこんな風に説明した。vmdk は仮想マシンの中身を入れる箱であり、vmfs はその箱を置く倉庫のような場所だと。要するに ディスクとストレージの違いを“箱と倉庫”で覚えると混乱がぐっと減る。話しながら一緒に表を見て理解を深め、授業後には友達も自分の仮想環境での使い分けを自信を持って語れるようになった。





















