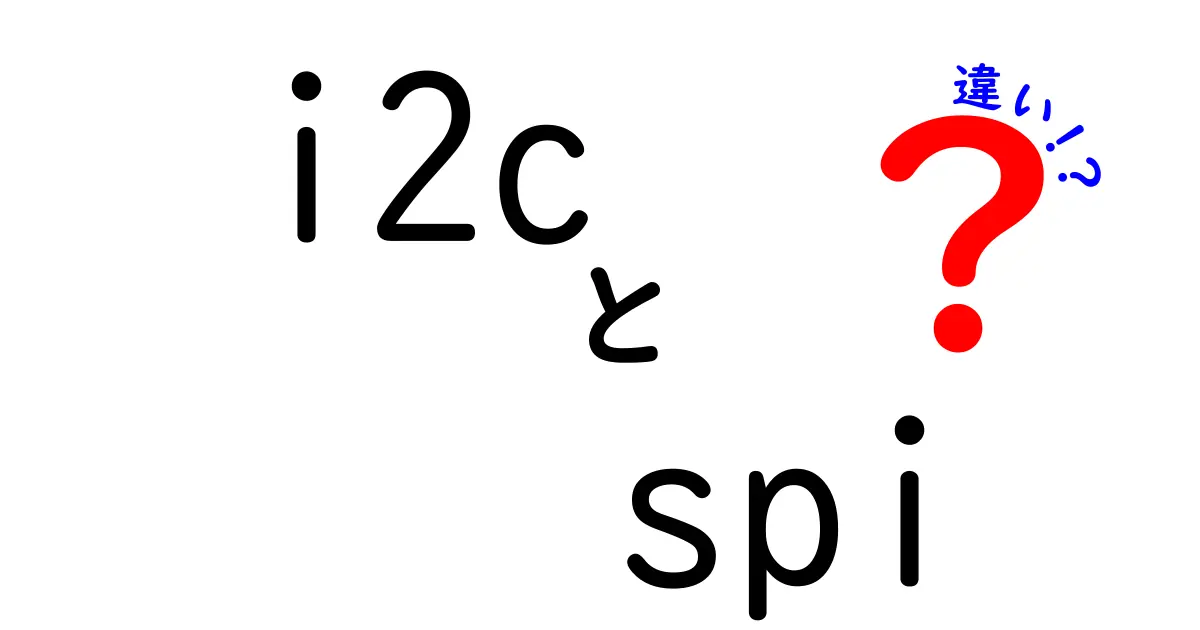

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
概要と前提知識
このセクションでは、まず違いを理解するための基礎を固めます。
i2cとSPIはどちらもマイコンと周辺デバイスをつなぐ通信方式ですが、接続方法の形、速度の特性、実装の複雑さ、そして用途の適性が大きく異なります。
i2cは「多くのデバイスを1つのバスに接続できる」ことが魅力で、配線が少なくて済む反面、速度やクリアランスには制約があります。
一方、SPIは「速く安定して動作させやすい」反面、配線の本数が増えやすいという特徴があります。
この記事では、中学生にもわかる言葉で、それぞれの仕組み・実務での使い分け・よくある誤解を丁寧に解説します。
最後には、実務で役立つ判断基準と、初期設定のチェックリストもご紹介します。
I2Cの特徴と使われ方
I2C(Inter-Integrated Circuit)は、2本の信号線で複数のデバイスを接続できるマルチマスタ/マルチスレーブ対応のバスです。
線はデータ線SDAとクロック線SCLの2本だけ。
デバイス同士はアドレスを用いて通信を行い、同じバス上のデバイス同士で衝突を避ける工夫が必要です。
この設計のおかげで、配線が少なく済み、部品点数が増えても配線の管理が楽というメリットがあります。
ただし、通信は「バイト単位の連続転送」や「ACK・NACKの手続きを含む」など、少し堅めの手順があり、最大通信速度は一般的に100kHz~400kHz程度、近年は「超高速モード(FM/SM)」の実装もありますが、長距離には向きません。
周囲にノイズが多い環境では、信号の安定性を確保するために適切な抵抗や終端、プルアップ抵抗の値設定が重要です。
I2Cは低速なセンサ群や小規模な組み込みシステム、配線を最小化したい場面に最適です。
また、多デバイスを1つのバスに接続する設計は、拡張性を高めたい場合にも利点になります。
I2Cの特徴と使われ方
I2Cの最も大きな魅力は、ドラフト的な拡張性と配線の少なさにあります。
複数のセンサやデバイスを同じ2本のバスに接続できるため、教材用の教育ボードや小型のプロトタイプ、プロジェクトの初期段階でよく採用されます。
ただし、高速性が必要な場面には不向きです。センサのデータ取得が定期的に発生する場合でも、バス上で他のデバイスとアドレス衝突を避けるための工夫が必要です。
設計上のポイントとしては、プルアップ抵抗の選定、バス長の制限、デバイス数の上限を把握すること、そして起動時のアドレス割り当てとデバイス初期化の順序を決めておくことが挙げられます。
実務では、温度センサ・光センサ・ボタンなどの低速デバイスを複数接続する場合に適しています。
また、モジュール間でのデータ整合性を保つためには、通信のタイミングとデータ形式の規則を事前に決めておくことが重要です。
SPIの特徴と使われ方
SPI(Serial Peripheral Interface)は、データ転送の速度と柔軟性が高い通信方式です。
基本的には1つのマスター(マイコン)と複数のスレーブの構成ですが、複数のスレーブを個別のチップセレクト線で選択する方式が一般的です。
信号線はSCK(クロック)、MOSI(マスター→スレーブ)、MISO(スレーブ→マスター)、そしてチップセレクト(CS/SS)線が必要です。
この構成のおかげで、速度は非常に高く設定可能で、一般的には数MHz以上の転送が可能です。
また、データ転送の順序が単純で、同期転送が基本なので、プログラマブルな高速動作を実現しやすい点も魅力です。
ただし、スレーブごとにCS線が必要なため、接続するスレーブの数が増えると物理配線が増えるデメリットがあります。
SPIは、高速なセンサ群やディスプレイ、EVBの周辺機器など、データ量が多く安定性が求められる場面に向いています。
設計上のポイントは、適切なクロック分周、CS信号のタイミング、データのビットオーダー(MSB/LSB)、およびデバイス間のデータ整合性の取り方です。
適切に設計すれば、I2Cよりもはるかに高速な通信が実現します。
速度と配線の現実的な比較
ここでは、実務でよく直面する「速度と配線のトレードオフ」を整理します。
まず速度面では、SPIは理論上の最大速度が高いため、大量のデータを連続して送る場合に有利です。
I2Cはデバイス数が増えるほど、アドレス解決やACK/NACK処理のオーバーヘッドが増え、相対的に遅く感じることがあります。
ただし、I2Cは実装がシンプルで、距離が短く、ノイズが少ない環境では十分な性能を発揮します。
配線面を比べると、I2CはSDAとSCLの2本だけなので、ボード上の配線がスッキリします。対してSPIはCS線を含めるとデバイス数に応じて配線が増え、設計時の配線計画が重要になります。
実務上の選択ポイントとしては、転送データ量とデバイス数のバランス、ノイズ環境と距離、実装の複雑さと保守性などを総合的に判断します。
結論として、高速な連携が必要でデバイスが少ない場合はSPI、接続デバイスが多く配線負荷を抑えたい場合はi2cを検討するのが一般的です。
実務での使い分けと落とし穴
実務ではプロジェクトの要件に合わせて適切な選択をします。
まずは、データ量、動作周波数、デバイス数、配線の長さを整理しましょう。
まとめると、I2Cは「拡張性と簡易設計」を重視する場合に最適、SPIは「高速性と安定性」を重視する場合に向いています。
ここでよくある落とし穴を挙げます。
1) プルアップ抵抗の設定を誤ると通信が不安定になる。
2) SPIで複数スレーブを使う場合、CS信号の配線漏れやデバウンス対策が甘いと通信が混線する。
3) バス長が長いとI2Cは特に信号反射やノイズの影響を受けやすい。
4) クロック極性・位相(CPOL/CPHA)の設定の不一致はデータ破損の大きな原因になる。
これらを避けるには、初期設計時にデバイスのデータシートをよく読み、具体的な電気仕様とタイミング要求をプロジェクト内で共通に管理することが大切です。
最後に、実務での設計チェックリストを紹介します。
・デバイス数と配線計画を確定しておく
・クロック周波数とデータレートを現実的な値で設定する
・長さと配線のノイズ対策を想定する
・エラーハンドリングと再試行の仕様を決める
・デバッグ用のモニタリング手段を用意する
まとめと今後のポイント
この記事を通して、i2cとSPIの違いと、使い分ける際の判断基準が見えたはずです。
要件を明確にしてから設計を始めることが、後のトラブルを防ぐ最善策です。
新しいプロジェクトでは、まずデータ量・デバイス数・距離・ノイズ環境を整理し、現実的な周波数と配線計画を練ってください。
最終的には、必要な性能と保守性のバランスを取り、最適な通信方式を選択することが成功への近道になります。
友人とカフェで雑談しているときのこと。SPIの話題になって『速さは正義だよね』なんて言いがちだけど、実は現場には“速さだけでは解決できない”局面があるんだ。SPIは確かにデータをガンガン送れるけれど、スレーブごとにCS線が必要で配線が増える。i2cはその反対で、配線は少なく済むがデバイス数が増えると衝突回避やアドレス管理の工夫が必要になる。結局、大人たちは「この場面にはこの路線」と、状況に応じた正解を選ぶ。そう考えると、どちらを使うかは“速度と拡張性のバランス”のゲームなのかもしれない。





















