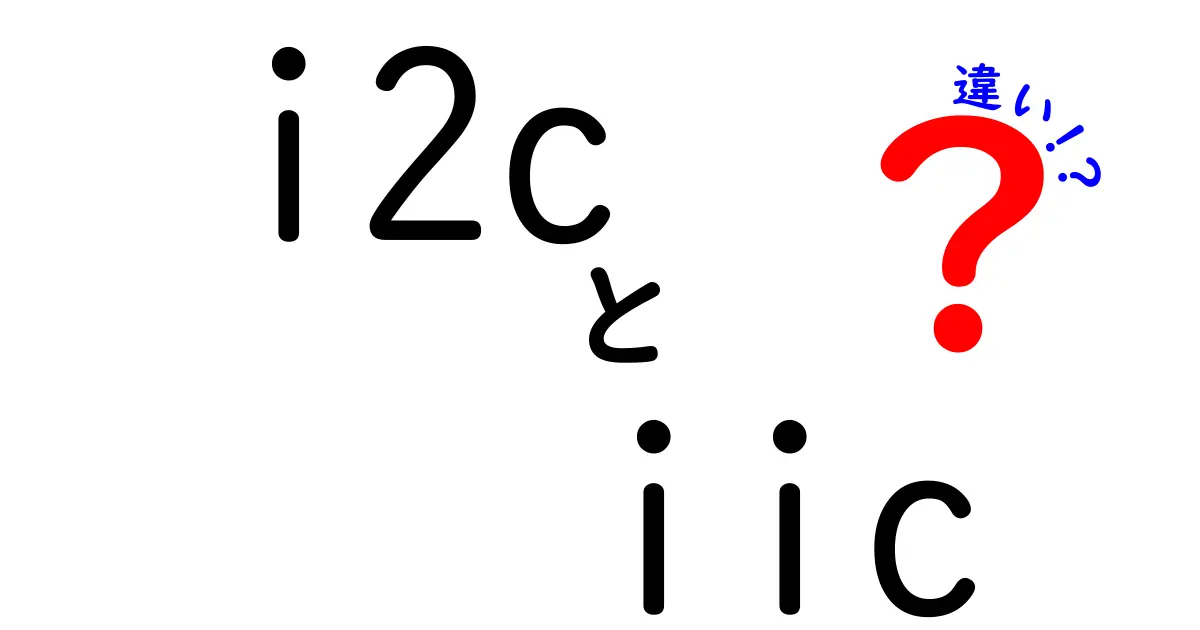

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに: i2cとiicの基本を知る
i2cとiicは、日常の電子工作やマイコン学習でよく出てくる2つの用語です。結論から言うと、実務的には同じ“I2Cバス”を指すことが多く、差はほとんどありません。ただし名称の使われ方には歴史的背景や混乱の原因があり、それを押さえると資料を読んだりデバイスを選ぶときに混乱が減ります。I2Cは1980年代にPhilips(現NXP)によって提案されたInter-Integrated Circuitの略称で、2線式の通信方式です。SDAとSCLの2本の線を使い、複数のデバイスを同じバス上につなぐことができます。データのやり取りにはアドレスが使われ、主役はデバイス同士の「話す順序」と「競合を避ける仕組み」です。初心者がつまずくポイントは、名称の差よりも「どうやって接続するか」「どうやってデータを送るか」という実務の基本です。ここで重要なのは、2つの用語が混ざると混乱しがちだという事実を認識すること。説明書やチュートリアルの中には、I2CとIICを別の機構として扱う記述もありますが、一般的には同じバスを指す語として使われることが多いのです。結果として、最初の一歩は「公式名は I2C である」という前提をしっかり押さえ、以後のリファレンス検索を I2C で行う癖をつけるのが安定です。
さらに、I2C という名称が現場の文化や国ごとの教育でどう扱われるかも理解しておくと、将来の勉強や職場の資料の読み替えが楽になります。つまり、用語の揺れを怖がらず、実際の通信の仕組みや動作原理を優先して理解することが、学習のコツです。
歴史と由来
i2cの正式名は I2C で、1980年代の半導体メーカーPhilips(今のNXP)によって提案されました。公式名称は I2C であり、後に国際的に広く使われるようになりました。一方で IIC という呼び方は古い資料や日本国内の解説書で根強く残っており、実務上は同じバスを指す別名として使われることがあります。技術仕様自体はほぼ同じですが、混乱を避けるにはまず公式名で検索・読解を行うのが安全です。
「Inter-Integrated Circuit」という表現そのものは複数のメーカーで解釈が微妙に異なることがあり、用語の揺れはよく起こります。
実務での使い分けとよくある誤解
実務上は I2C と IIC の差はほぼありません。現場の資料やデータシート、開発ボードの説明でも「I2C」と書かれていることが多く、通信用語としてのI2Cは標準、SMBus などの関連規格と混在することがあります。
ポイントは「SDAとSCLの2本の線で複数デバイスを同じバスに接続する」こと、アドレス指定、クロック周波数、そしてクロックストレッチという機構です。コードを書くときには I2C のライブラリ名やデバイス名が地域や学校、企業で微妙に異なることがありますが、動作原理は同じです。
ここで覚えておくと良いのは、公式資料を I2C で調べる、IICという表記は補助的な言い換え程度と認識することです。これだけで、データシートの読み違いは減ります。
表で整理: I2CとIICの基礎
以下の表は、I2CとIICの用語の違いと共通点を簡潔に整理したものです。
本質は同じバス規格を指していること、公式名称は I2C、IICは補足的な別称として使われることが多い点にあります。
このように、用語の揺れはあるものの、基礎となる概念(SDA/SCL、アドレス、クロック、スレーブとマスターの関係)は共通です。特に初心者は、用語の揺れに惑わされず、実際の通信の仕組みや動作を理解することが重要です。
例えばマイコンのデバイスを導入するときは、データシートの「I2C」セクションを探し、実装例のコードを読み解くことから始めましょう。
ある日、電子工作部の机の前で I2C の配線をさわりながら友達と話していた。彼は i2c と iic の違いを真剣に尋ね、まるで難問のように感じていた。私は落ち着いて答えた。I2C は公式な名前で、SDA とSCL の2本の線を使い、マスターとスレーブがアドレスで呼び合いながら通信する仕組みだ。IIC は昔から使われてきた別名で、実務上はほぼ同じ意味として扱われることが多い。つまり「差はほとんどない」という理解で正解だ。そこから私は次のポイントを伝えた。第一に、資料検索は I2C で統一することで情報が集まりやすい。第二に、クロック周波数やアドレス長、クロックストレッチといった細かい仕様はバージョンごとに微妙に異なる場合があるので、データシートを丁寧に読む癖をつけること。最後に、名称の違いにこだわりすぎるより、実際に動くコードと回路の理解を優先すること。話を聞いた友達は「なるほど」と顔をほころばせ、私たちは笑いながらI2Cの世界に一歩近づけた気がした。





















