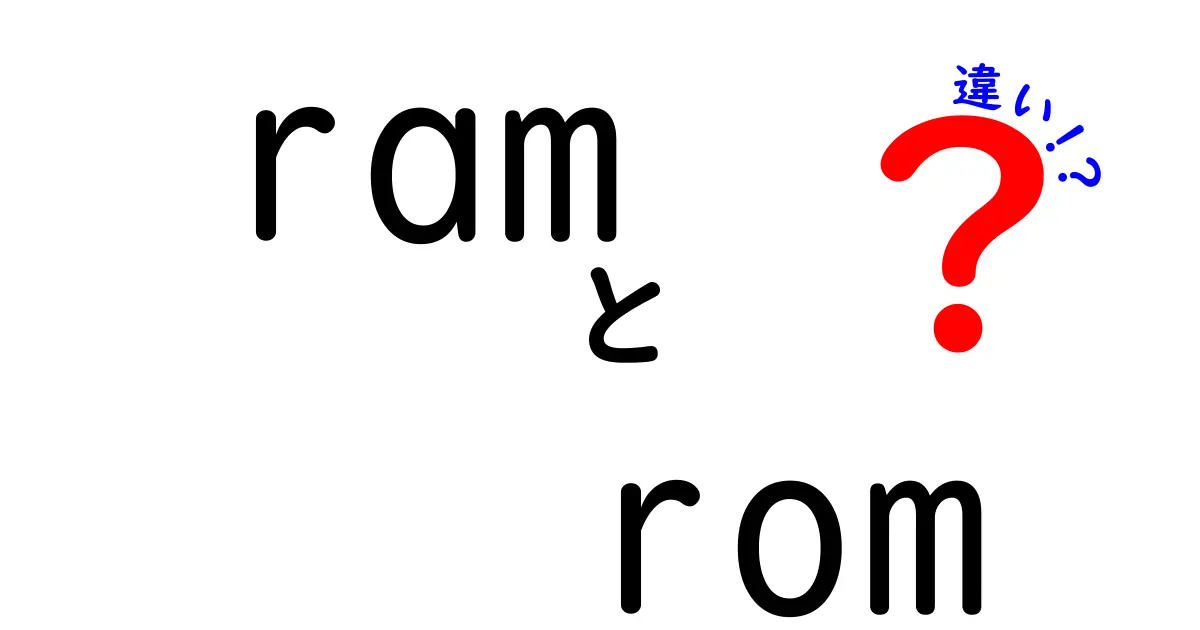

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
RAMとROMの違いを理解するための基本
RAMとROMは私たちの身の回りの機器に入っている「記憶領域」です。
RAMは作業中のデータを一時的に置く場所で、電源を入れている間だけデータを保持します。
この性質を「揮発性」といいます。電源を切ると中のデータは消えてしまい、再び使うときには改めて読み込む必要があります。
一方ROMは読み出し専用の記憶で、電源を切ってもデータが残る性質を持ちます。
OSの起動情報やファームウェア、機器の設定など長期間保存しておくデータをここに入れるのが基本です。
つまりRAMは“今この瞬間の作業”を支える高速の机、ROMは“長く使う設計図”のようなものです。
この差を知ると、なぜコンピュータが速く動くのか、なぜ機器は初期設定を覚えるのかが見えてきます。
RAMとROMの基本的な違いを具体的に見る
RAMはデータを読み書きする速さが重要です。
CPUがデータを必要とするとき、RAMから素早く取り出せると作業がスムーズに進みます。
容量が大きいほど、同時に開くアプリやゲームが増え、作業の快適さが上がります。
RAMは電源を切るとデータが消える「揮発性」なので、保存したい情報は別のストレージに保存します。
ROMは起動時の基本情報やデバイスの設定、ファームウェアなどを保持し、機器を安定して動かす役割を果たします。
このように、RAMとROMは役割が異なるが、協力して機器を機能させています。
さらにRAMにはDRAMやSRAMといった種類があり、速度・容量・コストのバランスで選ばれます。
DRAMは容量を増やしやすい一方で再整備(リフレッシュ)が必要です。
SRAMは速いですが高価で容量も小さめです。
ROMにはマスクROMやフラッシュROMなどがあり、現代の機器ではフラッシュROMがよく使われています。
フラッシュROMは書き換えが可能で、スマホやSSDにも使われる重要な技術です。
RAMとROMを比べる表
RAMとROMの使い分けのポイントとまとめ
生活の中での感覚として、RAMの容量が大きいと作業がスムーズに進みます。例えば動画編集や複数のウェブを同時に開くとき、RAMが多いと待ち時間が減ります。
一方、ROMの安定性は起動の速さと長持ちするデータの保存に直結します。機器を長く使いたい人は、RAMとROMの容量・速度をチェックして選ぶと後悔が少なくなります。
この違いを理解しておけば、買い換えのときにも自分の使い方に合う組み合わせを選びやすくなります。
結局のところ、RAMとROMは相棒のように協力して機器を動かしているのです。
友達とカフェでRAMの話をしていて、RAMは“作業の机の広さ”みたいなものだと結論づけた。たとえばゲームを始めるとき、机の広さが広いほど物を広げられる。これがRAMが多いと動作が滑らかになる理由。ROMは長期保存の棚で、起動時の設定を守る盾の役割だ。私たちは日常的に、この2つを使い分けて快適さを保っている。





















