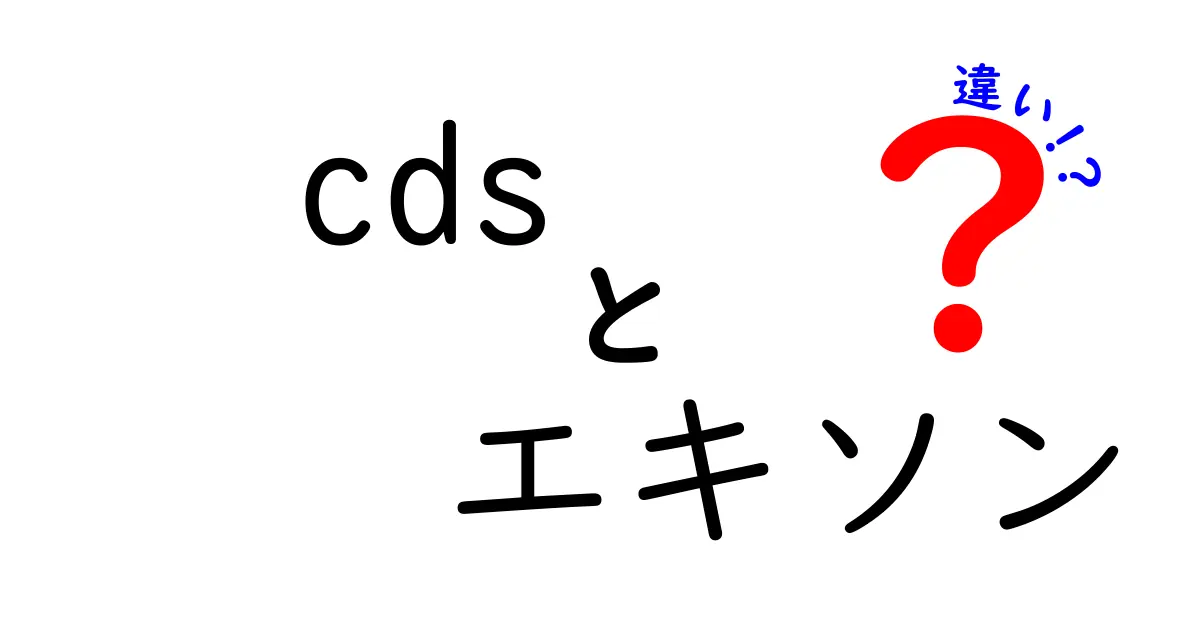

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:CDSとエキソンの違いを理解する
CDSとエキソンは、学校の授業でよく出てくる用語ですが、混乱しがちな組み合わせです。CDSはCoding Sequenceの略で、タンパク質を作る「設計図の中の本当に作られる部分」を指します。エキソンは、転写後に成熟mRNAを作るときに取り出され、つなぎ合わせられるDNAの連続した部分です。これらの言葉は似ていますが意味は大きく異なります。CDSは“翻訳の設計図”のこと、エキソンは「その設計図を乗せる部品」だと覚えると理解が進みます。
エキソンとイントロンの違いを先に理解すると、CDS の位置づけが見えやすくなります。CDSはタンパク質を作る指示を含む部分で、通常はエキソンの一部または複数のエキソンから成り立ちます。イントロンは翻訳には使われませんが、遺伝子の情報を柔軟に使い分ける仕組みの土台となる区切りです。成熟過程でイントロンは取り除かれ、エキソンだけがつながって意味のある情報になります。
この違いを整理するポイントは次のとおりです。
・エキソンは転写後に残る部分で、成熟mRNA の情報を構成する
・CDS はその中でもタンパク質を作るための塩基の並びを指す
・CDS は必ずしも全てのエキソンを含むわけではなく、翻訳の範囲を表す
・UTR(翻訳されない領域)はCDS の外側や一部にまたがることがある
これらを押さえると、せっかくの遺伝子情報がどのようにタンパク質に結びつくのかが見えてきます。
CDSとエキソンの意味と役割を詳しく見る
CDSは "coding sequence" のことで、実際にアミノ酸が並ぶ“翻訳の設計図”を指します。DNA からRNA に転写され、その後リボソームで読み取られてタンパク質が作られます。CDS には開始コドン ATG から始まり、停止コドンで終わる一連のコドン列が含まれ、ここに並ぶ三つ組の塩基が一つのアミノ酸に対応します。
この過程で重要なのは、CDS が翻訳される範囲を決めることです。つまり、どの部分がタンパク質の材料になるかを決める“設計図の実装部分”であり、それ以外の領域はタンパク質には使われません。
一方、エキソンはDNAの中で成熟mRNAを作る元になる連続した配列です。イントロンはその間に挟まっている区切りで、成熟過程で取り除かれます。エキソンの配列がつながることで、CDSを含む場合も、含まない場合もあります。エキソンとイントロンの組み合わせは生物種ごとに異なりますが、基本的な考え方は変わりません。
エキソンとイントロンの関係
エキソンはタンパク質を作る情報の“部品”として働きますが、すべてのエキソンが翻訳に使われるわけではありません。CDS は翻訳に使われる部分を指し、どのエキソンが翻訳の対象になるかは、生物の種や遺伝子の設計によって変わります。イントロンはスプライシングという過程で除去され、エキソンだけがつながって新しいmRNAになります。これにより、同じ遺伝子でも異なる組み合わせのエキソンが使われ、異なるタンパク質が作られることがあります。
また、オルタナティブスプライシングという現象もあり、同じ遺伝子から複数のタンパク質が作られることができるのです。こうした仕組みが、生物の多様性を生み出す鍵になります。
まとめと実例の比較
ここでは簡単なイメージでの比較をします。
エキソンは“遺伝子の部品”で、翻訳の材料となる情報を含むことが多いです。CDSはその部品の中でも、実際にタンパク質を作る指示を含む部分を指します。イントロンは翻訳には使われない区切りであり、スプライシングによってエキソンをつなぎ合わせることで成熟mRNAが完成します。現代の生物学では、オルタナティブスプライシングによって、同じ遺伝子から異なるタンパク質を作ることが多く、これが生物の多様性の源泉となります。
こうした考え方を身につけると、教科書の図だけでは見えなかった“遺伝子の動き”が、日常のニュースや研究の話題の中にも見え隠れしていることに気づくはずです。
ある日、友だちと図書館でエキソンの話をしていました。エキソンは遺伝子の部品で、CDSはその中でもタンパク質を作る設計図の部分だと説明しました。私たちはノートに図を描き、イントロンという“区切り”があるおかげで、同じ遺伝子からいろいろなタンパク質ができることに気づきました。講義の整理が苦手だった僕ですが、紙を一枚ずつ切って貼るように、エキソンとCDSの関係を視覚化してからは、話がぐんと分かりやすくなりました。たとえば、あるエキソン群の中にCDSが跨る場合と跨らない場合がある、という事実を、身近な例のように頭の中で接続することで理解が深まりました。こうした学習のコツは、教科書の語彙を生活の中の“設計図”と“部品”に結びつけることです。





















