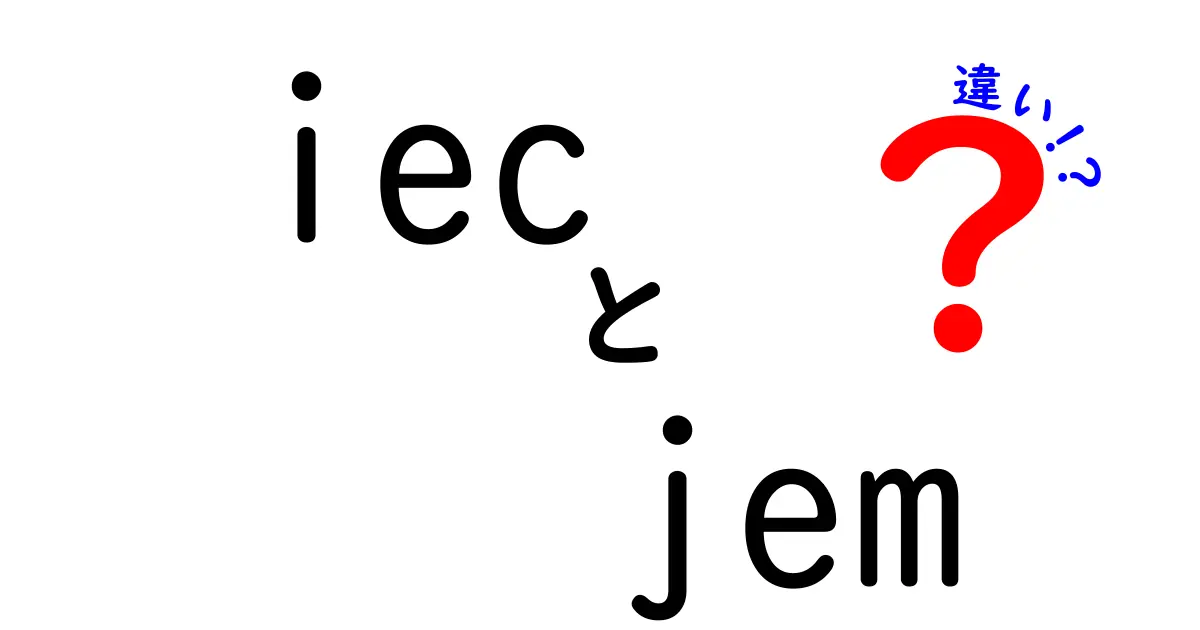

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
IECとJEMの違いとは?まずは全体像からつかもう
世界には多くの規格があり、製品を世界市場で安全に提供するためには「この基準に合っているか」を判断する必要があります。ここでのポイントは「どの規格がどの市場を対象としているか」を理解することです。IECは国際規格の代表格として、複数の国が同じ仕様で動けるように設計された枠組みで、JEMは日本国内市場向けの規格・指針を集約する形で存在します。これらを正しく使い分けることが、海外展開と国内販売の両方をスムーズに進める鍵です。
国際規格と国内規格の理解は、製品開発の初期段階から顧客の信頼を得るためにも重要です。
この章では、両規格の基本的な違いと基本用語を、難しくなく誰でも理解できる言葉で解説します。
IECとは?国際規格の作り方と世界の広がり
IECはInternational Electrotechnical Commissionの頭文字をとった名称で、日本語では「国際電気標準会議」と呼ばれることもあります。
この組織は世界中の技術者が集まり、電気・電子の安全性や性能を高めるための規格を作成します。
規格づくりは、専門家の委員会が設計・試験・評価の基準をじっくり議論することから始まり、ドラフティング(文案作成)→公開コメント→最終審議→承認という流れで進みます。
完成した規格は、加盟国が自国の法規制と照らし合わせて適用したり、輸出入の際の共通言語として使われたりします。
IECの大きな長所は、世界中の企業が同じ基準で設計できる点です。
ただし、国内法規制や地域の認証制度は別途存在するため、現場では「IEC準拠」と「国内認証」の2つを同時に満たす作業が頻繁に発生します。
JEMとは?日本国内の規格体系の中の役割
日本語での説明が必要な場面では、JEMという用語をよく見かけます。JEMはJapan Electrical Manufacturers' Associationの略称で、日本の電機・電子産業を代表する団体です。
JEM自体は国際規格を作る組織ではなく、日本国内市場向けの規格・指針を整理・提示する役割を担います。
例えば国内市場での適合性を示す基準や、安全性の確保に関する指針、製品開発における推奨事項の集合体として機能します。
このため、日本の企業が国内販路を確保する際には、JEMの指針をベースに国内法規やPSEと連携して開発・認証手続きを進めることが多いです。
つまり“国内市場の使いやすさと安全性を確保するための道しるべ”としての価値が高い存在です。
具体的な違いを表で比較
下の表は、IECとJEMの実務的な違いをざっくり比較したものです。表だけを見ても分かるように、対象となる市場、作成の主体、言語、適合の仕組み、更新の頻度などが異なります。
企業がどの市場を狙うかによって、設計の優先順位が変わるため、初期の企画段階で「どの規格を最優先に満たすべきか」を決めておくことが重要です。
この表を使って、海外展開と国内展開の優先順位を整理してみましょう。
日常の現場での使い分けと注意点
日常の仕事の中で、IECとJEMをどう使い分けるかが実務の鍵になります。海外へ製品を出す場合は、IECを核として設計を進めつつ、各輸出先の法規制に合わせた認証を追加します。国内市場を狙う場合は、JEMの指針を土台にして、日本の法規制(例えばPSEなど)へ適合させる作業が重要です。
また、技術者だけでなく企画や営業の人も「どの標準を満たしているか」を意識することが大切です。
要点は、最初の設計プロセスで適用する規格を決め、その後の開発・検証・認証の流れを統一することです。
この考え方を持つと、製品の安全性と信頼性を高めつつ、時間とコストの無駄を減らせます。
結論として、IECとJEMは互いを補完する関係にあり、両方を正しく使い分けることがグローバル市場での成功につながります。
私たちは放課後、部活動の道具作りの話題からIECとJEMの深い話題へと踏み込んだ。Aは“IECは世界共通のルールで、海外の人もこの基準を見て作業するってことだよね?”と聞く。Bは“そう、ただし国ごとの認証は別にあるから、IEC準拠だけでは足りないことが多いんだ。日本国内ではJEMの指針とPSEが絡んでくる。”と説明する。二人は、実際の製品開発の現場で、どの規格を最優先にするか、どんな資料を作成すべきか、そして言語の違いが翻訳コストにどう影響するかを雑談形式で深掘りした。





















