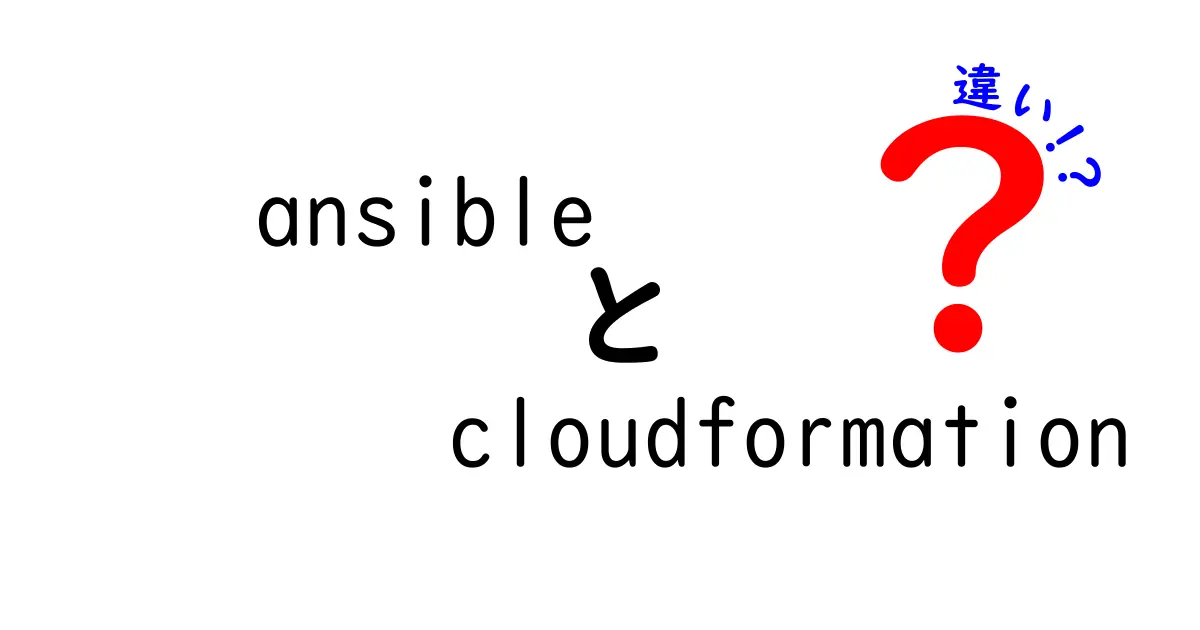

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
AnsibleとCloudFormationの違いを徹底解説:初心者にも分かる使い分けのポイント
クラウドの構成管理を学ぶと、AnsibleとCloudFormationという言葉をよく耳にします。両方ともインフラの自動化を目的としていますが、成り立ちや使い道は大きく異なります。まず、Ansibleは汎用的な構成管理ツールで、サーバーの設定、ソフトウェアのインストール、サービスの起動といった日常的な運用作業を一度書いたプレイブックを繰り返し実行して整えます。エージェントレスの考え方を取り入れており、SSH経由で対象ホストと対話します。そのため、オンプレミスからクラウド、そして複数のクラウドを跨いだ運用にも適しています。対してCloudFormationはAWSのネイティブなインフラ定義サービスで、クラウドリソースそのものの「宣言的な状態」をテンプレートとして表現します。要するに、何を作るかを宣言することで、AWSがその状態を実現するように動作します。
この違いは、実際の運用での適用範囲にも大きく影響します。CloudFormationはAWSのリソースと紐づくため、そこで生まれる整合性と自動的な依存関係解決が強みです。一方、Ansibleは跨プラットフォーム対応が強く、サーバーの設定変更を一括して適用する力があります。これを理解することが、最初の「何を自動化したいのか」という設問の答えになります。
実践的な使い分けのポイント
実務では、CloudFormationがAWS資源の管理を最もシンプルかつ確実にします。スタックの作成と更新、ロールバックの仕組みが組み込まれており、障害時の復旧も比較的楽に行えます。対してAnsibleは、複数の環境や異なるOS・アプリケーションを横断して同じ運用手順を適用するのに強みがあります。プレイブックは読みやすく拡張性が高いため、新しいサーバーやサービスを追加する際にも柔軟に対応可能です。言い換えれば、CloudFormationは「何を作るか」を定義する道具、Ansibleは「どう作るか・どう設定するか」を定義する道具だと覚えると選択が楽になります。さらに、学習コストやCI/CDへの組み込み、セキュリティポリシーとの整合性などを考慮すると、組織の成長段階での最適解が見えてきます。
以下のポイントを押さえると、より適切なツール選択ができます。
- クラウドはAWS中心か、それ以外の環境も含むか
- インフラと構成の結合度をどう考えるか
- チームの経験と学習コスト
- デプロイの頻度と変更の管理方法
ある放課後、友達と教室でAnsibleとCloudFormationの話を雑談風に深掘りしました。CloudFormationはAWSの資源を宣言的に定義するテンプレートで、リソースの最終状態を決めるとAWSが自動で整えてくれます。対してAnsibleは複数のOSやアプリを跨いだ設定を一括で適用する、汎用的な自動化ツールです。私たちはウェブサーバーの例を挙げ、CloudFormationならネットワーク設定やセキュリティグループまで一括管理できる点、Ansibleならアプリのデプロイや細かな設定変更を柔軟に組み合わせられる点を比較しました。冪等性の話題にも触れ、同じ手順を繰り返しても状態が崩れない仕組みが大切だと実感しました。初学者の私たちにも使い分けの感覚が少しずつ見えてきた瞬間でした。
前の記事: « 夢中と熱心の違いを徹底解説|使い分けで日常と学習が変わる





















