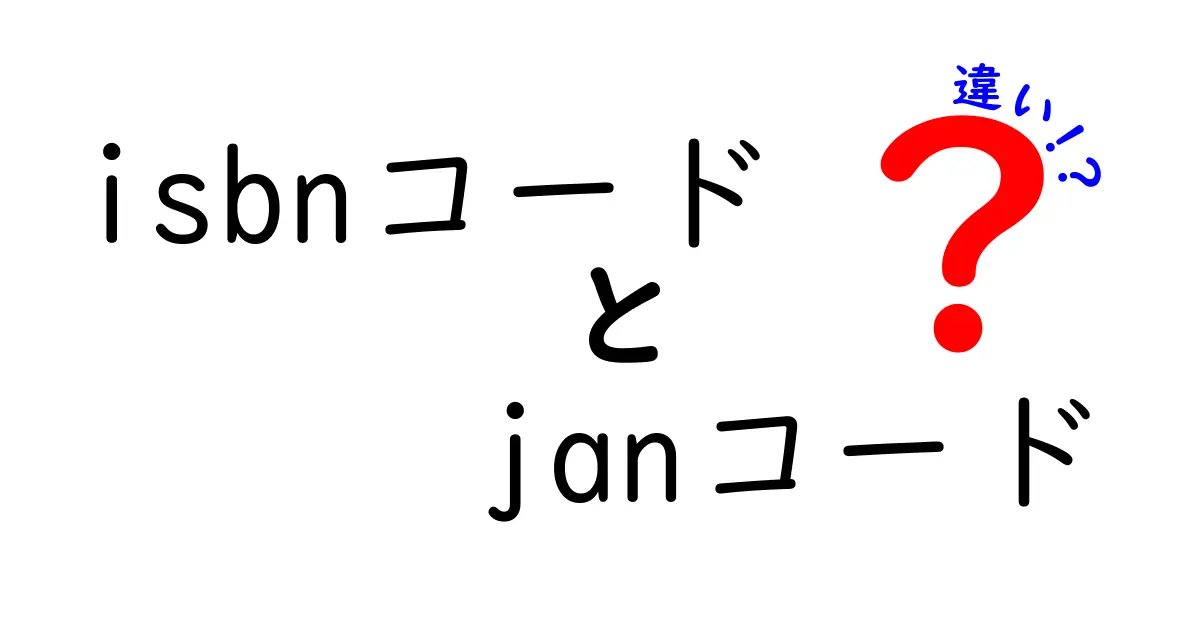

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
ISBNコードとJANコードの基本を一度に整理しよう
ここでは、世界で使われているISBNコードと、日本国内の流通で使われるJANコードの「違い」と「つながり」を、中学生でも分かる言葉でやさしく解説します。まず大前提として、ISBNは本を世界で一意に識別する番号、一方でJANは日本の小売流通で使われるバーコード番号という点を押さえましょう。ISBNは長く使われてきた国際ルールで、世界中の出版社が同じルールに従って番号を付けます。これに対してJANは、日本国内で商品を扱う店や倉庫が、商品を正しく管理・発注・売上げ計上できるようにするための仕組みです。
ISBNには通常13桁の表記が一般的ですが、歴史的には10桁のISBNが存在しました。現在は新規登録は13桁が基本で、13桁のうち先頭3桁は「978」または「979」といったプレフィックスが使われます。このプレフィックスの後ろには書籍を特定する番号が続き、最後の1桁がチェックディジットと呼ばれる検査数字です。
一方、JANコードは一般に13桁のEAN-13形式で表示され、日本国内の流通を対象に構成されています。書籍にもJANが付されることがあり、棚で読み取り機にかざすだけで在庫がすぐに分かるようになっています。
この2つを混同しないためには、用途と適用範囲を分けて覚えるのがコツです。ISBNは「本の世界的なID」、JANは「日本国内の商品のID」というイメージを持っておくと理解しやすくなります。以下の表とポイントを合わせて押さえておくと、授業や読書のときにも役立ちます。
① 何を識別しているのか:ISBNとJANの役割の違い
この段落では、ISBNが「本そのもの」を識別する番号であり、世界の図書館や書店、出版社などが共通のルールで使います。反対にJANは「日本国内での流通を管理するためのコード」で、書籍以外の食品・日用品・雑貨など、さまざまな商品を読み取り機で扱えるように整理します。つまり、ISBNは国際的な図書識別の規格、JANは日本国内の流通・管理のための識別規格と考えると理解が進みます。>この違いをしっかり押さえると、友人や家族と話すときにも説明がスムーズになります。
学校の図書館では、借りたい本の背表紙にISBNが書かれているのを見つけることがよくあり、海外の図書を借りるときにはISBNを基に検索をかけるケースが多いです。店頭ではJANコードを使って商品をスキャンし、在庫をすばやく管理します。これらの運用の背景には、それぞれが果たす役割の違いが関係しています。
② 数字の仕組みと実世界での使い分け
ISBNは、基本的に13桁の数字で構成されます。先頭の3桁は「978」または「979」というプレフィックス、次に続く9桁が書籍を特定する独自番号、そして末尾の1桁がチェックディジットです。このチェックディジットは、数字の並びが正しいかを機械や人が確認できるようにする検査数字で、誤入力を減らす役割を持っています。旧来の10桁ISBNは、13桁へ移行して現在は新規登録で主流です。
JANコードは、EAN-13形式で表示され、日本国内の流通を対象に構成されています。書籍にもJANが付くことが多いですが、同じ書籍にISBNと JANが両方付くケースがあり、店頭やオンラインで検索するときはどちらを使っても本を特定できることが多いです。実務では、出版社や流通業者がISBNを中心に管理しつつ、店舗の棚番号管理やPOSレジでの読み取りにはJANが活躍します。
以下の表は、両者の違いをひと目で比べられるように作成しました。読みやすさを重視して、項目ごとにポイントを絞っています。
表を見れば、対象、形式、用途、発行元といった基本情報が整理できます。
友達との休み時間の雑談風小ネタ: 私が授業でISBNとJANの違いを質問されたとき、こう答えました。「ISBNは本そのものを指す世界共通のIDで、海外の図書館や書店でも同じ番号を使う。JANは日本国内での流通を管理するバーコードで、日本の商品なら何でも識別できる。つまり本は国際的なID、日用品は日本の棚を整えるID、というイメージで覚えると混同しにくいんだ。さらに、ISBNは13桁が主流で、先頭の978/979と末尾のチェックディジットで成り立っている。JANも同じく13桁のコードだけど、用途は店頭の読み取りや在庫管理に強い。だから本を買うときにはISBN、スーパーで日用品を買うときにはJANを思い出すと覚えやすい、という雑談でした。
前の記事: « 店舗名と支店名の違いを徹底解説!初心者にもわかる基礎ガイド





















