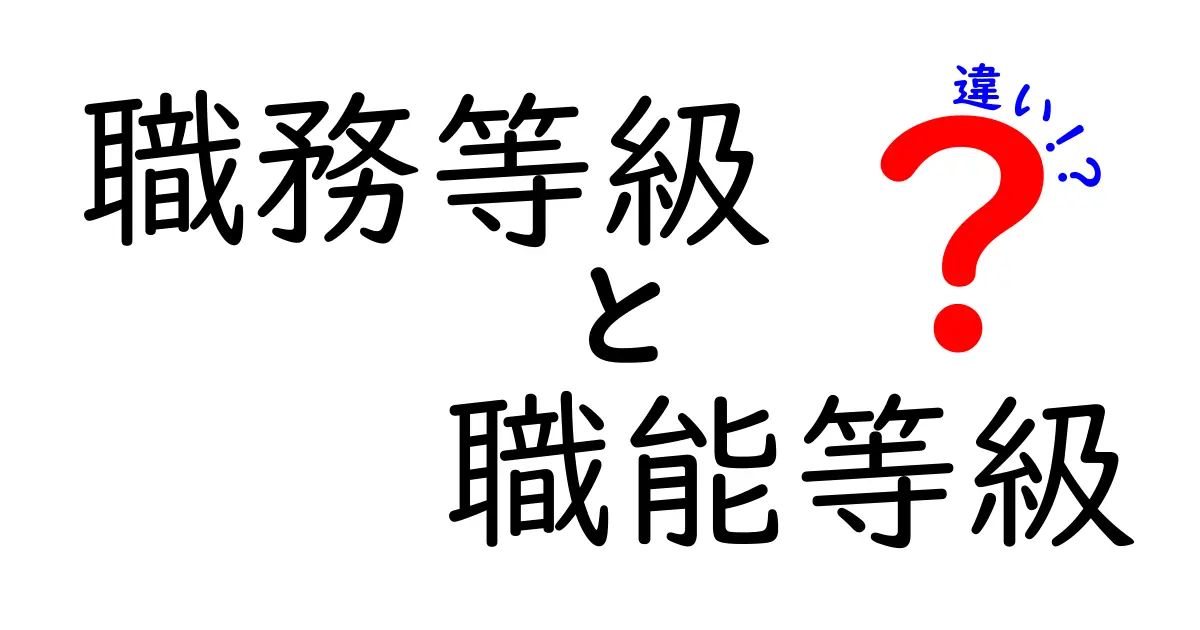

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
職務等級と職能等級の違いを知ろう:昇進の基準を誤解しないための解説
このテーマは、多くの人が職場で混乱するポイントです。職務等級と職能等級は、似た言葉のようでいて評価の軸が大きく異なります。職務等級は「その人が担う仕事そのものの難易度と責任の重さ」で決まります。仕事の規模、決断の度合い、部下の有無、予算の取り扱いなどが基準になります。一方、職能等級は「その人が持つ技能や能力の深さと幅」で決まります。技術力、専門知識、語学力、リーダーシップ、コミュニケーション能力など、個人の能力要素を評価します。
この2つの違いを理解することで、昇給・昇進の根拠が見え、キャリア設計がしやすくなります。以下では、それぞれの特徴と現場での使い方を詳しく解説します。
まずは全体像を押さえ、次に具体的な適用例を見ていきましょう。
職務等級とは何か
職務等級は仕事の「役割そのものの難易度と責任の重さ」を基準にします。つまり同じ部署でも、リーダー的な立場で意思決定を多く任される仕事は高い職務等級が付与されがちです。高い職務等級は給与レンジや昇進の機会にも直結します。実務の現場では、誰が誰の上司になるのか、誰が何を承認する権限を持つのか、予算をどう扱うのかといった要素が評価対象になります。もちろん、組織ごとに定義は異なりますが、共通しているのは「仕事そのものの価値」や「組織内での影響力」が基準になる点です。
この考え方のメリットは、ポジションの要件を透明化できる点です。人が同じ仕事をするなら、同じ級に配置されやすくなり、昇進の道筋が分かりやすくなります。デメリットとしては、実際の業務の難易度が市場環境やプロジェクトごとに変わる場合、基準の見直しが必要になることです。
具体例として、事務職であっても大規模な予算を扱い、部門を横断的にリードする役割を担う場合には高い職務等級が付くことがあります。対して、同じ職務名でも予算管理や戦略的決定の責任が少ない場合は低めの職務等級になることがあります。
つまり、「仕事の難しさと責任の大きさ」を出発点に評価するのが職務等級の基本です。
職能等級とは何か
職能等級は個人が持つ技能や能力の深さと幅を評価します。たとえばプログラミングの技術レベル、データ分析の精度、英語や他言語の運用能力、プレゼンテーション力、チームビルディングなどが対象です。仕事を「こなす力」が問われる場面で、この職能等級が上がると昇給や昇進の機会が増えることが多いです。長期的には、専門性の高い人材を育てるための制度として重要な役割を果たします。
この制度の魅力は、学習と成長の道筋がはっきりする点です。どの技能を伸ばせばどの段階まで到達できるのかが分かるため、個人の学習計画を立てやすくなります。ただし、測定が主観的になりやすい点には注意が必要で、評価基準をできるだけ具体化し、複数の評価者で共通理解を作る工夫が求められます。
職能等級は、技術系だけでなく人間関係のスキルやマネジメントの素養にも適用されます。例えば新しい技術を学ぶ意欲、複雑な課題を分解して解決策を提示できるか、同僚との協働を促進できるかといった要素が含まれます。
このように、職能の高さを評価することで、組織内での学習カルチャーを作る一助となります。
両者の違いと実務での使い分け
実務では職務等級と職能等級を組み合わせて用いるのが一般的です。
基本的な枠組みとしては、職務等級が「この仕事を誰が担当できるか」という土台を決め、職能等級が「その人がどれだけ成長・熟練しているか」を横から補完します。つまり、仕事の難易度と個人の能力の両方を見て総合的に評価します。
使い分けのコツをいくつか挙げます。
1) 新人や初級者には職務等級を低く設定しつつ、職能等級を上げるための研修を設計する。
2) 中堅層には両方をバランス良く評価して、リーダー候補を選定する。
3) 高度な専門職やマネジメント層には、職務と職能の両方を同時に高めるキャリアパスを示す。
このようにして、職務と技能の両方を意識して評価することが、社員の成長と組織の競争力を高めます。
透明性が高い評価は、社員のモチベーションと信頼感を育み、離職率の低下にもつながります。
昔の会社の同僚と昼休みに話したことが今も印象に残っています。彼は新卒で入ってきたころ、職務はまだ低くても技能を磨く意欲が高く、上司へ積極的に質問していました。その姿勢が評価され、職能等級を速やかに上げるための研修プログラムにも参加。半年後には小さなプロジェクトを任され、班のリーダー補佐としての経験を積みました。私たちはその話をして、昇進は「どの仕事をどう担えるか」と「どれだけ技能を身につけたか」の両方が組み合わさって決まるんだねと再認識したものです。結局、職務と職能の両輪が効くと理解したとき、キャリアは一気に動くという実感を彼は教えてくれました。





















