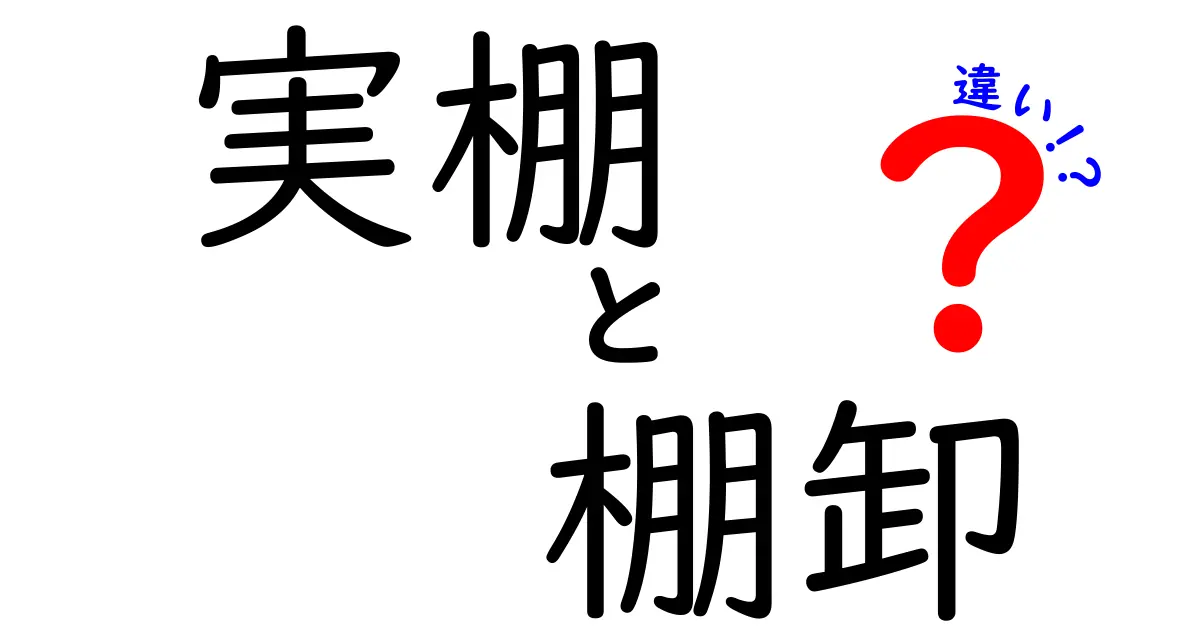

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
実棚と棚卸の違いを理解するための基礎
日常の現場でよく混同されがちな 実棚 と 棚卸 の違いを、まずは基礎から整理します。実棚とは現物の在庫を実際に数えたり確認したりして把握する行為のことです。つまり目の前にある箱やケースを触って数量を確かめる作業を指します。これに対して棚卸は帳簿上の記録と現物を照合する全体の作業プロセスのことを指します。棚卸には実際の現物確認に加え、記録の修正や差異の原因分析、関係部門への連携などが含まれます。つまり実棚は現物確認の行為そのもので、棚卸はその確認を通じてデータを正しく整える一連の活動です。ここを混同すると在庫の数が過少・過大になるリスクが生まれ、財務諸表にも影響します。
では、なぜこの違いを理解することが重要なのでしょうか。第一に、在庫管理の精度はコスト管理と資金繰りの安定に直結します。現物と記録のズレ が生じると、発注の過不足や出荷ミス、賞味期限の管理不全につながることがあります。第二に、棚卸を正しく実施することで、財務諸表の信頼性 が高まります。減損や評価損の判断、資産計上のタイミングなどが正確になります。第三に、棚卸は業務の改善にもつながります。棚卸を行うときには、在庫の滞留や過剰在庫、欠品の原因を分析する機会にもなるため、仕入れ計画や生産計画、物流の動線の見直しにもつながります。
このように 実棚 と 棚卸 は切り離して考えるよりも、現場の確認作業とデータ整備の両輪として理解することが大切です。以降のセクションでは、それぞれをより具体的に見ていきます。
要点をまとめると、実棚は現物の数量を実測する作業、棚卸はその実測を含む全体の評価とデータの更新プロセス、という2つの役割を持つということです。現場での手順を統一することで、ミスを減らし、業務をスムーズに回すことが可能になります。
実棚とは何か
実棚は現場での実測作業の具体例です。棚や箱を一つずつ確認し、SKUや品番、ロット、賞味期限など必要な情報を手元の端末に入力します。現物確認を行うときには、仕入先のバーコード と現物のラベルを照合します。使用する道具としては、カウント用の専用端末、セクションごとのリスト、ペンとノート、計数器などがあります。作業の流れは準備、実測、記録、確認、保管の順です。準備として、棚の区画分けを決め、担当者を割り当て、作業ルールを共有します。実測では、同一SKUが複数の場所に分散していないか、欠品や過剰がないか、期限切れがないか、部門間で確認します。記録は現場端末に入力されるか、紙の棚卸票に記入して後でデータ化します。照合が終われば、差異があればすぐ対応します。差異は原因を分析し、データベースを更新します。X社では実棚を週次のルーティンとして実施していますが、初期は人員の負荷が高くなることがあります。ここでのポイントは、日常的な実測の習慣化 と、正確なデータ入力、そして差異時の原因究明です。現場の混乱を防ぐためには、チェックリストの活用が欠かせません。これらを守ると、後の棚卸作業がスムーズになり、財務への影響を最小化できます。
現場の現物確認は、実務の信頼性を高める基盤です。たとえば、同じ品目でもロットが異なる場合は、優先順位を分けて管理します。こうした細かな点をうまく運用することで、在庫の鮮度と質を保つことができます。
棚卸とは何かと実務のポイント
棚卸は現物の実測と記録の照合を合わせて行う総称です。日常の在庫管理の中で、棚卸は月次、季節ごと、年度末などのタイミングで実施されます。全数棚卸と部分棚卸の2種類があります。全数棚卸はすべての品目を数える方法で、欠品の有無を正確に把握できます。一方、部分棚卸は特定のカテゴリや重要品目だけを対象にする方法で、作業を短縮します。実務上のポイントは、データの整合性を最優先にすることと、差異の原因分析を徹底することです。差異が大きいときには、原因を追究するチームを設け、調達、入荷、出荷、ロケーション管理の各部門に連携します。差異が大きいと財務への影響が大きくなるので、関係者を巻き込み必要な対応をすることが大切です。以下の表は実棚と棚卸の違いを簡単に整理したものです。観点 実棚 棚卸 意味 現物の数量を実測する作業 帳簿の数量と現物を照合する作業 目的 在庫の正確性の確認 財務の正確性と信頼性の確保 頻度 日常的な現場確認の一部として行う 月次・年次・任意のタイミングで実施
このように棚卸は会計上の正確さに直結しますが、実棚は現場の数え方に直結します。現場での正確な実測がなければ、棚卸でどんなに厳密に照合しても正確さは保てません。したがって、両者を組み合わせた運用が最も効果的です。さらに、棚卸の結果は財務報告や資金計画に直接影響します。差異が大きい場合は、在庫の評価方法の見直しや発注の見直しが必要になる場合があります。実務では、棚卸を実施する前に在庫データのバックアップを取り、作業後には再度データの検証を行うプロセスを設けると安心です。
放課後の話題で友だちと棚卸の話をしていた。店長さんが語る棚卸の本当の意味は「数を合わせるだけじゃない」という言葉だった。実棚で現物を数え、在庫の状態を把握する。その結果生まれた差異を分析して、発注の仕方や保管の仕方を改善する。私はそれを聞き、棚卸は現場とデータの橋渡しだと腑に落ちた。現場の手間を減らすには、カウントリストを事前に作る、同一SKUは同じ場所に揃える、バーコードを使って入力を自動化するなどの工夫が必要だと理解した。棚卸は単なる作業ではなく、在庫の質を守る仕組みづくりであり、組織の信頼性を高める大事な行程だと実感した。





















