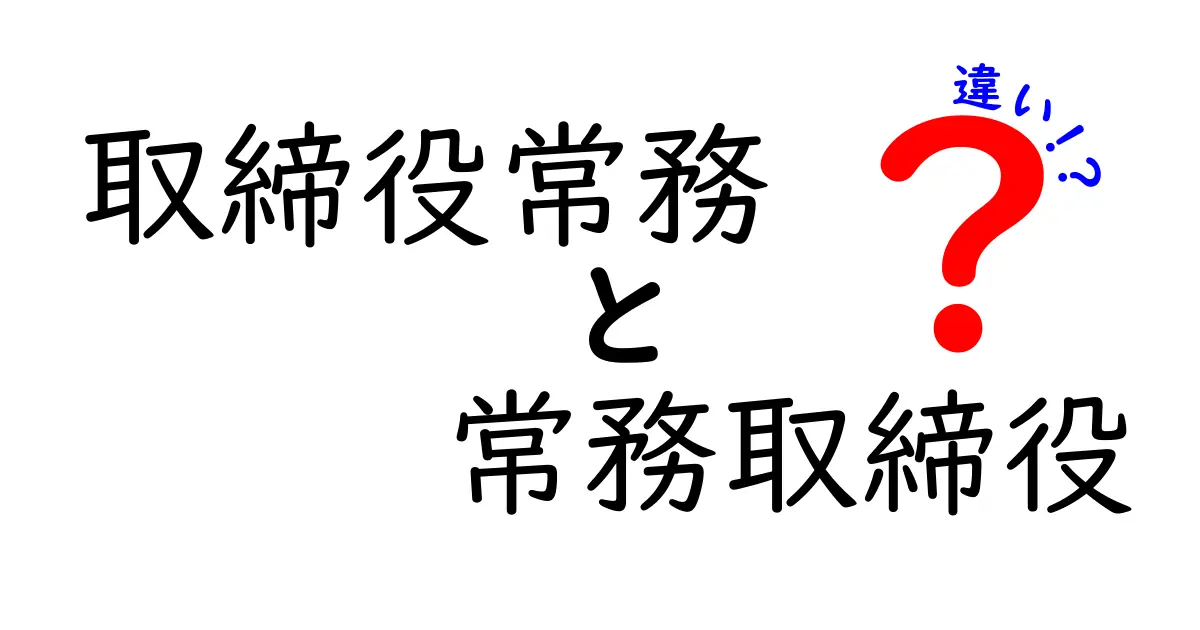

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
取締役常務と常務取締役の違いを理解する徹底ガイド
会社の経営陣にはさまざまな役職があり、名前だけではその権限が分かりにくいことがあります。特に取締役常務と常務取締役は似た響きで混同されがちですが、実際には役割や立場が微妙に異なる点が多いです。ここでは中学生にも分かるように、基本的な定義から現場での使われ方まで丁寧に整理します。まずは結論から。取締役常務と常務取締役は両方とも取締役の一種ですが 権限の度合いは所属する会社の定款や取締役会の決定によって決まることが多く、法的な区別というよりは組織運用上の呼称の違いです。
そのため同じ会社であっても 呼び方が違うだけで実際の責任範囲が同じ場合もあれば、逆に部門の責任がより広い人を指すこともあります。ここからは具体的な違いを、法的な観点と現場の実務の観点の2つの軸で整理します。
なお本稿での基本的な前提は日本の会社組織における一般的な理解であり、外国企業や非上場企業では事情が異なる場合があります。
1. 基本的な定義と呼称の背景
取締役常務とは、取締役の地位をもちつつ日常の業務執行を広く担う人を指す表現です。法的には取締役として株主総会と取締役会の意思決定に参加します。一方で実務の世界では常務として経営陣の中核を担い、複数の部門を横断して意思決定を動かす役割を果たすことが多いです。つまり 取締役としての地位と日常の実務執行の責任を同時に持つという点が特徴です。
ただしこの肩書きがあるからといって必ずしもCEO直轄の意思決定を行うわけではなく、会社ごとに権限の範囲は異なります。
現場の実務ではこの呼称を使う企業と使わない企業があり、同じ someday ではなくその組織の規程に合わせて運用されます。取締役会に出席する権限と、各部門の指揮を執る責任の双方を併せ持つ点が重要な特徴です。
2. 権限と職務の差
権限の差は企業によってかなり幅があります。基本的にはどちらも取締役としての権限を持つ点は共通ですが、日常業務の執行を誰がどの程度現場で統括するかという点が違いとして現れます。常務取締役は一般に現場の業務を実質的に統括する立場として扱われ、部門横断の調整や重大案件の実行計画を作成して実行します。一方、取締役常務は取締役会の中での序列や責任の割り振り方、組織内の指揮系統の組み方が少し異なるケースがあり、必ずしも現場の直接統括を意味しない場合もあります。
要するに 実務の中核を担う人という点は共通でも、現場での直接的な統括の度合いが企業ごとに差し、個別の職務分掌によって決まります。具体的には人事や財務、製造や販売の責任範囲の広さがポイントになります。表現の違いはあっても、現場での意思決定と実行の連携を強く意識している点は共通です。
3. 役員会での位置づけと意思決定の場
取締役会は会社の重要事項を決定する最高意思決定機関です。ここに出席するのが 取締役 の基本形ですが、取締役常務 や 常務取締役 はその中で特定の権限を付与され、日常の業務執行に関する決定を迅速に進める役割を担います。実務上は「部門長級の意思決定権を持つ執行権限」を持つことが多く、緊急の案件や予算の最終調整などを代表取締役や取締役会に報告しつつも、現場での決定をスムーズに進める仕組みを作ります。
この点が 取締役としての法的地位と執行責任の橋渡し役 としての位置づけを生み出します。
4. 就任要件・任期・報酬の現実
就任要件や任期、報酬については、会社の定款や就任規程により大きく異なる点が特徴です。多くの企業では取締役の任期は2年程度で、再任の可否は株主総会の決定に委ねられます。常務系の役職であっても、法的には取締役としての権限と任期が適用されるケースが多い一方、実務的な報酬は「役職手当」や「執行責任に対する報酬」の形で別途設定されることがあります。
重要なのは、同じ取締役でも肩書きによって報酬の算定方法が異なる会社があるという点です。したがって、所属する企業の人事規程を確認することが最も確実な方法です。
5. 実務上の混同を避けるポイントと実例
現場では、名称の違いだけで権限が変わるわけではない点に注意が必要です。実務での判断基準は、部門の統括範囲、決裁権限、そして取締役会への報告ラインです。例えば、ある企業では取締役常務が財務と人事を大きく統括する一方で、別の企業では常務取締役が製造部門を横断して戦略を決定します。これらは同じ「常務」という肩書きでも組織ごとに役割が異なる典型的な例です。
混同を避けるには、就任時の定款・規程の読み込み、部門の責任範囲の明確化、そして定期的な役職の役割再確認が有効です。最後に、組織図を自分の目で確認し、どの職位が誰を指揮しているのかを把握する癖をつけましょう。
補足と要点のまとめ
最後に簡単な要点を表にまとめました。 項目 取締役常務 常務取締役 補足 法的地位 取締役としての地位が基本 取締役としての地位が基本 いずれも取締役であり法的に同等の枠組み 権限の程度 実務執行の度合いは企業次第 実務執行の度合いが強いことが多い 部門横断の責任範囲は企業規程次第 意思決定の場 取締役会と現場の橋渡し役的役割が多い 日常の執行決定を担う場面が増えることが多い 呼称の違いが実務に影響する場合がある 就任要件・任期 会社の規定に準ずる 会社の規定に準ずる 定款や就任規程が重要 ble>報酬 役職手当等は企業次第 執行責任に応じた報酬設定が多い 同じ取締役でも差が出ることがある
友だちとカフェで雑談しているときの話題みたいに深掘りしてみよう。
君が部活の部長だとして、部長は部の意思を決める責任を持つけれど、部長が同時に日々の練習メニューを作って実行もしているとする。そんなイメージが取締役常務と常務取締役の背景に近い。
ただし実際の呼び方は会社ごとに異なるので、同じ人でも別の肩書きを使うことがある。結局は、法的な地位は同じでも現場での実務の責任範囲や決裁権限の配分がどう割り振られているかが大事。つまり名前よりも、組織図と指揮系統を確認することが大事なんだ。
前の記事: « 旅館業と民泊の違いを徹底解説!中学生にもわかる選び方と注意点





















