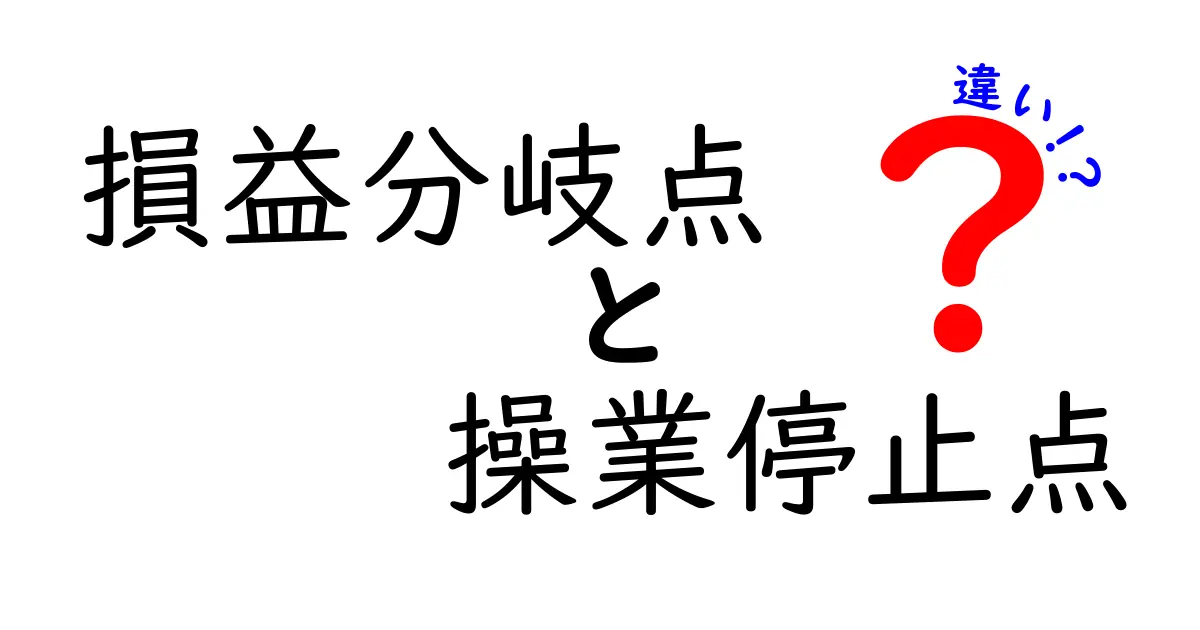

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
損益分岐点とは?
損益分岐点とは、企業が商品やサービスを販売して得た売上が、その商品のすべての費用(固定費と変動費)をちょうど賄うときの売上高のことを指します。
例えば、パン屋さんがパンを売って得たお金が、材料費や光熱費、人件費などの合計と同じになる点です。ここを超えると利益が出始め、下回ると損失が出ます。
損益分岐点は、企業の経営判断においてとても重要な指標です。ここを基準に、どれだけ売らなければ利益が出ないかを計算し、経営計画を立てます。
計算式はシンプルで、
損益分岐点売上高=固定費÷(1-変動費率)
となります。
ここで固定費とは売上に関わらず一定の費用(家賃や給料)、変動費とは売上に比例して変動する費用(材料費など)を指します。
損益分岐点を知ることで、必要な売上目標を明確にでき、無駄なコストを抑える努力にもつながります。
操業停止点とは?
一方、操業停止点は損益分岐点よりも重要度が高いかもしれません。
操業停止点とは、企業が操業(生産活動)を続けるかどうかの判断基準となる売上高のことです。
これは企業が製品を作り続けることで落ちる損失と、製品を一時的に作らない(操業を停止する)ことで発生する損失を比較して決められます。
具体的には、変動費を上回る売上があれば操業を続け、変動費を下回る売上となると操業を停止したほうが損失が少なくなる状況です。
つまり、操業停止点は
変動費と売上がトントンのところを指しています。
操業停止点売上高=固定費を除いて変動費を賄えるかどうかの境目です。
この点において、企業は「損が出ても操業を続ける」か、「無理して操業せずに一時停止する」かを決めます。
操業停止点よりも売上が低い場合は、操業をやめたほうが損失が小さいのです。
損益分岐点と操業停止点の違いをわかりやすく一覧で比較
それでは、損益分岐点と操業停止点の違いを簡単にまとめてみましょう。
| 比較項目 | 損益分岐点 | 操業停止点 |
|---|---|---|
| 意味 | 売上で固定費+変動費すべてを賄う点 | 売上で変動費のみを賄う点 |
| 売上高 | 固定費÷(1-変動費率)で計算 | 変動費に相当する売上高 |
| 判断基準 | 利益が出始める最低限の売上 | 操業を続けるか停止するかの境目 |
| 経営への影響 | 収益性の分析や計画に重要 | 操業の継続判断に重要 |
| 結果 | この点を超えれば利益がでる | この点を下回る場合操業停止が望ましい |
このように損益分岐点と操業停止点は似ていますが、見るべきポイントが違います。
損益分岐点は利益の発生点であり、操業停止点は生産を続けるかどうかの判断点です。
混同しやすいですが、企業経営ではどちらも非常に重要な指標なので理解しておくと役立ちます。
まとめ
・損益分岐点とは、売り上げが費用をすべてカバーして損益がゼロになる売上高
・操業停止点とは、生産を続けることで少なくとも変動費を賄える最低ラインの売上高
・損益分岐点を超えれば利益が出るが、操業停止点を下回ると生産停止を検討する
これらの知識があれば、会社の売上や製造コストを理解する助けになります。
今回は「損益分岐点」と「操業停止点」の違いについて分かりやすく解説しました。
これから経済や経営を学ぶ人にも役立つ内容ですので、ぜひ参考にしてください!
損益分岐点はよく知られていますが、操業停止点はあまり注目されません。
実は操業停止点は、「どれだけ売っても利益が出ないけれど、生産を続けるかどうかを判断する基準」なんです。
たとえば、パン屋さんが売上で材料費などの変動費はカバーしているが、人件費や家賃などの固定費は足りない場合は、損失は出るけどパンを作った方がいいと判断できます。
でも、売上が変動費にも満たなければ、パンは作らずに休業した方が損失を減らせるんです。
意外と知られていないですが、この違いを知っておくと経営のリアルが見えてきますね。
次の記事: 産業雇用安定助成金と雇用調整助成金の違いをわかりやすく解説! »





















