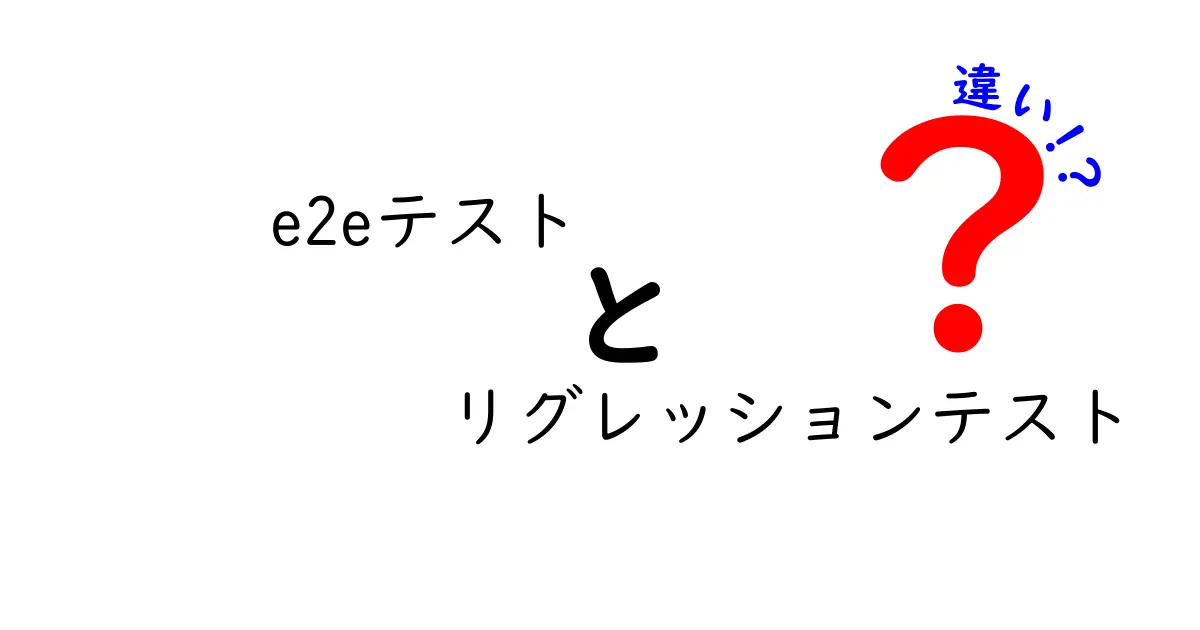

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
e2eテストとリグレッションテストの違いを理解するための基本
まずは二つの用語の基本を整理します。e2eテストはエンドツーエンドの略で、ユーザーが実際に操作する一連の流れを、システム全体の連携が正しく機能するかどうかを検証します。たとえばログインから商品を探し購入し、決済、確認メール、注文履歴の表示までを通して検証します。ここでは複数のコンポーネントや外部サービスが関係するため、環境をそろえるコストが大きくなりがちです。
リグレッションテストは、過去に動作した機能が新しい変更後も正しく動作するかを確認する検証です。既存のテストケースを再利用して、変更の影響範囲をなるべく狭く保つのが基本です。実行時間はe2eより短いことが多く、頻繁に回せるよう自動化の工夫が求められます。
要するに、e2eは「ユーザーの視点で全体の流れを検証する」もので、リグレッションは「機能の安定性を守る」ための反復検証です。
この違いを理解すると、テスト戦略の出発点がはっきりします。例えば新機能の導入時にはe2eを増やし、日常の回帰網を強化するイメージで進めると、品質を落とさず開発を回せます。
日常的な開発現場での使い分けと実践例
現場では「いつ、どのテストを走らせるか」を決めるルール作りが大切です。新機能の追加直後には、影響範囲を広く見たいのでe2eテストを優先して回すと良いです。これにより、ユーザーがつまずくポイントを早期に発見できます。一方で、変更が小さい修正やリファクタリングの場合は、リグレッションテストを中心に実施します。既存機能が壊れていないことを確認するため、自動化された回帰スイートを回すことが効率的です。
実務では以下のような工夫が役立ちます。まずテストの階層を「unit テスト → 統合テスト → e2e テスト」というピラミッド型に組み、コストと効果のバランスを考えます。次に、リグレッションの対象を「クリティカルパスとよく使われる機能」に絞り、時間内に回せるようにします。外部依存を減らす工夫や、テストデータの共通化、失敗時の原因分析を繰り返すことも重要です。
このような運用を整えると、起きてほしくない不具合を減らしつつ、リリースサイクルを回しやすくなります。テストを増やすだけでなく、結果を集計して頻出の失敗パターンを分析し、テストケースを拡充していくことが品質改善の近道です。
e2eテストって、名前はかっこいいけど実は現場での会話に似たところがあります。端的に言えばe2eは「最終的な使い勝手」を確かめるための検証です。私は友達と話していたとき、オンラインショッピングの一連の動作を最初から最後まで追ってみると、決済画面でエラーが出る、カートの中身が更新されない、メール通知が来ないといった細かい不具合だけでなく体験そのものが崩れる瞬間を拾えることに気づきました。だからこそ、ユーザーの体験を守るという視点が大切です。リグレッションは過去の失敗を繰り返さないようにする保険です。変更を加えるたびに設計の見直しが必要になる場面があり、そこには学びがたくさん詰まっています。つまり、e2eは体験の保証、リグレは安定性の保証という二つの目的があるんだよ、という結論に落ち着くのです。





















