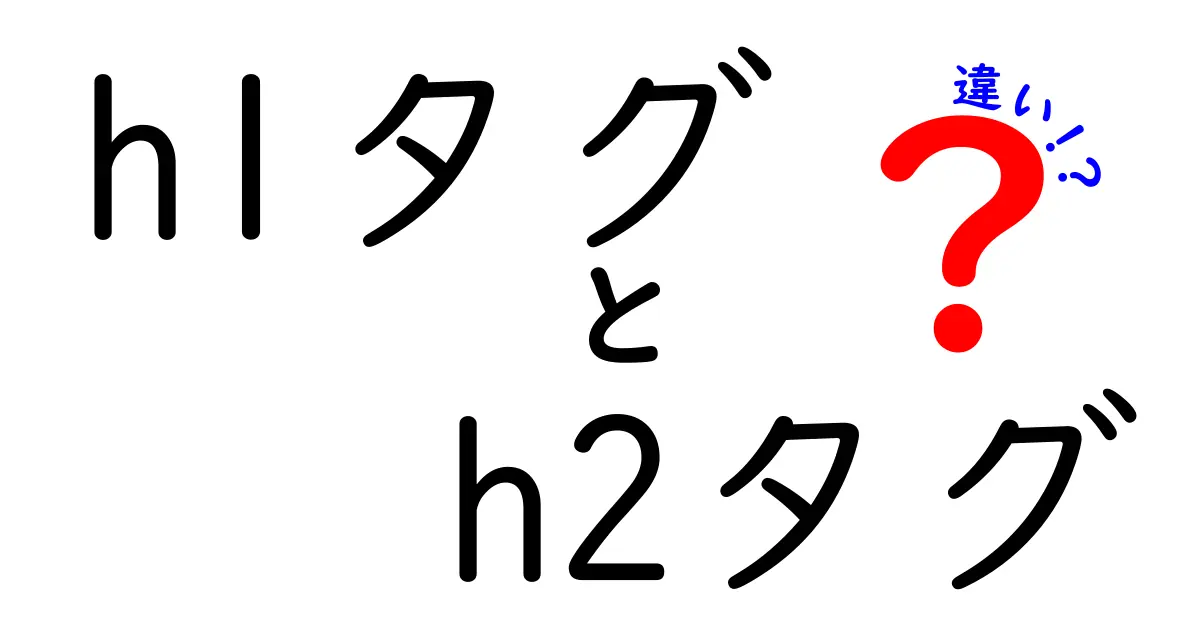

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
基本的な違いを知る
h1タグとh2タグは、HTML文書の情報設計を分かりやすくするための“見出し”です。h1はページ全体の主題を1つだけ示す最上位の見出しで、読者がこのページで一番伝えたい話題をつかむ手掛かりになります。これに対してh2は、ページの中の段落やセクションを分ける“道標”の役割を果たします。多くのウェブページでは、h1をページタイトルに使い、その下にいくつものh2を置いて、記事の章立てを作ります。
この階層は、視覚デザインだけでなく、検索エンジンにも情報の流れを伝える重要な手掛かりです。検索エンジンはh1の語句をそのページのメインテーマとして理解し、h2以下の見出しによって各セクションの内容を要約します。
またアクセシビリティの観点からも、スクリーンリーダーを使う人は
との階層構造を音声で追うことで、どの情報が重要で、どの部分が補足なのかを判断しやすくなります。
良い設計では、複数のH1を使わず、H2を必要なだけ増やすことが基本です。H1を1つに絞ることで、ページの主題がブレません。H2を適切に分けると、読み手は自分の興味のあるセクションへ自然と進み、長い記事でも迷わず読み進められます。さらに、SEOの観点では、H1とH2にキーワードを自然に分散させることで、検索クエリに対する適合度を高めやすくなります。使い分けのコツと実例
良い設計では、複数のH1を使わず、H2を必要なだけ増やすことが基本です。H1を1つに絞ることで、ページの主題がブレません。H2を適切に分けると、読み手は自分の興味のあるセクションへ自然と進み、長い記事でも迷わず読み進められます。さらに、SEOの観点では、H1とH2にキーワードを自然に分散させることで、検索クエリに対する適合度を高めやすくなります。
使い分けのコツと実例
実務での使い分けのコツは、まずページの全体像を決め、次に各セクションの内容を具体的に表す言葉をH2に置くことです。最初に1つのH1を設定します。H1は検索したときの第一印象を決めるので、短く要点をまとめ、商材名や話題の軸となる語を含めると良いです。続いてH2を、章ごとに“何が知れるのか”を端的に示す文にします。例えば、ある記事が「ダイエットの方法」についてなら、H2を『カロリー計算の基本』、『運動と栄養のバランス』、『実践のコツと落とし穴』などに分け、各セクションの中でさらにH3を使って詳述します。
この構造は、読者にとっては読み進めやすく、検索エンジンにとっては情報の階層が明確です。
また長い記事では、H2を適切な数に保つことが大切です。多すぎると読み手が迷い、少なすぎると内容が薄く感じられます。実務的には、1ページあたり3〜6つのH2を目安にし、各セクションを約400〜600文字程度にまとめ、全体で1000〜2000文字程度を目標にすると、読みやすさと情報量のバランスが取れます。さらに、H3の活用で細かなポイントを分けると、長文でも整理しやすくなります。
よくある間違いと改善点
よくある間違いは、H1を複数使う、H2を過剰に連ねる、あるいはH2にキーワードを過度に詰め込むことです。H1は1つ、H2は2〜5程度が適切な目安です。H2を省略せず、内容に応じて適切な語句を用いて分かりやすくすることが大切です。例として、ダウンロードサイトの説明文をH1にしてしまい、その後の見出しをH2で埋め尽くすと、主題が分かりにくくなります。代わりに、H1は「ダウンロード方法の総論」、H2は「準備」「手順」「よくあるトラブル」「よくある質問」など、セクションごとに整理します。
このように整理すると、読者はどの情報を探しているのかを直感的に掴めます。
さらにアクセシビリティの観点からも、H2が適切な階層にあるかを確認しましょう。スクリーンリーダーは見出しの階層を音声で読み上げるため、不自然な順序や欠落は利用者の理解を妨げます。
友だちとカフェで話しているような雰囲気で、h2タグについて深く掘り下げます。h2タグはH1の次の階層を作る“道標”の役割を果たすんだ。例えば教科書の章の見出しみたいに、各セクションの内容を簡潔に示すことで、読み手は次に何が来るのかを予想できる。実際のページ設計でも、H2を適切に分けると、スマホで縦に長くなる記事でも要点が掴みやすい。さらに、SEOの現場ではH2にキーワードを自然に含める工夫をする人もいるけれど、キーワードを過剰に入れすぎると文章の読みやすさが損なわれることもある。結局は“読みやすく、探している情報に速く辿り着けるか”が大事なんだ。だからH2は、短くても意味のあるものをつけよう。





















