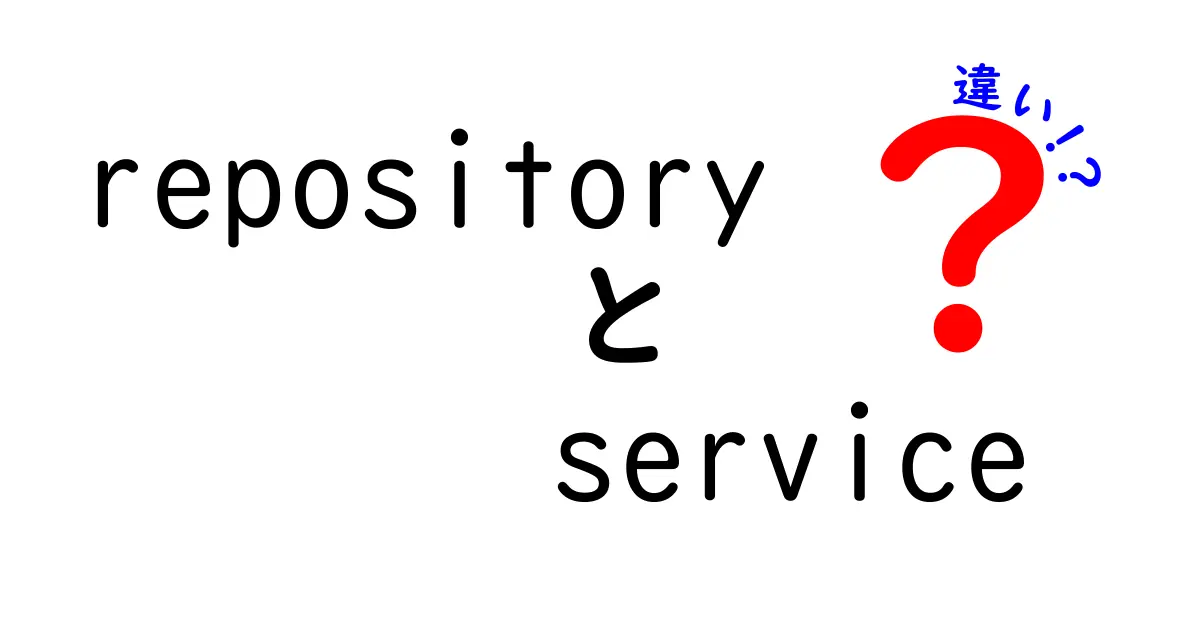

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:repositoryとserviceの違いを正しく理解する
ここでは リポジトリ と サービス の役割を混同せず、別々の責任として捉える考え方を身につけることを目的にしています。ソフトウェア開発では同じような言葉が別の意味で使われることがあり、初心者にとっては「何をどこに置くべきか」が分かりにくい場面が多いです。特に リポジトリパターン と サービス層 の違いは、コードの保守性やテストのしやすさに大きく影響します。
この説明を読んで、あなたのプロジェクトで「データの取得と保存」はリポジトリに任せ、「業務の流れや決まりごと」はサービスに任せる、という基本線をしっかりと作ってください。
まずは用途の違いを頭に入れ、実際のコードでどう割り当てるかを順番に見ていきます。
そのうえで、なぜこの区別が大事なのか、どのようにテスト設計に影響するのか、具体例を交えて説明します。
この段落だけでも、要点の要約として 責任の分離 が大切だと理解できるはずです。
それでは、リポジトリとサービスの基本を一つずつ詳しく確認していきましょう。
リポジトリ(Repository)とは?その役割と目的
ここでいう リポジトリ には主に二つの意味があります。一つはコードの保管場所としての コードリポジトリ、もう一つは設計パターンとしての リポジトリパターン です。どちらも「データを扱う場所・方法」を表しますが、意味と役割は異なります。
コードリポジトリはファイルやバージョンを追跡する場所で、プログラムの構成要素を安全に保管する役割を果たします。敵対的な環境では履歴管理が命綱になることもあり、プルリクエストやブランチを通じて協働をスムーズにします。
一方でリポジトリパターンは、ドメインの「データの取得・保存の仕方」を抽象化するための設計手法です。データの取得方法 や データの変換、インターフェースの統一 を通じて、上位のビジネスロジックがデータの細かな実装に影響されずに動くようにします。
この二つを混同すると、後で混乱が生まれます。リポジトリパターンの目的は「データアクセスの複雑さを隠蔽すること」にあり、実装の背景としては データベースの種類や ORM の差異に強くなる設計、テスト時には フェイクやモックを使いやすくする 効果があります。
結論としてのポイントは、リポジトリは「データへの入口と出口を整える設計」であり、ビジネスロジックを含まない、または厳密には含めずに分離するべきという点です。
サービス(Service)とは?どんな動きを担当するか
サービスはビジネス上の「どう動くべきか」を決める役割を担います。サービス層 は、複数のリポジトリを組み合わせて一連の業務フローを実行したり、データの整合性のルールを適用したりします。
ここでのポイントは、サービスが 業務ロジック の責任を持ち、データの保存場所やクエリの具体的な形を直接知る必要がない、という点です。つまり 「何をどうするか」 を決め、「どこに保存するか」や「どう取得するか」 はリポジトリに任せる、という分業です。
中学生の言い換えで言えば、サービスは学校の校務のように「この通知を出す」「この処理を順番に実行する」という流れを決め、リポジトリはその準備を整える工作部のような存在です。
この分業によって、後から新しいデータ源を追加したいときも、ビジネスロジックを変えずに対応できます。
また、サービスはテストの観点からも有利です。実際のデータベースを使う代わりにモックを使えば、業務の流れを確認しやすく、失敗時の挙動も検証しやすくなります。
違いを分ける3つのポイント
リポジトリとサービスの役割を混同しないためには、まず「責任の分離」という原則を常に意識することが大切です。第一のポイント は役割の分離です。リポジトリ はデータの入口・出口を取り扱い、 business ロジックには踏み込みません。
第二のポイントは「データ取得と業務処理の分離」です。データをどう取得するかはリポジトリ、業務の判断をどう進めるかはサービス、という切り分けにより、後から新しいデータベースや新しいビジネスルールを追加しやすくなります。
第三のポイントは「テストのしやすさ」です。リポジトリをモック化することで、業務ロジックの動作を isolated に検証でき、バグの原因を特定しやすくなります。
以下の表は、実務での役割の違いを簡単に視覚化したものです。
このように、責任の分離 を徹底するだけで、将来の拡張が楽になります。実務ではこの関係を厳格に守ることが、コードの読みやすさと保守性を大きく高めます。
次のセクションでは、具体的な使い分けの場面をいくつか挙げ、実際のコード設計の観点で見ていきます。
また、よくある誤解として「リポジトリに全てのビジネスロジックを詰め込んでしまう」というパターンがありますが、これは避けるべきです。リポジトリはあくまでデータの窓口、サービスは業務の道筋 を決めると理解しておくとよいでしょう。
実務での使い分けの具体例
例えばユーザー情報を管理するアプリを考えます。リポジトリはユーザーのデータベースから「ユーザーを探す」「新しく追加する」といったデータ操作を担います。
一方で サービス は「新規登録時のビジネスルールを適用する」「退会処理と連携する他の処理を順番に実行する」といった業務の流れを決めます。
この場合、サービスは複数のリポジトリを組み合わせて処理を実行します。たとえば、ユーザーだけでなく関連するプロフィール情報や通知の処理も一連の作業としてまとめる、という形です。
別の例として、外部の決済サービスと連携する場合にも、決済の成否に応じて次の処理をどうするかという「業務フロー」をサービスが担い、決済情報の保存や取得はリポジトリが担当します。
このように、実務では「データの取得・保存をリポジトリに任せる」「業務の流れをサービスで統括する」という基本形を軸に、さまざまなケースへ拡張していきます。
よくある誤解と注意点
よくある誤解のひとつは「リポジトリとサービスは同じものだ」というものです。リポジトリはデータの窓口であり、サービスは業務の道筋を決める指揮をとるものです。
もう一つの誤解は「すべてのデータ操作をリポジトリに任せればいい」という考えです。実際にはビジネスルールや整合性の判断はサービス側にあり、データの保存形式をどうするか、どのデータを結合するかはリポジトリの責任範囲です。
メリットとしては「変更の影響範囲が狭くなる」「テスト設計が楽になる」「新しいデータソースの追加が容易になる」。デメリットとしては「過度な分離によりコードが散らばること」「小さな変更でも設計が大きく変わってしまう場合がある」などがあります。
このような点を頭に入れて、役割を適切に割り当て、設計をシンプルに保つことを心がけましょう。
最後に、学習のコツとしては、実際のコードを見ながら「この場所でデータを取り出し、ここで業務を進める」という流れを可視化してみることです。
今日は友達との雑談風に深掘りしてみるよ。リポジトリはデータを取ってくる窓口、サービスはその窓口を使ってどう動くかの計画表みたいなもの。「データの入口」と「業務の流れ」の分担があると、コードがきれいにまとまる。たとえばゲームアプリを例にすると、リポジトリは「スコアデータを保存する仕組み」を提供し、サービスは「新しいスコアが入ったときのルールを適用して通知するかどうか」を決める。これが分かれていると、新しいデータソースが増えても、ビジネスの流れを変えずに対応できる。逆に一つの場所に両方詰め込むと、変更の影響範囲が広がり、後で修正が大変になることが多い。だから最初から「データの扱い」と「業務の流れ」を別々に設計する癖をつけると、長い目で見て楽になるんだ。





















