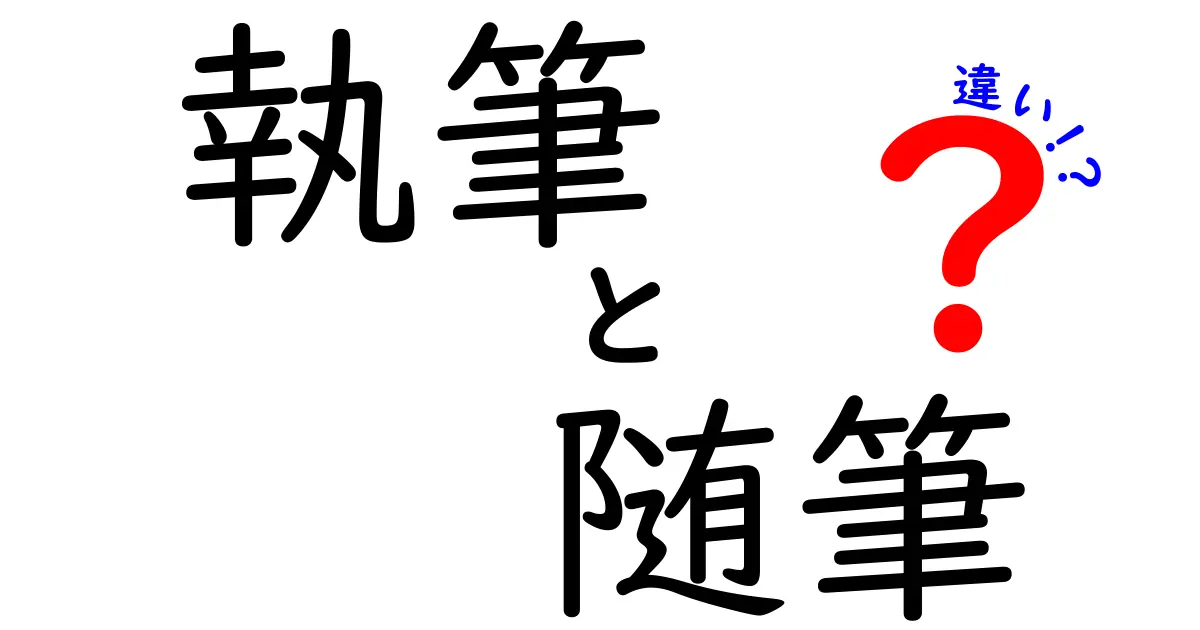

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
執筆と随筆の違いを詳しく解説する基本ガイド
このセクションでは まず執筆と随筆という言葉が指す範囲の基本を整理します。執筆は文字で思考を形にして何かを伝える行為全般を指す言葉です。学校の課題、レポート、論文、ブログ投稿など形は多様で、目的は情報の正確さや説得力を高めることが多いです。一方、随筆は個人的な視点や体験、記憶をもとに自由な形式で書かれる文学的な表現です。題材は若干日常的で身近なものが多く、読者に自分の感情や考えを伝えることを主眼にします。これらの差は表現の硬さや構成の自由度にも現れ、読み手が何を求めているかによって使い分けが変わります。
まずは基本的な違いを押さえましょう。執筆は目的が情報伝達や論証、手順の説明など論理性を重視することが多く、読者に結論へ導くことを意識します。文章は分かりやすさと正確さを重視し、箇条書きや図表を使って整理することも一般的です。対して随筆は感情の揺れや個人的な体験の語り口が重要で、形式は自由で構成も一定ではありません。語り口調が親しみやすく、著者の声が直接読者に届くことを狙います。
次に、場面ごとの使い分けを考えてみましょう。学校の授業や試験では執筆が中心になる場面が多く、情報の正確さと論理の流れが評価の鍵を握ります。反対に日記やエッセイの課題、読書感想文、ブログ記事などでは随筆的な要素を取り入れると、読者に共感や興味を引きやすくなります。以下の表は執筆と随筆の違いを短く比較するための目安です。
執筆と随筆は同じ書く行為でも、目指す成果物や読み手との関係性が異なります。強調したいポイントは 「目的に合わせて言葉を選ぶ」こと、そして 「読者に届けたい気持ちをどう伝えるか」を考えることです。これを意識すると、初めは難しく感じても次第に書きやすくなります。
読み手の立場を想像しながら、まずは自分の伝えたいことをはっきりと整理することから始めましょう。
執筆と随筆の違いを日常的に使い分けるヒント
日常生活の中で執筆と随筆の感覚を使い分けるコツをいくつか紹介します。まず、情報を伝える場面では 「結論→根拠→具体例」の順で構成する練習をします。次に、自分の感じたことを素直に書き出す習慣をつけたいときは随筆の要素を意識的に取り入れ、体験の順序や場面描写を丁寧に描くとよいです。さらに、<object>見やすさを高めるために、見出しを使って段落を区切り、箇条書きや表で要点を整理すると、読み返しやすくなります。中学生の皆さんには、授業ノートを執筆的に整理する練習と、日記や感想文を随筆的に自分の感情と結びつけて書く練習をセットで取り組むことをおすすめします。経験を積むほど、両者の境界線は自然と見えてくるでしょう。
随筆という言葉の自由さを友達と雑談しながら深掘りするなら、まず「自由回答の文学」とでも言える随筆の魅力について、個人的な体験と他者の視点を混ぜて語ってみるといい。私が中学時代に日記で感じた小さな出来事、例えば雨の匂いと校庭の匂いの違い、友だちとの小さな誤解から得た気づきを、形式にとらわれず書き留めると、読み返したときに自分自身の成長を実感します。執筆よりも気軽で、でも心の奥底が透けて見えるのが随筆の魅力。





















