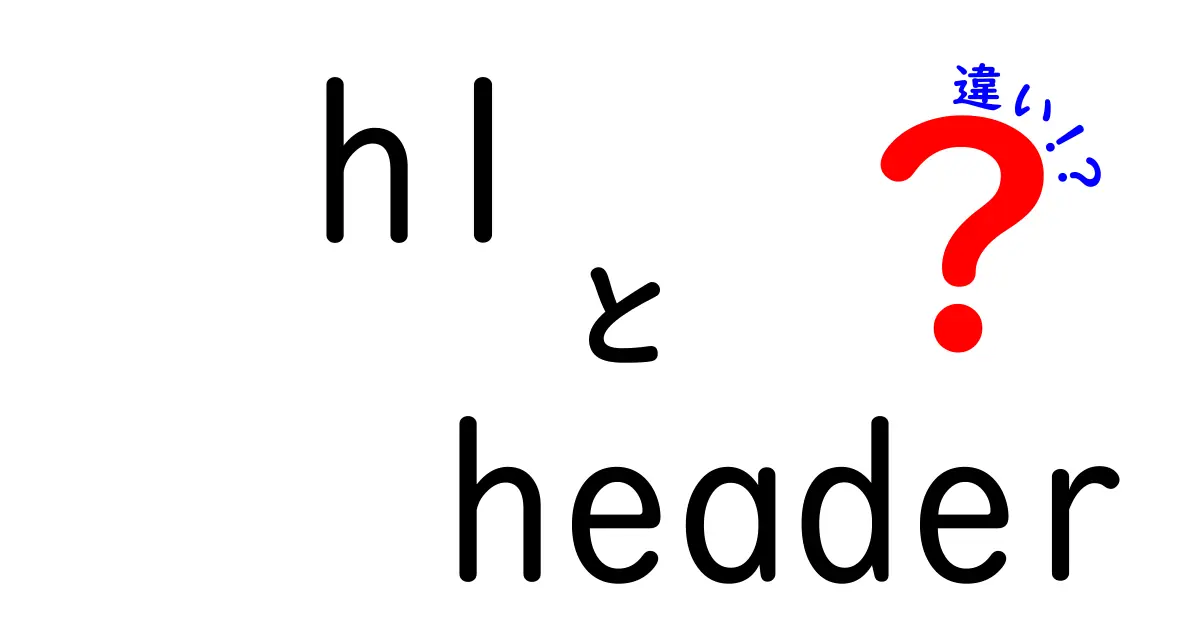

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
h1と他の見出しタグの基本的な違い
h1はウェブページの最上位の見出しとして役割が決まっています。多くのサイトではページの主題を示すタイトルとして使用され、検索エンジンはこのタグをページの話題を判断する手掛かりにします。つまり、h1は“そのページの主題”を一意に伝える役割を持ち、複数回使うべきではありません。反対に、h2以降の見出しはページの中のセクションを区切るための道標です。デザイン面では、 h1はデフォルトで大きく太字になることが多く、読み手が最初に目にする情報となります。そのため、 キーワードの選定と一文の明確さ が特に重要です。適切に使えば、読者が長い文章の中でどこを読めばよいかを直感的に理解できます。
しかし、 h1を何度も使うと構造が崩れ、スクリーンリーダーを使う人にとっては混乱の元になります。
実務では、1ページにつき1つのh1を基本として、その下にh2/h3で階層を作るのが一般的なルールです。これにより、ページ全体の意味が整理され、検索エンジンにも「このページはどんなテーマに関する記事か」が伝わりやすくなります。例えば、旅行記事なら h1に「東京のおすすめ観光スポット」、h2に「1日目のルート」「2日目のグルメ情報」などと分けると良いです。
このような考え方はSEOだけでなく、情報の整理にも役立ちます。正しい階層を守ること、主題を1つに絞ること、そして読者が迷わない導線を作ること、これらが基本です。
SEOとデザインの観点から見る実践的な使い方
実務での運用では、 h1の語数は短くするのが効果的です。検索エンジンは長い文よりも要点を短く伝えるタイトルを好む傾向があります。例えば、ユーザーが検索で「h1 header 違い」と入力する場合、タイトルにはそのキーワードを含めつつ、ページのテーマを明確にする一文を入れると良いでしょう。配慮点として、キーワード過剰詰め込みを避け、代わりに自然な文章を心掛けること。視覚デザインでは、h1のフォントサイズや行間をCSSで制御して、読みやすさと印象を両立させることが大切です。
また、アクセシビリティの観点からは、スクリーンリーダーが見出しを順番に読み上げるため、階層が適切であることが重要です。階層が乱れていると、読者はセクションのつながりを見失い、ページの理解が遅れます。ここで実践的なコツをいくか挙げます。
1) ページの主題を最初のh1に集約する
2) セクションの重要度に応じてh2, h3を適切に使い分ける
3) キーワードを過度に配置せず、自然な文章で伝える
4) スタイルはCSSで統一し、見出しのスタイルを揃える。
この4点を守れば、読者の理解と検索エンジンの評価の両方を高められます。最後に、この記事のテーマを再確認します。h1はページの指針、h2〜h6は内容の道案内。正しい構造を保つこと、読者に伝わる文章にすること、SEOとアクセシビリティの両立を意識すること、この3つが成功の鍵です。
実は h1 というのは“ページの顔”のような存在です。最初に目に入る大切な要素であり、SEOの観点だけでなく、読者の第一印象にも大きな影響を与えます。私がサイトを作り始めた頃、h1を適当に決めてしまい、あとから「何の記事だったっけ?」と悩んだ経験があります。その経験から、h1はその記事の要点を一言で伝える短い文にするべきだと学びました。例えるなら、店の看板のように、訪問者が何を得られるのかを直感で理解できるフレーズが理想です。みなさんも、記事を書くときには一度“このh1で伝えたいことは何か?”を自問してみてください。きっと、文章が引き締まり、読者の関心も高まるはずです。
前の記事: « 字数と文字数の違いを徹底解説!中学生にもわかる使い分けガイド
次の記事: 執筆と随筆の違いを徹底解説!中学生にも伝わる使い分けガイド »





















