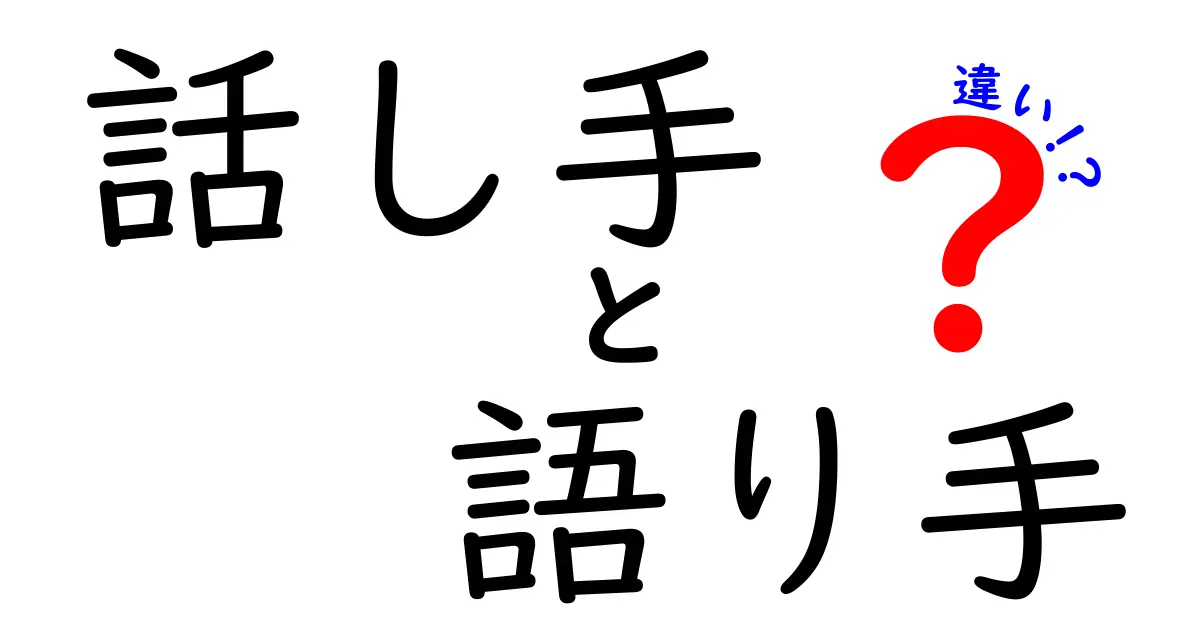

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
話し手と語り手の違いを知ると文章が変わる!
このセクションでは、日常でよく混同されやすい「話し手」と「語り手」の意味の違いを、例を交えながら丁寧に解説します。
「話し手」は文字どおり話している人を指し、会話の中での実際の発話者を示します。
一方で「語り手」は物語を進める声、あるいは物語を語る視点を持つキャラクターのことを指すことが多いです。
つまり、話している本人と、物語を語る声は別のことがあるのです。
この違いを理解すると、文章を読んだときに、誰の立場で語られているのか、どの情報がどう伝えられているのかが見えやすくなります。
ポイント:日常会話では「話し手」を、物語やニュースの解説・再話には「語り手」を使い分けるのが自然です。
この理解を押さえておくと、読んだ人が混乱せずに情報の出どころを追いやすくなります。
話し手の特徴と使われ方
話し手は、実際に言葉を発する人のことを指します。
直接話法や引用を使うときは、話し手が誰であるかを明確にすることが大切です。
例えば、会話の場面では「太郎が『明日行くよ』と話した」というように、発話の主体を示します。
話し手はその場の時間・場所・感情を伝える役割を担い、文脈によっては恥ずかしさや興奮、安心感などの心理的ニュアンスを読者に伝える効果があります。
強く伝えたいポイントは、直接発話のときは特に主語が重要です。
また、教育的な文章では、話し手が誰であるかを常に意識させるため、動作や感情の説明と合わせて「話し手の意図」を読者に伝える工夫をします。
語り手の特徴と使われ方
語り手は、物語の世界を案内する「語りの声」として機能します。
語り手は必ずしも実際にその場で話している人物とは限りません。
第一人称の語り手なら自分自身の視点で語ることが多く、第三人称の語り手なら外部の視点から出来事を語ることが一般的です。
語り手は、情報の順序を決めたり、読者に必要な背景を選んで伝えたりする責任を持っています。
このため、語り手の性格・信頼性・距離感(読者との距離感)によって、物語の印象は大きく変わります。
語り手の多様性を理解すると、同じ出来事でも受け取る印象が変わることがわかります。
語り手という言葉には、ただ“物語を伝える人”以上の意味が潜んでいます。私たちが本を読んだとき、語り手の距離感や信頼性が物語の印象を大きく左右します。例えば、第一人称の語り手が語ると、読者は話者と同じ視点に立ち、心情を直接感じ取りやすくなります。一方、第三者の語り手は広い視野で出来事を整理して見せ、説明的な情報を組み込みやすい。こうした選択が、私たちの理解を深めたり、物語の面白さを生むのです。さらに、語り手がどの程度の情報を読者に開示するかも重要です。語り手が秘密を少しずつ明かすと、緊張感が高まり、読者の関心を引きつけます。語り手の視点を切り替える技法も、場面転換の合図として有効です。





















