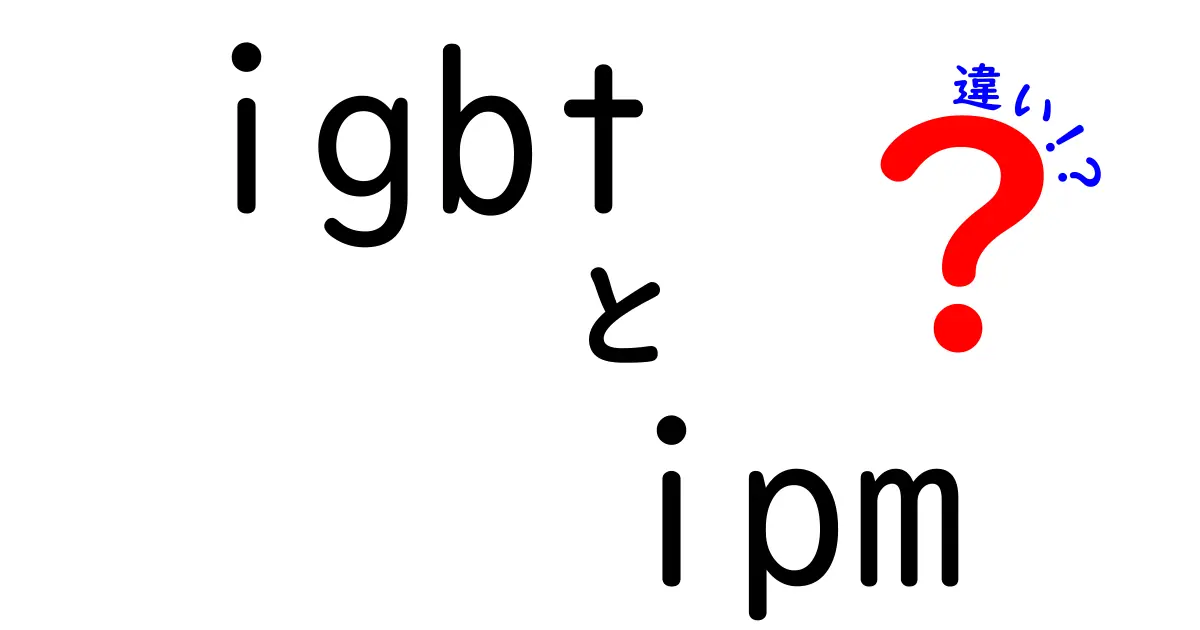

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
IGBTとIPMの違いを知って賢く部品を選ぼう
ここでは IGBT と IPM の違いを、技術的な話だけでなく日常の電子機器の選択にも役立つ観点で解説します。
初心者でも理解できるように、用語の意味や役割を丁寧に分解します。
まず大切なのは、IGBT は電力をスイッチングする「部品そのもの」であり、電流を流したり止めたりする機能を担う半導体です。対して IPM はその上に「動作を制御する回路」や「保護機能」を組み込んだ「モジュール」です。つまり IGBT は個別の部品、IPM は部品と統合回路をセットにした完成品に近い存在です。
この違いを理解するだけで、設計時の選択肢が大きく変わります。特にモーター制御や電源インバータを設計する場面では、単純に性能が良いだけの部品を選ぶのではなく、保護機能や駆動回路の有無、保守性、コストといった要素を総合的に評価することが大切です。
本記事では、構造の違い、動作原理、実務での使い分け、そして価格・信頼性の観点から詳しく解説します。
難しい用語はできるだけ噛み砕いて説明しますので、読み進めるうちに質問が思い浮かぶはずです。
最後には、あなたの用途に最適な選択肢を絞り込めるポイントをまとめます。
はじめに、IGBTとIPMって何者か?
IGBTはInsulated Gate Bipolar Transistor の略で、電力をスイッチングするための半導体素子です。高電圧・大電流での制御が得意で、インバータや電動機の制御に広く使われます。IGBTは単体の部品として性能を競い合いますが、現場ではそのまま使うのではなく、ドライバ回路や放熱設計、保護機能と組み合わせて使うことが多いです。IPMはIntelligent Power Module の略で、IGBTやMOSFETと保護回路、駆動回路、時にはキャパシタやダイオードまでを一つのモジュールにまとめた製品です。IPMは「賢い power module」として、現場での組み込みが楽になるよう設計されています。
つまり、IGBTはスイッチングの核となる部品、IPMはその周辺回路を含めた完成度の高い製品と考えてください。
この違いを意識するだけで、設計時のリスクを下げ、保守性も向上します。
| 項目 | IGBT | IPM |
|---|---|---|
| 構成 | 半導体素子のみ | IGBT + ドライバ + 保護回路 + 放熱部品 などを統合 |
| 設計難易度 | 高め | 低め、組み込みが容易 |
| コスト | 安価なケースもあるが周辺部品が必要 | 総合的には高めだが設計工数を削減 |
一つ目の違い:構造と役割
最初の大きな違いは「構造と役割」です。IGBTは電力を切り替えるための基本的な半導体素子で、スイッチとしての役割を果たします。ここでは“スイッチの開閉”が主目的で、駆動回路は別に用意します。
対して IPMは、スイッチの他に駆動回路、保護機能、場合によっては放熱設計までを一つの筐体に詰め込んだ「モジュール」です。これは現場での取り付け作業を大幅に簡略化し、故障時の原因追跡を容易にします。
図で見ても、IGBTは単体のスイッチ、IPMはそれを包む“箱”のようなイメージです。
実務では、部品点数を減らせるIPMを選ぶことで、 assemblage(組み立て)時間を短縮し、初期の設計ミスを減らすことが期待できます。
ただし IPM は“全てお任せ”という意味ではなく、場合によっては放熱設計や駆動条件が特定のモジュールに適合していないケースもあるため、用途に応じた選択が重要です。
二つ目の違い:動作原理と制御
IGBTの魅力は「高電圧・高電流を扱える点」と「高い耐久性」を両立できる点にあります。IGBT単体を用いる場合、ドライバ回路や保護機構を別途用意する必要があり、設計者には回路設計の自由度と引き換えに高度な知識が求められます。これにより、効率の最適化や熱設計の調整が可能ですが、同時に安定動作を確保するための検証工数も増えます。
一方の IPM は、駆動回路や保護回路が内蔵されているため、初期設計の難易度が低く、短期間での組み込みが可能です。動作原理としては、モジュール内のドライバがIGBTのゲートを適切な信号で制御し、過電流・過電圧・短絡などのトラブルを検知して保護します。
しかし、IPM が提供する保護機能は「標準化された範囲での保護」に留まることが多く、特殊な条件や高信頼性を要求されるミッションでは、追加の対策が必要になる場合があります。
三つ目の違い:価格・寿命・実務上の使い分け
実務では「コスト対メリット」の観点が非常に重要です。IGBTは部品単体のコストは抑えやすい場合がありますが、駆動回路・保護回路・放熱設計を別途用意するため、搭載時の総コストと開発工数が増大します。特に小規模開発や早期試作では、この点が大きな障壁となることがあります。
対して IPM は、初期の設計工数を抑え、現場への導入をスムーズにします。保護機能や駆動条件がモジュールに内包されているため、信頼性の高い動作を比較的短時間で実現可能です。
寿命の観点では、どちらも適切な熱設計と適用条件を守ることで長寿命を実現できますが、IPM は「組み込み済みの保護がある分、長期的にはトラブル要因の少ない設計」を助けます。ただし、IPM の選択肢が増えると、特定の動作条件に最適化された製品同士の比較が難しくなることもあるため、現場の要件を明確にして選ぶことが重要です。
要点としては、量産・安定運用を重視するなら IPM、カスタム駆動回路を細かく設計したい場合はIGBT を選ぶのが基本的な戦略です。
「IGBTは部品そのものを選べる自由度がある代わりに、駆動回りを自分で作る必要がある。つまり自分の手で制御の設計を楽しめる人には向いている。一方IPMはモジュール全体がまとまっているから、組み立ては楽で信頼性も高い。けれど選択肢がIPMの中で決まってしまい、細かい条件まで自分でいじる余地は少ないかもしれない。」
友人は「じゃあまずは手軽に動かせるIPMから始めて、余裕が出たらIGBTで自分仕様の駆動回路を作るのが良さそうだ」と言った。私は頷き、「要は用途と時間の余裕、そして設計の自由度のバランスだね」と締めくくった。
この会話は、部品選びの第一歩として“何を作りたいのか”を明確にする重要さを教えてくれた。今後のプロジェクトでも、あなたがIGBTとIPMの違いを正しく理解して選択できれば、設計の失敗はぐっと減るはずだ。
前の記事: « ipmとppmの違いを完全解説!基本から用途別の使い分けまで





















