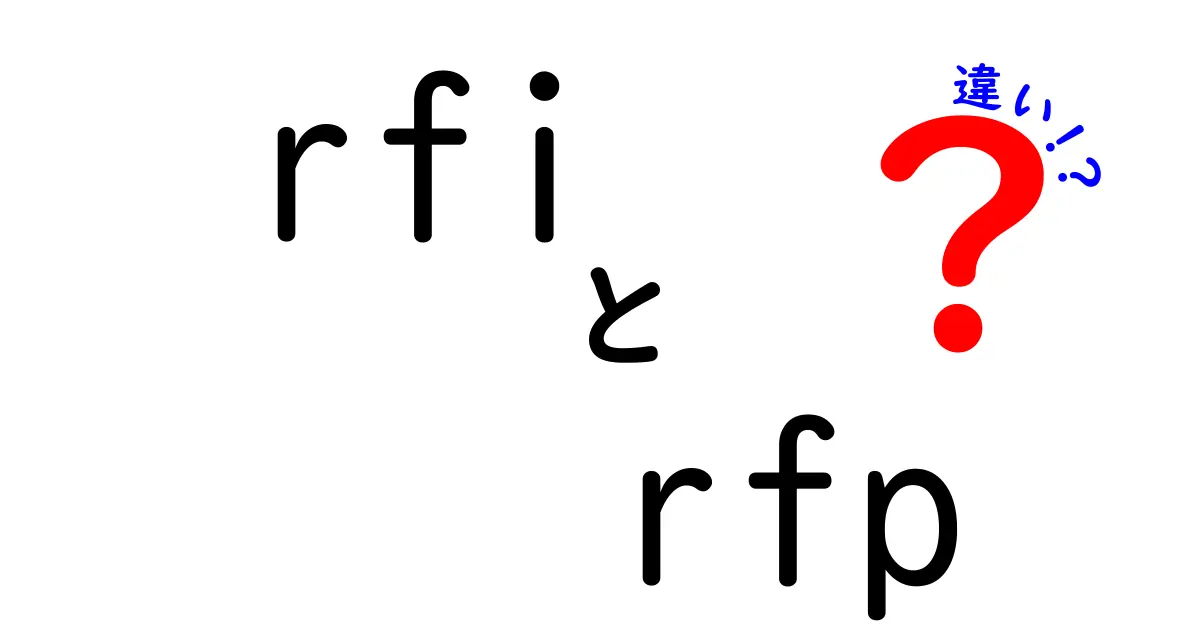

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
RFIとRFPの違いを正しく理解するための基礎知識
RFI(Request for Information)とRFP(Request for Proposal)は、ビジネスの調達プロセスで使われる重要な文書です。初めてこの2つに触れる人にとっては、似ているように見えるかもしれませんが、狙い・使い方・得られる情報が大きく異なります。RFIは情報収集のための文書で、どのような製品やサービスが市場にあるのかを広く浅く集めることを目的とします。これに対してRFPは、具体的な提案を求め、条件・価格・納期・実績などの詳細な提案を受け取り、比較検討するための文書です。要は、RFIは“出発点の情報収集”、RFPは“実際の提案を受け取って選ぶための依頼書”と覚えておくと理解が早いです。
この違いを正しく押さえておくと、後の進行がスムーズになります。情報が整理されていない状態でRFPを出してしまうと、要件のズレや評価の混乱が生じ、案件が長引く原因となることがあります。したがって、RFIは市場の現状を知るための道具、RFPは決定的な提案を受けて比較検討するための道具と認識するのが最も現実的です。
この章を読んでおくと、次の章で具体的な使い分けのコツや実務の進め方につながります。
RFIの定義と役割
RFIは情報収集の段階で用意します。社内の要件がまだ固まっていない時、ベンダーが提供する製品群やサービスの現行仕様、標準機能、実績、サポート体制、導入の際の一般的な注意点などを広く集めます。回答は市場の現状を把握するのが目的なので、提出形式は自由度が高いことが多く、定められた形式に縛られず、自由回答や候補となるソリューションのカテゴリを列挙する形もあります。RFIの成果物としては、要件の候補リスト、重要度の整理、実現性の可視化などが挙げられます。
この段階では、情報収集が目的であることを忘れず、過度に厳格な評価を避け、広い視点で市場を見渡すことが大切です。
RFPの定義と役割
RFPは、RFIの結果を踏まえ、実際の提案を比較検討するための正式な依頼書です。要件を具体化したうえで、価格、納期、サポート、契約条件、導入計画、実績、リスク分析などをベンダーに明確に回答してもらいます。回答形式は厳密に指定されることが多く、表形式の仕様書、技術要件、サービスレベル、評価基準、審査プロセス、提出期限などを事前に設定します。RFPの作成時には、社内の関係者と要件を確定させ、評価基準を定量的に設定することが重要です。結果として、複数のベンダーからの提案を比較し、総合的に最適解を選ぶための根拠を作ります。
RFPは単なる価格比較ではなく、実際の解決策の妥当性・実現性・コストパフォーマンスを総合的に評価する段階です。現場員が協力して、仕様と納期の整合性、サポート体制、導入後の運用計画までを検証することで、ミスの少ない契約判断を行えるようになります。
RFIとRFPの使い分けと実務例
現場での実務例として、まず新しいソフトウェアを検討する場合はRFIで市場の動向と候補を洗い出します。企業の予算規模や導入時期がまだ不確定なケースでは、RFIを使うことで候補を絞り込みつつ現実的な選択肢を把握します。次に要件が固まった段階でRFPを出して、具体的な提案と見積を受け取り、比較検討します。RFPでは、機能の適合性、実装の難易度、移行のリスク、サポート費用、総計のコストなどを厳しく評価します。IT以外の購買にもRFIとRFPは応用でき、公共調達や企業間の長期契約にも活用されます。使い分けのコツは、要件の確定度と決裁のタイミングです。要件が変わる可能性が高い場合はRFIの比重を高くしますし、社内の意思決定が速い場合はRFPの提出と評価を早めるべきです。最善の結果を得るには、段階的な進行と関係者の合意形成が欠かせません。
このように、RFIとRFPは協力して案件を前に進める力になる道具です。RFIで市場と要件の“地図”を描き、RFPでその地図を元に具体的な提案と契約条件を固めていくのです。最終的には、関係者全員が納得できる仕様とコストのバランスを見つけ、リスクを最小限に抑えた契約へと結びつけます。企業ごとに事情は異なりますが、基本的な流れと考え方を押さえておくと、初動の迷いが減り、成果の出る意思決定が可能になります。
私が友人とカフェでRFIについて雑談しているときのこと。彼は『RFIって情報を集めるだけでしょ?結局何が変わるの?』と尋ねた。私はこう答えた。RFIは市場の現状を描く地図みたいなもの。どんな機能があるか、どう導入できそうか、実績はどれくらいかを広く集めておくと、次のRFPで『本当に必要な要件は何か』を正しく決める力になる。さらに、ベンダーの違いを比較する際にもRFIの回答を基に「Yes/No」を早く判断できる。話は続き、要件が固まるたびにRFPに移行するのが理想だと気づいた。





















