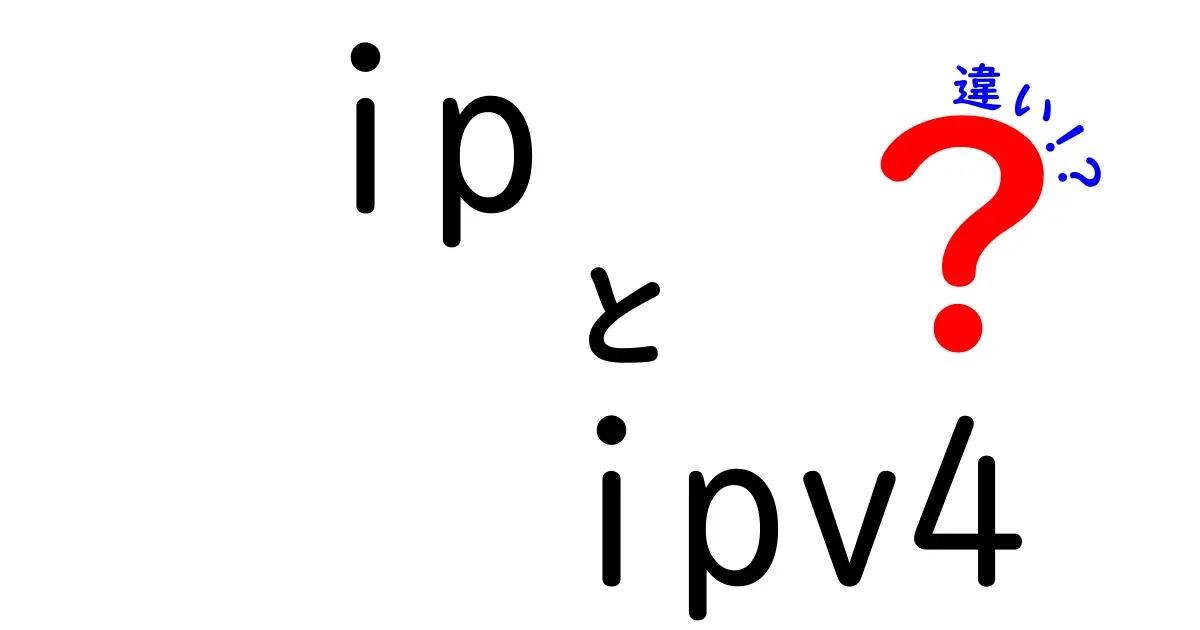

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
IPとIPv4の違いを理解するための基本ガイド
まず前提として覚えておきたいのは、IPという言葉は“インターネット上で機器を識別するための番号の取り決めの総称”という意味の総称語です。IPv4はその取り決めのバージョンのひとつで、数字の組み合わせで表現されます。日常生活で言えば住所のような役割を持ち、あなたのパソコンやスマホがインターネットに接続するときに世界中で一意の場所を示す手がかりになります。ところが現場では“IP”という言葉を使うときに2つの意味が混ざってしまいがちで、1つは“機器を識別するための番号そのもの”という抽象的な意味、もう1つは“その番号の使い方・決まり事”という実務的な意味です。そこでこのブログでは、特に初心者の人がつまずきやすい以下のポイントをしっかり押さえます。IPとIPv4の違いを理解するコツは、まず概念の範囲を分けて考えること、次に具体的な例と日常の感覚に置き換えること、そしてIPv4が現在どのくらい現場で使われているかを知ることです。
この3点を意識して読むと、IPという大きな世界の中でIPv4がどんな役割を果たしているのかが見えてきます。なお、IPv6という後続の規格が存在することも併せて覚えておくと、さらに理解が深まります。
本記事は中学生にも読みやすい言葉と、難しい専門用語を必要最低限に絞る工夫をしています。文章の長さよりも“伝える内容の正確さ”を優先し、図や表がなくても伝わるよう、段落と見出しの意味をはっきりさせました。
IPv4とはそもそも何か
IPv4というのはIPの中の一つの規格です。IPv4は四つの数値(0〜255)をドットで区切って表現します。例として192.168.0.1のような形です。この四つの数字を使って、コンピューターが『ここにいるよ』と示します。この規格が作られた頃は、インターネットに接続する機器の数は今ほど多くなかったため、32ビットの住所空間で十分でした。しかし時がたつにつれて接続機器が急増し、IPv4の枠が足りなくなる問題が起きました。その結果、NAT(ネットワークアドレス変換)という仕組みを使って1つの公的なアドレスを複数の内部機器で使う方法が広まりました。つまりIPv4は「現在も広く使われているが、限界がある規格」という二面性を持っています。
この点を覚えておくと、なぜIPv6へ移行する動きが出たのかが理解できます。IPv4の良さはシンプルで覚えやすい点、手元の機器や家庭のネットワークで実感しやすい点です。一方で問題点は「アドレスの在庫が少ないこと」「アドレスの翻訳が必要になる場合があること」です。これらを踏まえると、IPv4の役割と限界が自然に理解できます。
IPとIPv4の違いを日常生活に置き換えると
日常生活の例え話を使うと、IPは部屋の住所全般、IPv4はその部屋に割り当てられた具体的な“番地表現”の方法と考えると分かりやすいです。部屋番号がIPv4の個別番号だとすると、部屋がたくさんあるビル全体を包むのがIPの概念です。私たちがネットに接続するたびに、まず住所(IP)が決まり、その住所の下の部屋番号(IPv4の番号)が動的に割り当てられたり変わったりします。家の中のLAN内での接続は、別の仕組みで同じ家の中の機器同士が通信できるように設計されています。つまり、IPという大きな設計思想と、IPv4の具体的な番号表現は別の次元の話ですが、実生活に置き換えると理解が進みやすいのです。
実務での場面と具体例
学校や家庭、企業のネットワークでIPv4がどう使われているかを現場の視点で見てみましょう。家庭のルーターは通常、内部LANの機器にIPv4アドレスを割り当て、外部には1つのグローバルアドレスを使います。スマホやパソコンがネットに接続する際、ルーターがDHCPという仕組みで自動的にアドレスを与えます。この動作は“IPの世界がとても動的に動く”ことを示しています。
また、企業や学校のネットワークでは、NATやファイアウォール、VPNといった技術がIPv4の上で動作します。これにより、内部のアドレス空間を外部の世界と適切に切り分け、セキュリティを保ちながら通信を実現します。IPv4は日常の“ネットワークの現場”でいまだに主役の座を占めており、私たちの通信の多くがこの規格の枠組みの中で成立しています。表や図がなくても、接続の基本ルールが分かればネットワークの仕組みを理解するヒントになります。
今日はIPv4について友達と雑談するように話します。IPv4は四つの数字を点で区切って表す“部屋番号のような番号”の仕組みで、私たちの機器がインターネットにつながるときに使われます。昔はこの四つの数字だけで十分だったけれど、今は接続する機器が増えたので、番号の数が足りなくなる問題が出てきました。そこで家庭ではNATという工夫を使って、少ない公的アドレスをたくさんの機器で共有します。だからIPv4は“便利だけど限界がある”規格なんだよ、という話を友だちと話すと理解が深まるんだ。





















