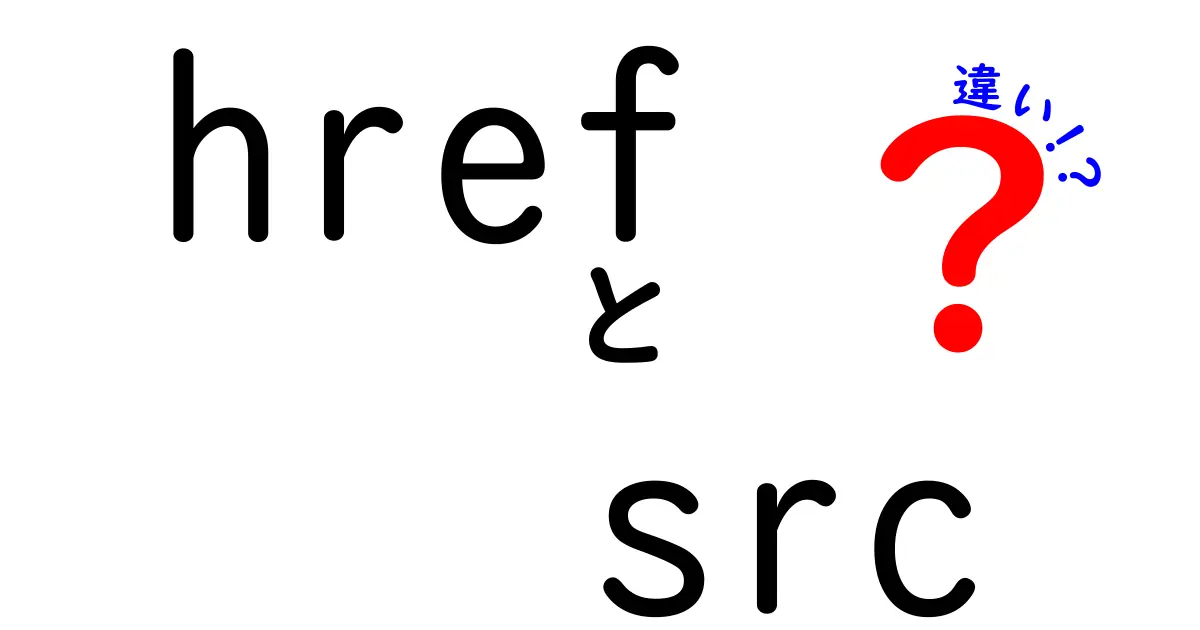

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
hrefとsrcの違いを理解する基本
この節では href と src の基本的な役割を、実務で使うイメージとともに解説します。href は主にリンク先の URL を指し示す属性です。リンクをクリックするとブラウザは新しいページへ移動したり、リソースを取得して表示を変えたりします。一方、src は埋め込む資源の場所を指し示します。たとえば画像、動画、外部の JavaScript や CSS ファイルの読み込みにも使われます。これらは同じように URL を指定しますが、目的が違います。
実務の場面を想像すると、次のような場面があります。href はリンク先を指す URL であり、ユーザーがクリックしたときに移動先が決まります。
その代わり、src は表示する資源そのものの場所を指すため、ページの中に画像や動画を出現させたい場合に使います。
例えば次のような表現を考えてください。<strong>href</strong> の使い方は Aタグ相当の動作を意識しますが、ここでは実際のタグを使わず説明します。<a href='https://example.com'>例のサイト</a> はリンク先を指し、<img src='https://example.com/logo.png' alt='ロゴ'> は資源を表示します。
このように href は移動先を指すのに対し、src は表示資源の場所を指すという違いを覚えると混乱を避けられます。
補足: 読み込みの仕組みを理解すると、パフォーマンスの工夫につながります。例えばページ読み込み時に必要なリソースだけを先に読み込み、遅延読み込みの活用やファイルサイズの最適化を意識します。
さらに href の場合はターゲット先の挙動や rel 属性の組み合わせ、src の場合はクロスサイトのセキュリティやオリジン制限などを意識することが重要です。
hrefとsrcを使い分ける実践テクニック
実務での使い分けは、まず目的を明確にすることから始まります。リンクは情報の導線を作る道具であり、閲覧者が次に何をするかを決めます。説明的なリンクテキストを使い、リンク先が外部か内部かを混同させないようにしましょう。画像や動画などの資源は src で読み込むことでページの視覚的な体験を作り出します。遅延読み込みや適切なサイズ設定を行うと、読み込み時間を短縮できます。
アクセシビリティと SEO の観点からも使い方を整えることが重要です。リンクには意味のあるテキストをつけ、画像には必ず代替テキストを用意します。外部資源の読み込みはセキュリティ上の考慮も必要です。たとえば外部リンクには rel 属性を追加し、スクリプトの読み込みには非同期・遅延の設定を検討します。
内部的な実装イメージとして、使い分けの要点を整理すると分かりやすくなります。 href は主にナビゲーション用、src は表示資源用、外部読み込みはパフォーマンスとセキュリティを意識する、アクセシビリティと SEO を意識したリンク設計を心がける、などの指針を覚えておくとよいです。
- href は主にナビゲーション用
- src は表示する資源用
- 外部読み込みはパフォーマンスとセキュリティを意識する
- アクセシビリティと SEO を意識したリンク設計を行う
この考え方を実際のコードに落とすと、リンクと資源の役割がはっきり分かります。例えば記事本文中のリンク先導線とページ内表示資源が混在していると、読み手の体験が分かりづらくなります。適切に分けて書くことで readability が上がり、後から修正するときのミスも減ります。
今日は href の話題を少し掘り下げた小ネタです。リンクを作るとき、私たちは見た目の文字列だけでなく先に何が起こるかを想像して設計します。説明的なリンクテキストは検索エンジンにも友好的で、スクリーンリーダーを使う人にも伝わりやすいです。私がよく心がけているのは、リンク先が何かを一言で伝える言葉を選ぶことと、リンク周辺の文脈を整えること。これだけでクリック率が少し変わる実感があります。
次の記事: tdとthの違いを徹底解説!HTML表の正しい使い分けガイド »





















