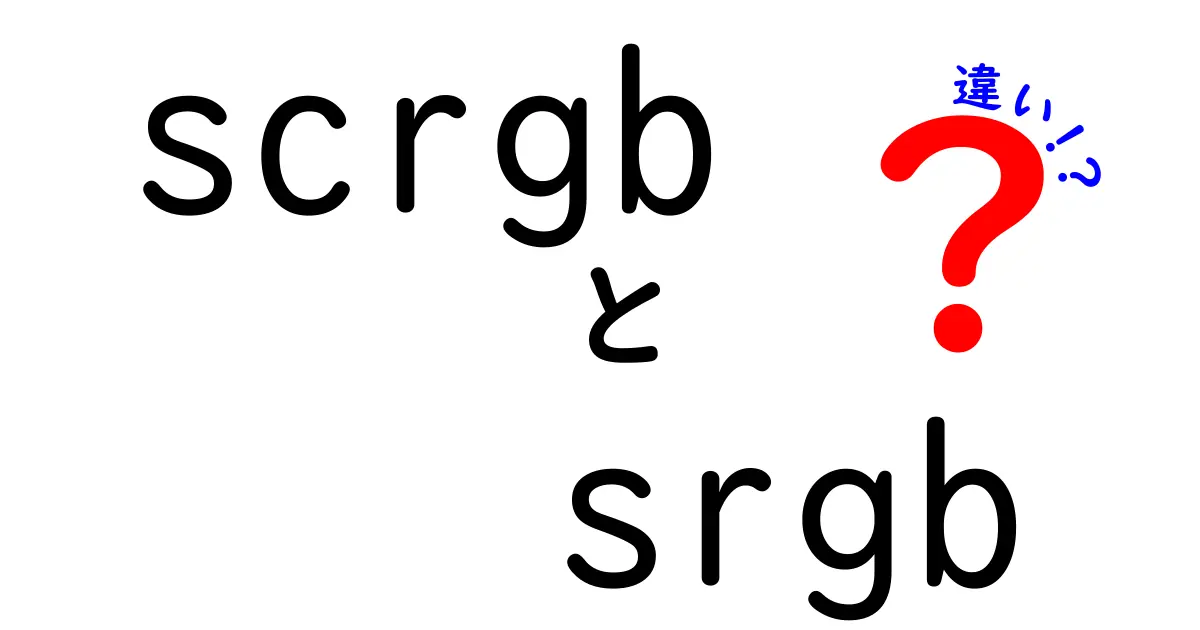

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
scrgbとsrgbの違いを基本からわかりやすく解説
sRGBとは何か、scRGBとは何か? まず大事なのは「ガンマ」と「色域」と「適用シーン」の三つです。
まずsRGBはウェブや多くの画像処理ソフトの標準カラー空間として広く使われており、これはガンマ補正と呼ばれる仕組みを使って、明るさを人間の視覚に合わせて非線形に表現します。つまり、暗い部分を濃く、明るい部分を少し薄くして表示します。こうすることで、私たちは同じ画像をモニターやスマホ、プリントでほぼ同じ色に見えやすく感じるのです。
一方、scRGBはこのsRGBより後に生まれた、より広い色の取り扱いを可能にする仕組みです。scRGBは「線形光」の表現として設計され、色の値を直线的に扱います。線形光とは、光の強さをそのまま数値で表す感覚に近いイメージです。これによって、物理的な光の加算・減算の計算が、非線形のガンマ補正を前提としたときより正確に行えます。さらに、scRGBはsRGBよりも広い色域を扱えるように作られており、暗い場所から明るい場所までの連続した明度の再現性が向上します。こうした特徴の違いは、実際に写真を編集したり、HRD対応の映像を扱うときに顕著に現れます。
実務的には、どの場面でどちらを使うべきかを知ることが重要です。ウェブ上で表示する写真や動画、あるいはプリントの色を他の人と正確に共有したいときにはsRGBが安定しています。ほとんどのブラウザやスマホはsRGBを前提として色を解釈します。もし別の色空間で保存しても、埋め込みICCプロファイルが正しく使われていなければ、表示が大きく崩れることがあります。そこで、ウェブ用の制作物はsRGBに変換して保存・埋込みを行うのが基本です。特にオンラインのポートフォリオやSNSにアップロードする場合は、sRGBでのエンコードが堅実です。
一方で、プロの映像編集やHDRの制作現場ではscRGBを選択肢に入れることがあります。scRGBは広い色域と線形表現の組み合わせにより、カラーグレーディングや色の補正を行いやすくします。たとえば、複数のカメラで撮影した素材を統合する場合、scRGBの方が色の整合性を取りやすい場面があります。ただし、日常の閲覧環境はさまざまで、scRGBは必ずしも全ての機器で同じように表示されるわけではありません。最終的には色管理の設定とICCプロファイルの適用が鍵となります。
そのため、実務での基本ルールとしては「作業段階を分けて考える」ことが大切です。写真の編集はscRGBや別の広色域に対応したワークフローで進めつつ、完成時にはsRGBへ変換して公開する、という二段階の戦略を取るのが現実的です。さらに、ドキュメントや作品の配布先が決まっている場合は、最初からその環境に合わせた設定を選ぶと色のギャップを減らせます。
最後に、ICCプロファイルの重要性を強調したい点をいくつか挙げます。もしあなたが作品を長く保存したいなら、色空間とプロファイルの情報を明示しておくことが大切です。これにより、数年後の閲覧環境が変わっても、元の意図に近い色を再現しやすくなります。色の話は難しく感じるかもしれませんが、基本を覚えておけば、写真・動画の質を大きく左右する決定的な差を理解できるようになります。
覚えておくべきポイント
- sRGBはウェブの標準で、ほとんどの機器がこれを前提として表示します。
- scRGBは広い色域と線形表現を使い、HDR的な編集に向きますが表示環境に依存します。
- 編集段階と公開段階を分けると色のずれを減らせます。
- ICCプロファイルの埋め込みは色の再現性を保つために重要です。
今日はスマホで写真を友だちに送るとき、同じ写真でも端末ごとに色が違って見える現象に気づきました。原因はsRGBとscRGBの違いと、カラー管理の有無です。私は友達の端末で見せたい色味を想定して最終出力はsRGBに変換して保存します。編集時にはscRGBの広い色域を活用して微妙な階調を鮮明に整え、公開時にはICCプロファイルを埋め込み、さまざまな端末で同じ見え方になるよう心がけています。カラーは難しそうですが、基本を押さえれば日常的な写真づくりにも大きな差が出ます。





















