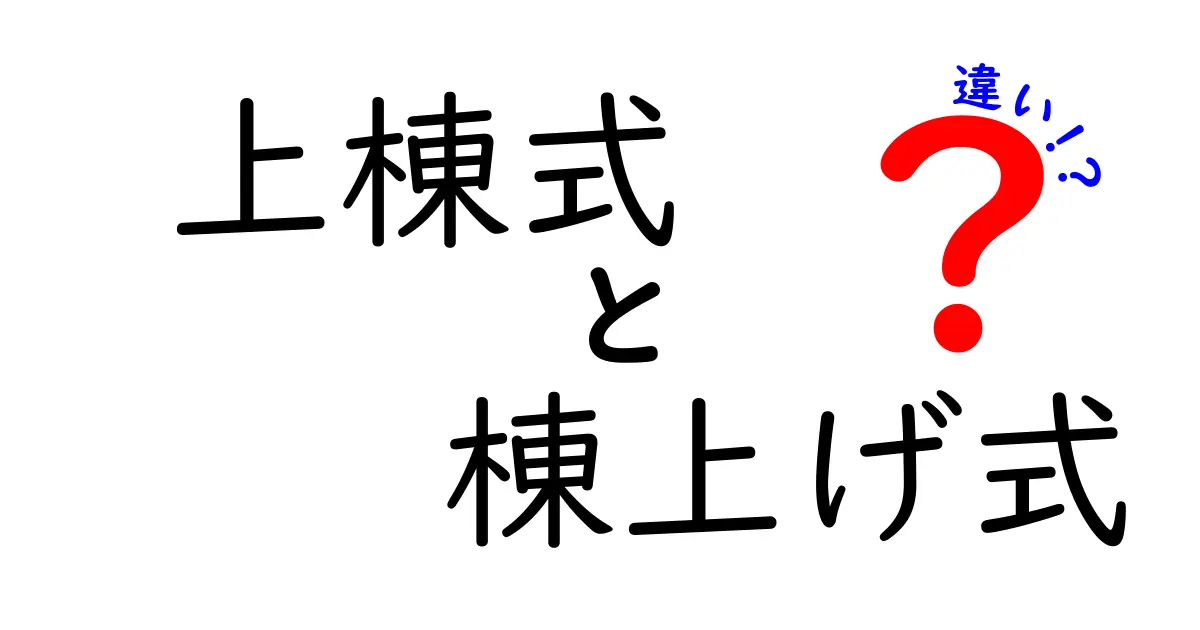

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
上棟式と棟上げ式の基本的な違い
「上棟式(じょうとうしき)」と「棟上げ式(むねあげしき)」は、どちらも家を建てる時に行う伝統的な行事ですが、実はほとんど同じ意味を持っています。
上棟式は、建築中の家の一番高い部分にあたる「棟木(むなぎ)」を上げる時に安全や無事を祈って行う儀式のことです。
棟上げ式は、この儀式の呼び方の一つで、地域や人によって言い方が違います。
つまり、上棟式も棟上げ式も「家の骨組みが完成したことを祝う儀式」で、どちらか一方だけを指すのではなく、ほぼ同じ行事のことを意味しています。
上棟式・棟上げ式の由来と歴史
この行事は昔から日本の住宅建築に根付いていて、家を建てる工程の中でも重要な節目として大切にされてきました。
「棟」とは家の屋根の一番高い横棒の部分を指し、これを上げることで建物が形作られていくことを示しています。
「上棟式」という名前は、まさにその「棟が上がる」ことを祝う式という意味です。一方で、「棟上げ式」という呼び方は言葉としては同じ意味ですが、関東圏など特定の地域では特にこの言い方を使うことが多いです。
元々は神道の考え方と結びつき、建物が無事に完成し住む人に幸せをもたらすようにという願いが込められています。
実際の上棟式・棟上げ式の流れ
では、実際にどんなことが行われるのかを簡単に説明します。建物の骨組みが完成した日、一緒に働いてくれた大工さんや関係者が集まって行われます。
一般的な流れは以下の通りです。
- 棟木を最後に設置し、屋根の骨組みが完成する
- 神様にお供え物(米や塩、酒など)を捧げて、工事の安全や家の繁栄を祈る
- 手締め(みんなで手を叩いてお祝いの合図をする)を行う
- 参加者で飲食を楽しみながら感謝の気持ちを表す
以下に、上棟式と棟上げ式の違いを簡単に表にまとめました。
まとめ
上棟式と棟上げ式は同じ行事の違う呼び方であり、地域や言葉の使い方によって変わります。
どちらも建築中の家の安全と完成を祈る大切な儀式です。
もし家を建てる時にこれらの言葉を耳にしたら、同じ行事を指していると理解して大丈夫です。
昔の文化を感じながら、無事に家が完成することを願う心を大事にしたいですね。
「棟木(むなぎ)」という言葉、聞いたことありますか?家の屋根のいちばん高い部分にある太い木のことです。これを上げるのが上棟式や棟上げ式の大事な瞬間なんですね。実はこの棟木には「家の骨組みの頂点」という意味があって、建てる人みんながここまで来た!と達成感を味わうポイントでもあります。だから昔から安全や繁栄も願って祈るんですよ。ちょっとした木一つにも日本の建築文化の奥深さが感じられますね。
次の記事: 知らないと損する!上棟式と建前の違いをわかりやすく解説 »





















