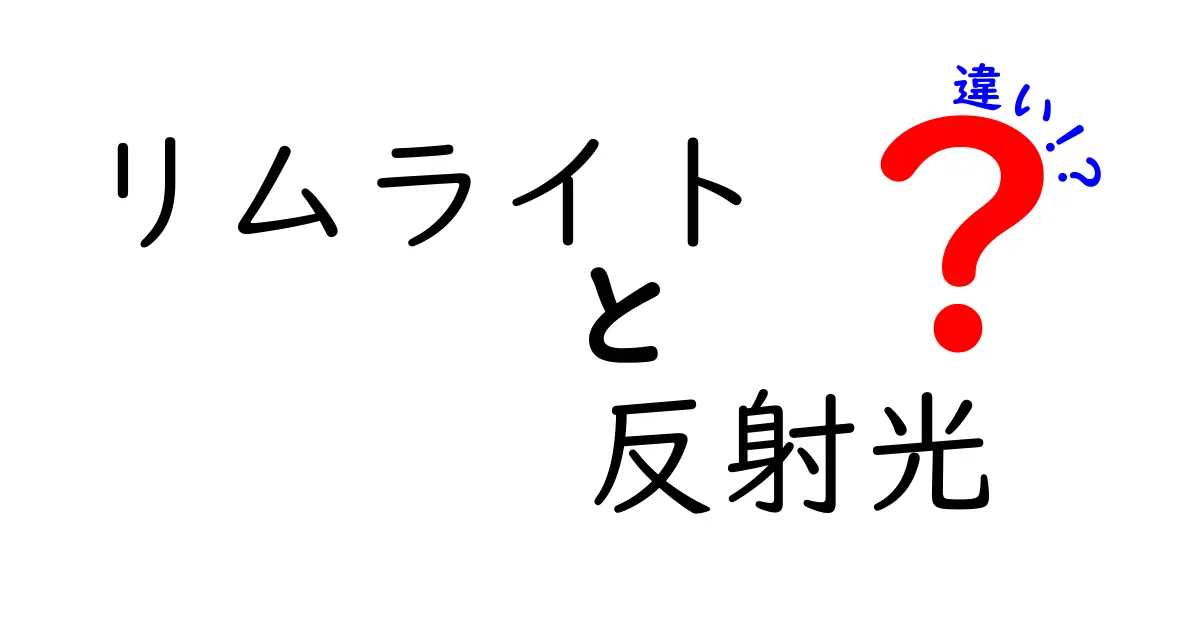

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
リムライトと反射光の基本的な違い
リムライトとは何かを最初に押さえましょう。リムライトは被写体の後ろや横から細い光を当て、被写体の輪郭に細い「縁取り」を作ります。この縁取りは被写体を背景から際立たせ、立体感を生み出します。前方を直接照らすわけではないので、肌を明るく均一にするには向きません。リムライトの光は通常、角度を変えると光の太さや色味が変わり、髪の毛のハイライトや肩の縁、耳の輪郭など意図した場所に微妙なラインを作ることができます。反対に反射光は、壁や床、天井などの表面に反射して広がる光のことを指します。反射光は陰影を柔らかくし、顔全体を自然に明るく見せるのに向いています。このふわっとした質感は屋内の撮影で特に役立ち、露出を大きく変えずに立体感を得る手助けをしてくれます。リムライトと反射光を比べると、前者は“輪郭の強調”と“ドラマ性の演出”に長け、後者は“空間の広がり”と“顔の陰影の自然さ”を作る力が強いと覚えておくと良いでしょう。
実際の画づくりでは、両方を組み合わせて使う場面が多いです。強いリムライトだけだと被写体が二次元的に見えがちなので、反射光で全体を落ち着かせてバランスを取ると自然で美しい写真になります。
リムライトと反射光の使い分けと作り方のコツ
写真や映像で活用するコツを具体的に見ていきましょう。
まずは光源の位置を決めます。リムライトは被写体の後ろまたは横45度前後のあたりに置くのが基本です。角度が浅いほど縁が細く長く見え、角度を深くすると縁は広くなる傾向があります。環境光や背景の色、被写体の髪の色によって光の色味を調整しましょう。
反射光は壁や天井の性質に左右されます。白い部屋なら柔らかく広がり、暗い壁なら暗い影が広がります。反射光の強さは、リムライトの強さとバランスを取りながら決めましょう。
実践では、3カメラ体制のように主光、リムライト、反射光を組み合わせると安定感が出ます。主光で脸の基本の形を作り、リムライトで輪郭を際立たせ、反射光で陰影をなだらかに整えるのが基本の手順です。もちろん機材はLEDなら色温度を揃える、ストロボなら発光量を同調させるなど、基本的な設定が求められます。
次の表はリムライトと反射光のポイントを分かりやすく整理したものです。
実践例: ポートレート・商品写真・屋内の場面別ポイント
ポートレートでは、リムライトは髪の毛のハイライトを作り、反射光で顔の陰影を和らげる組み合わせが良いです。肌の質感を壊さず、立体感を保つには陰影の範囲と強さをコントロールします。商品写真では、リムライトを小さめに設定して輪郭だけを強調し、反射光で製品の表面の細かな質感を出します。屋内の場面では壁の色に合わせて反射光の色味を微調整すると写真の雰囲気が大きく変わります。
友達と写真部の合宿で、リムライトと反射光の話題になりました。私は最初、どちらか一方を強く当てればいいと思っていましたが、先輩は違いを一言でこう言いました。リムライトは輪郭を描くペン、反射光は影を塗る絵の具。結局、良い写真にはこの二つを上手に混ぜることが大切だという結論に至りました。この記事を読んでいる君も、まずは自分の使い方を一度紙に描いてみてほしいです。部活の仲間と一緒に実践すれば、きっと写真の印象が劇的に変わります。
前の記事: « 吹き替え字幕と日本語字幕の違いを徹底解説!どっちを選ぶべき?





















