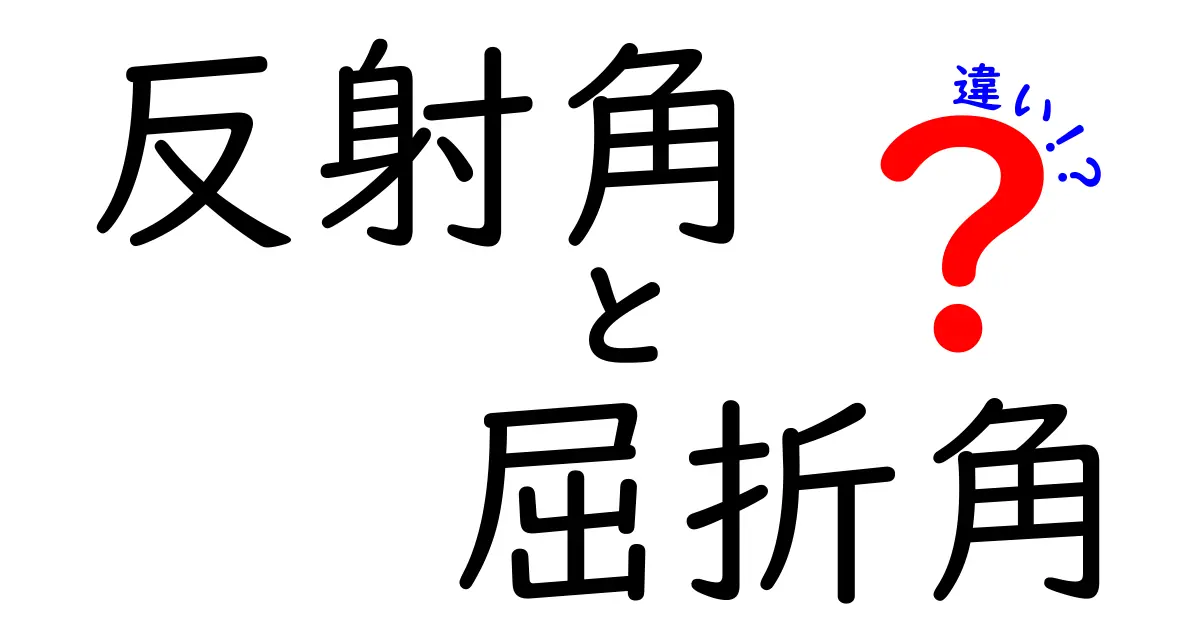

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに: 反射角と屈折角の基本と身近な例
光が境界にぶつかると、どちらの方向へ進むかは角度とその質によって決まります。まず反射角とは、光が境界面で跳ね返るときの角度のことです。境界線を法線と呼ぶ垂直な線を基準に、入射角という光が入ってくる角度と反射角は関係します。実際には、鏡を見たときの自分の姿が“そのまま”映るのは、反射角が入射角とほぼ等しくなる特徴があるからです。
反射は、物質の違いにはあまり左右されず、光の進む方向をのみ返す現象です。続いて屈折角は、光が別の物質へ進むときに起こる“角度の変化”のことを指します。光の速度が物質ごとに違うため、境界を越えると進む角度が変わるのです。水から空気へ光が出ると、屈折角は入射角より大きくなることが多いのがその典型です。
私たちが日常で目にするプリズムの虹や、水中の魚が水面越しに見える景色は、屈折角の変化の美しさを教えてくれます。こうした現象を理解するには、法線という基準線を使って、入射角と反射角・屈折角の関係を整理するのがコツです。
反射角と屈折角の違いを日常で理解するコツ
ここからは、日常の場面を使って違いをより実感できるコツを紹介します。
最初のコツは、鏡を使って実験してみることです。光を鏡の前方に当て、鏡の表面を“法線”に合わせて観察すると、反射角の法則が自然と理解できます。
次のコツは、透明な媒質を切り替えながら観察することです。水/空気/ガラスの境界で、光が進む角度がどう変わるかを比較すると、屈折角の感覚がぐんと掴みやすいです。
日常の例としては、コップの水の中の棒が折れて見える現象や、海岸の波が水面を越えるときの向きの変化、プリズムを使って虹を作るときの光の道筋などがあります。こうした現象を観察する際には、強調したい点をメモしておくと後で整理しやすくなります。
最後に、入射角と屈折角の関係を自分なりに書き出してみると、理解が深まります。
koneta: 友達と海で見た光のふしぎ話をきっかけに、屈折角の話題で盛り上がりました。水の中の棒が水面を越えるときにどう見えるかを観察し、入射角が大きいほど屈折角も大きくなるという直感を得ました。先生の説明は、屈折は光の速さの違いが原因で起こる道の曲がり方だという点を強調します。私たちはこの小さな現象から、科学は身の回りにたくさんあることを学び、興味を持ち続けることの大切さを感じました。





















