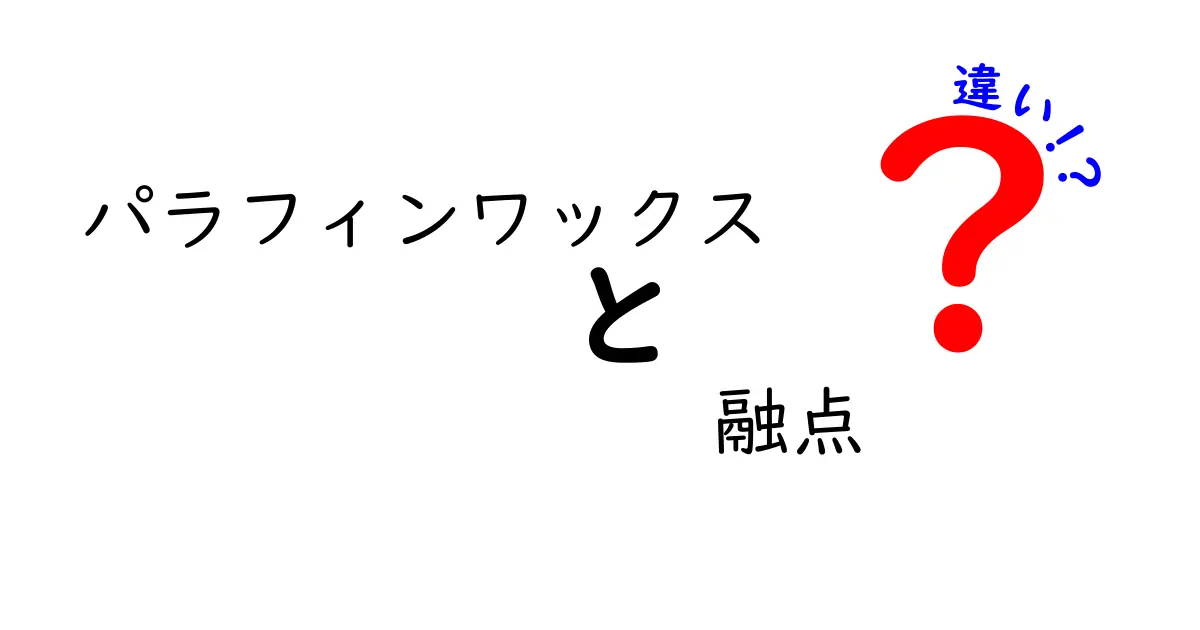

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:パラフィンワックスの融点の基本
パラフィンワックスは、固体のろうの一種で、室温では固体ですが、温度を上げると徐々に柔らかくなり、やがて液体になる性質を持っています。特に「融点」は製品を選ぶときの要点です。融点とは何か、どう決まるのかを知ると、日用品として使う場合や工業用途として選ぶときに迷いにくくなります。
この融点の話は、単純な温度の話だけではなく、原料の組成、添加物、加工方法、製品の使用環境、保管条件など、さまざまな要素と関係しています。
例えば、キャンドルを作るときと、潤滑剤やシール材として使うときでは、求められる融点が異なります。
本記事では、融点の違いがどこから生まれるのか、どのような用途でどの融点が適しているのか、そして実際の選び方のコツを、中学生にも分かる言葉で丁寧に解説します。
読み進めると、パラフィンワックスの世界が「温度と用途の関係」という形で整理できてくるはずです。
融点の違いを生む要素と具体的な用途の関係
パラフィンワックスの融点が異なる背景には、原料の性質と製造工程の違いがあります。純度の高い長鎖炭化水素だけを主成分とするクリーンなパラフィンは、一般に融点が高めに出やすいです。これに比べ、石油の残留成分や微細な不純物を含む場合、結晶構造が乱れ、結果として若干融点が低くなることがあります。添加物の有無も大きな要因です。例えば、柔軟性を高めるためのオイル未使用の硬いタイプと、オイルを少量混ぜて滑らかさを出したタイプでは、同じおおよその重合度でも融点が異なることがあります。
また、製造時の冷却速度や結晶の成長のしかたも極めて重要です。冷却が急速だと結晶が細かく、融点が高く出やすい一方、ゆっくり冷却すると大きな結晶が育ちやすく、結果として融点が低めになることが多いです。こうした差は、製品の用途に直結します。例えば、冬場のキャンドルに使う場合は低めの融点の方が点灯しやすいのに対し、熱環境が高い場所では高めの融点が必要になる場面があります。
このように、融点の違いは単なる数字ではなく、原料、加工、環境条件の三つの要因が絡み合って決まるのです。
用途別に融点を選ぶ際は、実際の使用温度や耐久性、表面の安定性まで考慮することが大切です。
融点別の用途と選び方
用途別に融点をどう選ぶか、いくつかのポイントを整理します。
1) キャンドル作り:美観と点灯安定性を考え、60°C前後のタイプを選ぶと滴下や表面のムラが少なくなります。
2) 潤滑・防護膜用途:温度環境が高い場所では高融点タイプが向きます。
3) 食品接触の可能性がある場合は、食品級や医療グレードの融点のものを選ぶべきです。
4) 加工性:柔らかさが必要ならオイルを少し添加したタイプ、硬さが必要なら純度が高いタイプを選ぶと作業性が変わります。
以上の点を踏まえ、実測値の融点だけでなく、製品の規格書に記載された仕様を確認することが大切です。これにより、初期の失敗を避け、長期使用時の安定性も確保できます。
今日は友だちとLINEの雑談として、パラフィンワックスの融点について話してみた。融点は“物質が固体から液体へ変わる温度”という基本だけど、現場では原料の違い、添加物、冷却の仕方まで影響することを伝えると、みんな意外と納得してくれる。60°C前後の高融点タイプを選ぶ場面、46–50°Cの低融点タイプを選ぶ場面――それぞれの使い方と安全性の話が続き、結局は「用途に合わせて温度の目安を決めよう」という結論に落ち着く。
前の記事: « 個展と展覧会の違いを徹底解説:あなたの作品はどちらに出すべき?
次の記事: 個展と展覧会の違いを徹底解説:あなたの作品はどちらに出すべき? »





















