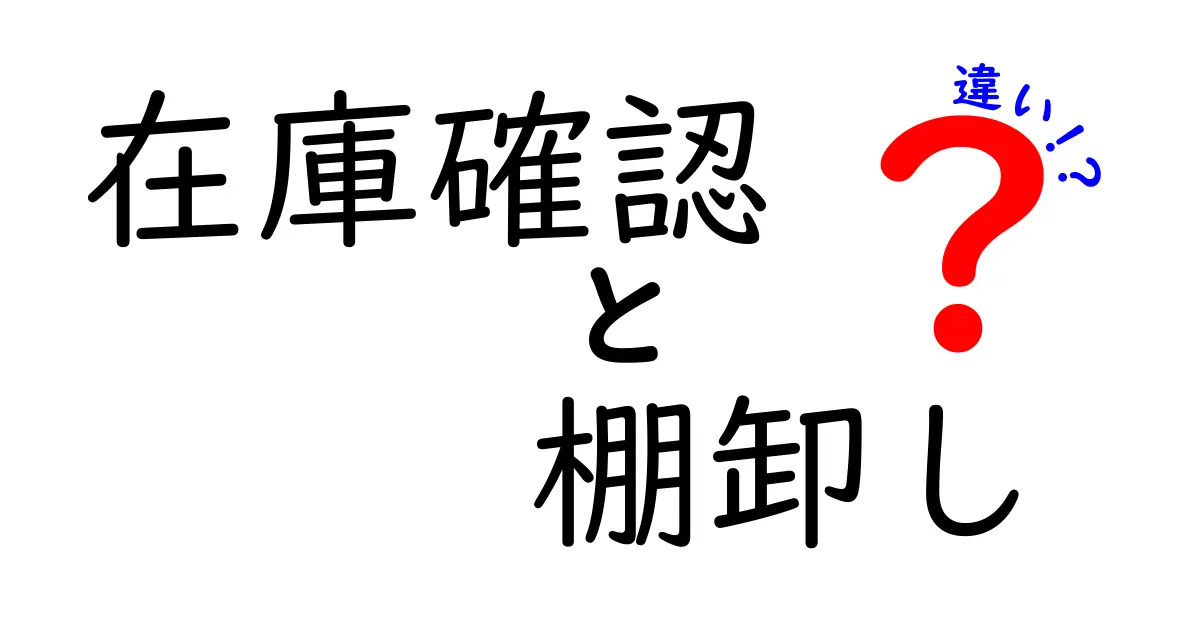

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
在庫確認と棚卸しの基本を押さえよう:違いをはっきりさせると現場が動く
まず覚えておきたいのは、在庫確認と棚卸しは同じ“在庫”を取り扱う作業ですが、目的とタイミングが違う点にあります。在庫管理の現場で使われる二つの言葉を正しく使い分けると、仕事の流れがスムーズになり、納期遅延や過剰在庫を減らすことができます。在庫確認とは、いま手元にある商品の数を把握する作業のことです。売上が入る前に出荷が可能かどうかを判断したり、欠品を未然に防ぐための補充計画を立てたりします。日次のルーティンとして行われることが多く、ERPやPOS、バーコード端末を使って在庫数をリアルタイムに表示する場合が多いです。しかし紙ベースの記録やExcelだけで管理しているケースもまだ見かけます。
この作業は“今ある量”を正確に把握することが目的で、現場の出荷効率と顧客対応のスピードを決定づけます。
棚卸しは、特定の日付を基準に実物を数え、記録と照合する作業です。財務報告の根拠になるほか、在庫評価の正確さを保つためにも重要で、ズレがあれば仕訳を修正します。棚卸しは日常の作業とは別枠で実施されることが多く、年次決算時に大きな影響を与えます。
この二つを正しく使い分けることが、現場の作業効率と経営の健全性を高める第一歩になります。
基本的な差を整理する
在庫確認と棚卸しの違いを、現場の手順と成果物の観点から詳しく整理します。
まずタイミングの差。在庫確認は日々の作業として、出荷指示や発注のタイミングに合わせて随時行われます。これに対して棚卸しは定期的に計画され、月次や四半期、年次の会計期間に合わせて実施します。次に対象の違い。在庫確認は通常の在庫として日常的に追跡するもので、限定された品目やカテゴリを対象にすることが多いです。一方、棚卸しは全在庫を対象にするケースが多く、廃棄品や過去の不良在庫、紛失や盗難の可能性まで含めて実物を数えます。方法の違い。在庫確認はバーコードやRFID、ERPの棚卸表などを用いて機能的な数を素早く取得します。棚卸しは現場の作業員が実物を手で数え、棚の配置を確認し、分布を正確に再現します。これらを混同すると、出荷ミスや財務上のズレの原因になります。そのため、手順の標準化とデータの統一、定期的な教育が重要です。最後に結果の取り扱い。在庫確認の結果は出荷計画や補充計画に直結しますが、棚卸しの結果は会計上の棚卸資産評価や在庫評価の基礎データとして使われ、仕訳の修正が伴うことがあります。現場はこの差を理解して、適切な頻度と正確さを保つことが求められます。
棚卸しについての雑談記事: 棚卸しは単なる数量合わせではなく、現場と会計をつなぐ“信号機”だと私は思う。新人の頃、棚卸しの場で上司が言った『現物と帳簿のズレを放置すると顧客対応にも財務にも悪影響が出る』という言葉が今も耳に残っている。だからこそ、棚卸しは準備が9割。棚の配置を整え、ラベルを見やすくし、バーコードの機能を再確認してから実施する。結果を共有するタイミングも大切で、遅れれば現場の混乱につながる。棚卸しは数字と現物の対話だと思えば、日々の在庫管理を楽しく、正確に進められるようになる。





















