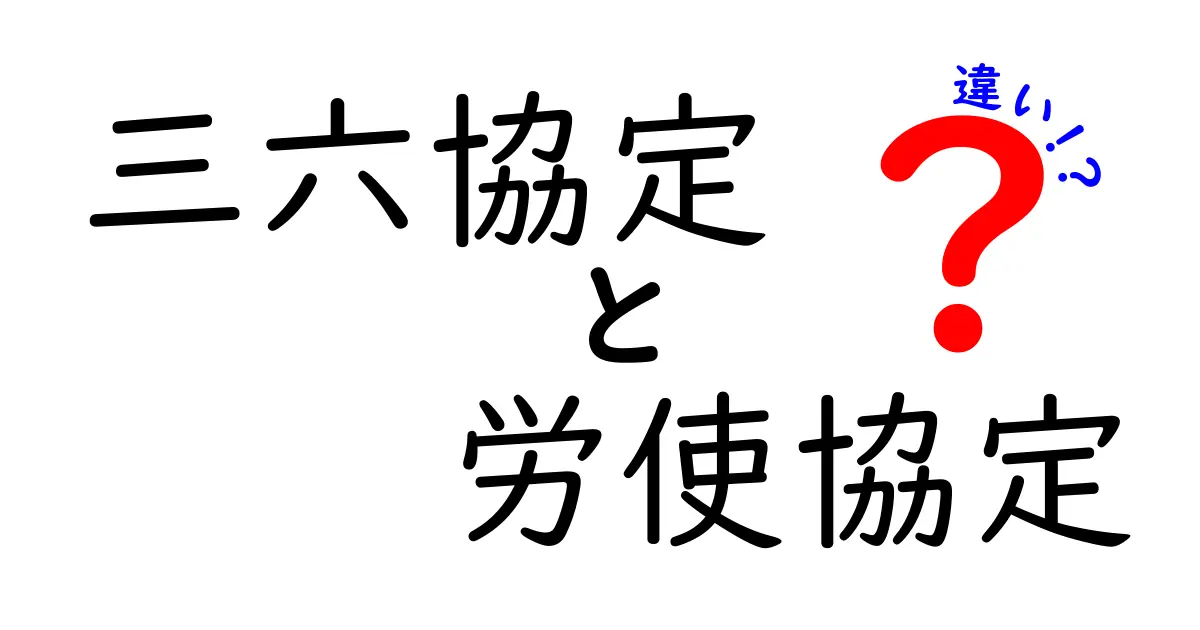

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:なぜこのテーマを学ぶのか
現代の日本の会社では、残業時間や労働条件をどう決めるかが重要な課題です。特に「三六協定」と「労使協定」という言葉は日常のニュースや就業規則でよく耳にしますが、似ているようで意味が違います。違いを正しく理解していないと、法を守るための手続きが遅れたり、思わぬトラブルにつながる可能性があります。この文章では、中学生にも伝わるやさしい言葉で、二つの協定の基本から、どのように使い分けるのか、そして現場での実務上の注意点までを丁寧に解説します。まずは「なぜ二つの協定が同じジャンルに見えつつ、別々の役割を持つのか」という疑問を解くところから始めましょう。長い文章を読んでもらうのは大変かもしれませんが、写真の説明を読む感覚で、要点をつかむ練習をしてみてください。
理解のコツは、三六協定が「時間外労働を認めるための条項」であり、労使協定は「労働条件全般を決めるルールの集まり」であると覚えることです。ここからは、具体的な定義、適用範囲、作成の手順、そして現場での注意点を順番に見ていきます。
三六協定とは?基本の理解
三六協定は、労働基準法の「時間外労働・休日労働を行うことができる条件」を定めるための正式な書面契約です。正式には“労働基準法第36条に基づく協定”と呼ばれ、企業が残業をさせる時には必ずこの協定を取り付けなければなりません。この協定は、労働者の過労を予防するための手続きとして、労使双方で同意した内容を、所轄の労働基準監督署に届出・提出する必要があります。三六協定の基本的な役割は、どの程度の時間外労働が認められるのか、どのくらいの休日出勤が許されるのかを、法の枠組みの中で決めることです。実務では、月の残業時間の上限、年の総時間、特別条項の有無といった要素を含むことが多く、企業ごとにこの協定の内容は異なります。
また、三六協定は必ず書面で行い、成立には労使の合意が必要です。ここでのポイントは「誰が書面を作成し、誰が署名するか」、そして「どのような条件で時間外労働が認められるか」を明確にすることです。
労使協定とは?何を決めるのか
労使協定は、労働条件、賃金、勤務形態、教育訓練、福利厚生、退職金制度など、労働者と雇用主の間で合意する様々なルールを指す総称です。この協定は必ずしも「時間外労働だけ」に限らず、広い範囲の職場ルールを規定します。ただし、現実の職場では、三六協定のように時間外労働を扱う項目が含まれる場合が多く、協定全体の中で個別の条項として「何時間まで働くか」「休憩はどうとるか」「休日出勤は認めるか」といった具体的な条件が定められることが一般的です。労使協定を作る際には、「誰が交渉の代表になるか」、「どの範囲の労働者が対象か」、「署名・届出の手続き」など、組織の構造と現場の実情を踏まえた設計が求められます。現場では、労働組合がある場合はそれが大きな交渉力となりますが、組合がない場合には、従業員の過半数を代表する者等を「代替的代表」につけるなどのルールがあります。
違いのポイント:どんな場面で使われるのか
三六協定と労使協定の違いを整理すると、まず目的が異なります。三六協定の目的は「時間外労働を法的に認める条件を定めること」であり、これは働く人の長時間労働を制度的に管理するための手続きです。次に、労使協定の目的は「広範な労働条件を決めること」や「組織の運用ルールを整えること」です。ここには賃金、休暇、教育訓練、福利厚生など、職場における多くの側面が含まれます。違いを具体的な場面で見ると、例えば「今月の残業は三六協定で認める範囲内か」「休日出勤は可能か」といった点は三六協定の領域です。一方で「新しい福利厚生を導入する」「給与テーブルを改定する」などは労使協定の領域です。
なお、三六協定は労使協定の一部や派生物として位置づけられることが多く、「三六協定を作る前提として労使協定の枠組みが存在することが多い」という現実もあります。この点で、混乱が生まれやすいのです。表に整理すると理解が深まります。
実務での注意点とまとめ
実務での注意点としては、まず手続きの遅延を避けることです。三六協定は必ず所轄の労働基準監督署へ届出を提出します。届出が遅れると、企業は法的なペナルティを受ける可能性があり、労働者の権利保護にも影響します。次に、協定の内容が現場の実態と乖離しないよう、適切なデータをもとに設定することが大切です。残業が固定化している職場では、月の実績と今後の見込みを踏まえ、現実的な上限を設定する必要があります。老若男女問わず、長時間労働は健康リスクにもつながるため、「適切な休息と健康管理を組み込んだ設計」が重要です。最後に、労使協定と三六協定が「互いの信頼の上に成り立つ関係」であることを忘れてはいけません。対話を重ね、透明性を保つことが、トラブル回避と生産性の向上につながります。
この章では実務におけるポイントをさらに整理します。
友達とカフェで雑談していたとき、三六協定と労使協定の話題になった。僕は『三六協定は、残業をさせてもいい条件を決める書面』だと理解したけど、友達は『それだけ?もっと広いの?』と尋ねた。僕は『そう、三六協定は“時間外労働を認めるための限定ルール”で、労使協定は“賃金や休暇、福利厚生など職場全体のルールを取り決める合意”なんだ』と説明してみた。二つは別物だけど、現場では三六協定が労使協定の一部として機能することが多い。もし本当に大切なのは「どうやって人の健康を守りつつ、仕事を回していくか」という点で、対話と透明性がカギになるんだ、と結論づけた。部活の顧問と部員の話し合いに例えると、協定の基本は「約束の内容を誰が作成し、誰が署名するか」という手続きの明確さと、現場の実態に合わせた現実的な枠組みを作ることだと理解した。
次の記事: 販売スタッフと販売員の違いを完全解説:意味・役割・使い分けのコツ »





















