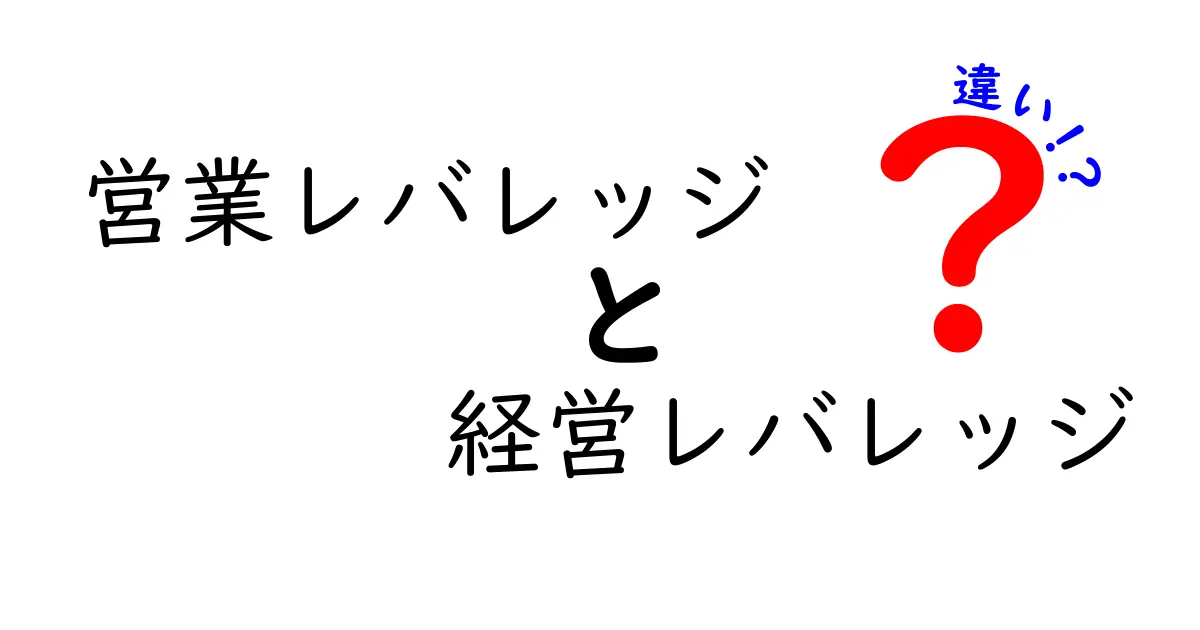

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
はじめに:レバレッジの基本と違いを理解する
レバレッジとは、同じ努力や資源でより大きな結果を出す仕組みのことを指します。ビジネスでは、営業レバレッジと経営レバレッジという二つの考え方がよく使われます。
営業レバレッジは、販売活動そのものの効率を高めて売上を増やす力のことです。電話やメール、商談の回数、セールスのパイプラインの質を高めることで、同じ人が同じ時間働いてもより多くの顧客を獲得できる状態を指します。
一方で経営レバレッジは、企業の固定費と変動費の構造に関わる概念です。固定費が高い企業は売上が少なくても黒字化が難しく、逆に固定費を適切に抑え、変動費を管理することで、売上が伸びるほど利益が加速する「てこの原理」が働きやすくなります。
この二つは密接に関係しながらも、指標の見方や改善の焦点が異なります。営業レバレッジは「どれだけ販売を増やせるか」という外部への働きかけ、経営レバレッジは「どうやって利益を効率良く生み出すか」という内部の仕組みづくりの話です。
経営の現場では、両者を同時に意識することが重要です。売上を増やす努力と、コスト構造の最適化を同時並行で進めると、短期間での利益改善だけでなく、長期的な成長基盤を作ることができます。
実務での使い分けとコツ:営業レバレッジと経営レバレッジを活かす
では、日常の業務でどう使い分けるべきかを具体的に考えてみましょう。まず、あなたの組織が直面している課題を整理します。売上は伸びているのに利益が薄い場合は、営業レバレッジの効きが弱い可能性があり、顧客獲得コストが高すぎるか、平均受注額が低いかを調べます。
この時、経営レバレッジを強化する手段としては、固定費の見直し、仕入れの一括契約、テナントのコスト最適化、事業のスケールメリットを生かすための設備投資の検討などが挙げられます。
製品やサービスの価格設定も重要です。値上げが難しい場合には、バンドル戦略やセット販売、顧客生涯価値(LTV)を高める施策を組み合わせ、売上と利益のバランスを調整します。
実務での考え方をさらに深めると、二つのレバレッジを同時に見ることが大切だとわかります。例えば、月次の売上が増え始めたとき、営業のキャンペーンだけでなく、固定費の見直しと原価管理を同時に進めると、利益がより安定して伸びやすくなります。数値としては、売上高、利益率、平均単価、顧客獲得コスト、LTVなどをセットで追い、改善サイクルを回すことが鍵です。
このように、営業レバレッジと経営レバレッジを別々のものとして捉えるのではなく、相互補完的な要素として計画に組み込むのが、現場で最も効果的なアプローチです。
友達との雑談風に、営業レバレッジと経営レバレッジの違いを深掘りする話題。営業は売上を増やす動き、経営はコスト構造を整える動き。両方を組み合わせると、短期の利益と長期の成長を両立できるんだよ、という話をしてみました。





















