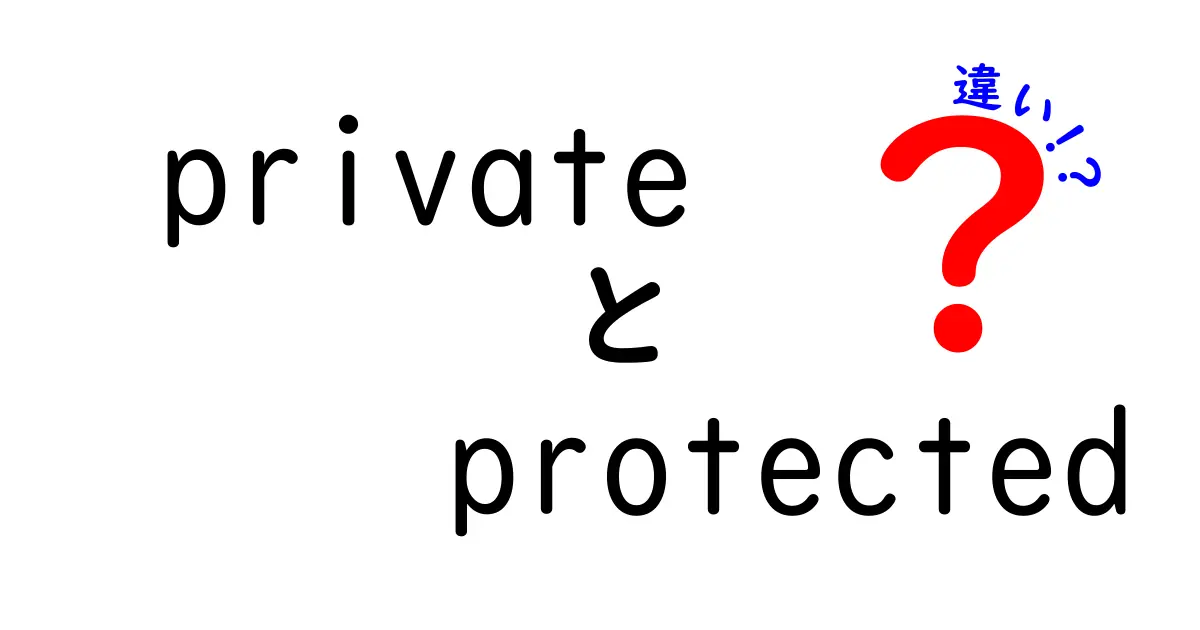

中嶋悟
名前:中嶋 悟(なかじま さとる) ニックネーム:サトルン 年齢:28歳 性別:男性 職業:会社員(IT系メーカー・マーケティング部門) 通勤場所:東京都千代田区・本社オフィス 通勤時間:片道約45分(電車+徒歩) 居住地:東京都杉並区・阿佐ヶ谷の1LDKマンション 出身地:神奈川県横浜市 身長:175cm 血液型:A型 誕生日:1997年5月12日 趣味:比較記事を書くこと、カメラ散歩、ガジェット収集、カフェ巡り、映画鑑賞(特に洋画)、料理(最近はスパイスカレー作りにハマり中) 性格:分析好き・好奇心旺盛・マイペース・几帳面だけど時々おおざっぱ・物事をとことん調べたくなるタイプ 1日(平日)のタイムスケジュール 6:30 起床。まずはコーヒーを淹れながらニュースとSNSチェック 7:00 朝食(自作のオートミールorトースト)、ブログの下書きや記事ネタ整理 8:00 出勤準備 8:30 電車で通勤(この間にポッドキャストやオーディオブックでインプット) 9:15 出社。午前は資料作成やメール返信 12:00 ランチはオフィス近くの定食屋かカフェ 13:00 午後は会議やマーケティング企画立案、データ分析 18:00 退社 19:00 帰宅途中にスーパー寄って買い物 19:30 夕食&YouTubeやNetflixでリラックスタイム 21:00 ブログ執筆や写真編集、次の記事の構成作成 23:00 読書(比較記事のネタ探しも兼ねる) 23:45 就寝準備 24:00 就寝
privateとprotectedの基本的な違いを押さえよう
プログラミングの世界には「アクセス修飾子」というルールがあります。この仕組みはクラスの中身をどう公開するかを決め、外部のコードからの見え方をコントロールします。特に private と protected は設計の安定性や拡張性に大きな影響を与える要素です。private は「そのクラスの内部だけに見える」という意味で、外部のコードは直接アクセスできません。protected は「そのクラスと、それを継承した派生クラスからは見える」が原則です。この差を理解しておくと、APIをきれいに保ちつつ、将来の拡張を楽に設計できます。
この考え方は言語ごとに少しずつ違います。Java や C# では private は厳密にクラス内だけ、protected は同一パッケージ(Java の場合)や派生クラスからアクセス可能というニュアンスがあり、PHP では private と protected の役割はより直感的に分かれています。結局のところ大事なのは「誰が責任を持つのか」「誰が内部の実装を読むべきか」という二つの問いに答えることです。これを踏まえて設計すると、将来の修正や他の開発者との協働がぐっと楽になります。
実務では、private を多用して内部の状態を外部から守ることでクラスの不整合を防ぎます。一方、protected は拡張の余地を残したいときに役立ちます。例えばあるゲームの「キャラクター」クラスを考えてみましょう。HP や攻撃力といったデータは private にして、public な入出金メソッドを通じてのみ残高を動かします。ここで、攻撃力の一部を派生クラスが異なるルールで計算したい場合、protected なメソッドを用意しておけば、派生クラスはその一部だけを変えられます。これが private のままだと、派生クラスが内部実装にまで踏み込んで改良するのが難しくなります。
以下の表はざっくりとした比較ですが、現場の設計を考えるときの判断材料になります。
使用する言語の公式ドキュメントも必ず参照して、自分のプロジェクトに合った意味を確認しましょう。
この表は「ざっくりの違い」を示すものです。言語ごとに細かな差異があり、実際には公式ドキュメントを読むのが安全です。実際に手を動かしてみると、private と protected の感覚はすぐに身につきます。触れて確かめることが成長の近道です。
ある日、私と友だちは放課後の雑談で private と protected の違いを深掘りしてみた。友だちは「private は壁みたいに強く、外部には決して見せない感じ」と言い、私は「protected は家族のように、継承関係の仲間だけが中身に触れられる余地を残す」という例えを返した。私たちは銀行口座クラスとキャラクターのクラスを思い浮かべ、残高を private にして公開 API で操作する設計と、派生クラスが金利計算や属性の拡張を protected 経由で行える拡張設計のバランスを話し合った。結局のところ設計の美しさは「誰に責任があるのか」を明確にすること。private は内部の整合性を守る盾、protected は将来の拡張を滑らかにする緩衝材。こうした考えを日常のコード設計にも持ち込むと、チーム全体の理解が深まり、後々の保守も楽になるという結論に至った。





















